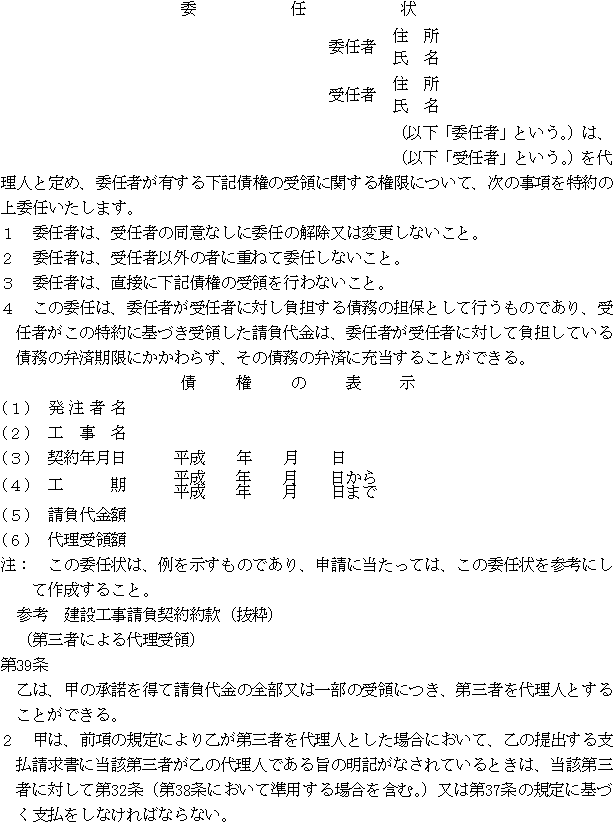○片品村建設工事執行規則
平成7年3月30日規則第4号
片品村建設工事執行規則
片品村建設工事執行規則(昭和37年規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、村の支出の原因となる、建設業法(昭和24年法律第100号以下「法」という。)第2条に規定する建設工事(以下「工事」という。)の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第3条の規定による特定調達契約については、それぞれ、当該特定調達に係る入札公告の定めるところによるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該に定めるところによる。
(1) 主管課長 片品村課設置条例(昭和50年条例第13号。以下「課設置条例」という。)第1条に規定する課のうち、工事の執行に関する事務を分掌する課(以下「主管課」という。)の長をいう。
(2) 契約担当者 村長又は片品村財務規則(昭和39年規則第2号。以下「財務規則」という。)第2条第1項第9号に掲げる者のうち、工事に係る支出負担行為を担当する者をいう。
(工事の執行方法)
第3条 工事の執行は、直営及び請負とする。
(直営工事)
第4条 直営による工事(以下「直営工事」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 工事の性質上請負に付することが不適当であるとき。
(2) 急施を要し請負に付するいとまのないとき。
(3) 請負契約を締結することができないとき。
(4) 特に直営とする必要があるとき。
2 直営工事の執行手続について必要な事項は、村長が別に定めるところによる。
(請負工事)
第5条 請負による工事(以下「請負工事」という。)は、財務規則の定めるところにより一般競争入札、指名競争入札又は随意契約により請負者を定めて執行するものとする。
(工事請負者の資格要件)
第6条 契約担当者は、次の各号に該当する者でなければ工事の請負をさせてはならない。ただし、第1号に掲げる者以外で法第3条第1項ただし書に該当し、かつ、あらかじめ村長の承認を受けたもの及び第2号に掲げる者以外の者で、特に緊急を要する工事又は特別の技術を要する工事についてあらかじめ村長の承認を受けたものについては、この限りでない。
(1) 法第3条第1項の規定により許可を受けている者
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第2項の規定により別に告示で定める資格を有する者
(工事実施計画書の作成等)
第7条 主管課長は、工事について配当を受けた予算に基づき毎年度上半期(4月から9月までの期間をいう。)及び下半期(10月から翌年3月までの期間をいう。)ごとに工事実施計画書(様式第1号)を作成して村長の決裁を受けなければならない。ただし、災害応急工事等緊急を要する工事その他計画を立て難い工事については、この限りでない。
(工事実施計画変更計画書の作成等)
第8条 主管課長は、前条に規定する工事実施計画書に定められていない工事(前条ただし書の規定に該当するものを除く。)を当該工事実施計画書に係る期間内において実施しようとするとき又は前条に規定する工事実施計画書に定められた今回起工経伺額又は支払計画額を変更しようとするときは、工事実施計画書の例による工事実施計画変更計画書を作成して村長の決裁を受けなければならない。
(工事実施計画書の送付)
第9条 主管課長は、工事実施計画書(工事実施計画変更計画書を含む。)について村長の決裁を受けたときは、直ちにその写しを総務課長及び会計管理者に送付するものとする。
(起工の決裁)
(指名人の決裁)
第11条 主管課長は、財務規則第134条又は第135条の規定により指名競争入札に参加させる者を指名しようとするときは、指名人の決定伺書(様式第3号)に指名業者調書(様式第4号)を添付して契約担当者の決裁を受けなければならない。
(指名の通知の決裁)
2 契約担当者及び主管課長は、前項の規定による指名を受けた者が入札を辞退しようとするときは、入札辞退届(様式第6号)を提出させるものとする。
(入札等)
第13条 契約担当者は、請負工事の入札を行うときは、財務規則第126条の規定により入札に参加した者に入札書(様式第7号)を作成させ、これを工事ごとに封筒に入れてその表面に工事名、工事場所並びに住所及び氏名を記載させて、公告又は指名通知書に示した日時に提出させるものとする。
3 主管課長は、落札者が決定し財務規則第129条第2項の規定により請負契約を締結しようとするときは、工事請負契約締結伺書(様式第9号)を作成し、契約担当者の決裁を受けなければならない。
4 第1項の規定は、財務規則第140条の規定による随意契約の見積書を徴する場合について準用する。
(契約書)
第14条 契約担当者が財務規則第142条第1項の規定により作成する請負契約に係る契約書は、建設工事請負契約書(様式第10号)及び建設工事請負契約約款(様式第10号の2)に基づいて作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により必要のない事項については、この限りでない。
2 前項の請負契約が議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第1号)第2条の規定に該当する場合は、建設工事請負仮契約書(様式第10号の3)に基づいて仮契約書を作成しなければならない。この場合において、当該請負契約に係る議会の議決がなされたときは、作成された仮契約書を本契約に基づく契約書とみなす。
(契約書の作成を省略する場合)
(契約保証金)
第16条 契約担当者は、請負契約を締結する場合において、当該工事について、金銭的保証が求められている場合にあっては、請負金額の100分の10以上の契約保証金を納付させ、又は、契約保証金に代わる担保を提供させなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を免除できると認められる場合はこの限りでない。
2 金銭的保証では履行保証として十分でないと認められる契約を締結する場合にあっては、公共工事履行保証証券に係る保証(かし担保特約を付したものに限る。)とし、契約保証金は100分の30以上を納付させるものとする。
(請負工事の執行、指示、報告等)
第17条 主管課長は、その事務を分掌する工事の請負契約が締結されたときは、その工事の取扱について、次に掲げるところによらなければならない。
(1) 既定設計の変更を要する場合は、遅滞なく設計変更伺書(様式第14号)に必要書類等を添えて契約担当者に報告し、その指示を受けなければならない。
(2) 天災事変その他の理由により、工事を一時停止し、又は中止することが有利と認めたときは、直ちに臨機の措置を講じ、速やかに契約担当者に報告してその指示を受けること。
(3) 財務規則第155条第2項の規定により工事の履行の延期について文書の提出があったときは、その理由を調査し意見を添えて契約担当者に進達する。
(4) 請負者が約定期間内に工事を完成する見込がないときは、その状況を調査し、意見を添えて契約担当者に報告すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、重要又は異例と認められる事態が生じた場合は、遅滞なく契約担当者に報告してその指示を受けること。
(一括委任又は一括下請)
第18条 契約担当者は、その事務を分掌する請負工事について、法第22条第3項の規定に基づく書面による承認を必要とするものがあるときは、当該申請理由、下請業者の能力その他について審査し、適当と認めたときは承認を与えることができる。
(債権譲渡の承認)
第19条 契約担当者は、財務規則第153条第1項ただし書の規定により、請負契約によって生じた債権の譲渡について承認を与えようとするときは、請負者から債権譲渡承認願(様式第15号)を提出させなければならない。
2 契約担当者は、前項の規定により債権譲渡承認願の提出があったときは、これを審査し、次の各号に該当すると認めたときは、これを承認することができる。
(1) 村税その他村に対する納付金を滞納していないこと。
(2) 国、県その他公共団体等から債権の取立について、債権差押え等の通知を受けていないこと。
(3) 願出の理由が債権譲渡をしないと工事の施行に支障があると認められること。
(4) 債権の譲受人が銀行若しくはこれに類する金融機関、群馬県建設事業協同組合又は地方公共団体であること。
(債権譲渡通知書)
第20条 契約担当者は、前条の規定による承認をした場合において、請負者が債権の譲渡を完了したときは、遅滞なく確定日付のある債権譲渡通知書(様式第16号)を提出させなければならない。
(工期の延長)
(工事の変更)
第22条 主管課長は、財務規則第155条第1項及び第2項規定により、請負契約の内容を変更しようとするときは、工事請負契約変更伺書(様式第18号)により契約担当者の決裁を受け、契約の相手方と工事請負契約変更協議書(様式第19号)により協議しなければならない。
2 契約担当者は、前項の規定により請負契約の内容を変更したときは、財務規則第155条第3項の規定により、直ちに請負者から工事変更請書(様式第20号)を提出させなければならない。
(前金払をしている場合の部分払の支払い限度額)
第23条 前払金をしている場合の工事について、財務規則第160条第1項本文の規定により部分払をすることができる金額は、次に掲げる算式により計算して得た額とする。
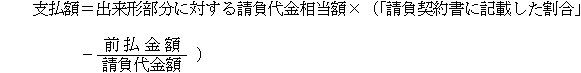
(部分払いの回数)
第24条 請負工事一件についてすることができる部分払の回数で、財務規則第160条第2項に規定する支払回数の取扱は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、契約担当者が特別の理由があると認めたときは、1回に限り増加することができるものとする。
請負金額 | 前金払をしていない場合 | 前金払をしている場合 |
150万円以下 | 支払わない | 支払わない |
150万円を超え 500万円以下 | 2回以内 | 1回 |
500万円を超え 1,000万円以下 | 3回以内 | 2回 |
1,000万円を超えるもの | 4回以内 | 3回 |
(出来形調書)
第25条 契約担当者は、請負者から契約に係る部分払を受けるための出来形検査願(様式第21号)の提出があったときは、検査員を指定して当該工事の出来形を検査させ、その結果を当該請負者に通知するものとする。
2 前項の規定により、指定された検査員は、検査を修了したときは、出来形調書(様式第22号)を作成してこれを契約担当者に報告しなければならない。
(工事の完成通知等)
第26条 契約担当者は、請負者が、工事の履行完了の届出をしようとするときは、工事完成通知書(様式第23号)を提出させなければならない。
2 主管課長は、その事務を分掌する請負契約に係る工事の工事完成通知書の提出があったときは、調査し、適正と認めたときは、当該工事完成通知書を添えて、その旨を契約担当者に報告するものとする。
(検査)
第27条 請負工事に係る検査については、財務規則及び片品村建設工事検査規則(平成2年規則第7号)の定めるところによるものとする。
(請負代金の請求)
第28条 契約担当者は、請負工事がしゅん工検査に合格したときは、当該請負工事に係る請負者から請負代金請求書(様式第24号)を提出させるものとする。
(書類の様式等)
第29条 契約担当者は、請負者が建設工事請負契約約款又は請書に基づいて次の表の左欄に掲げる書類を提出しようとするときは、当該右欄に掲げる様式により提出させなければならない。
区分 | |
共通事項 | |
工程表 | |
委任 請負工事一括 承認申請書 下請 | |
指定 監督員 通知書 変更 | |
指定 現場代理人等の 通知書 変更 | |
工事完成検査結果通知書 | |
完成引渡書 | |
前払金請求書 | |
部分払金請求書 | |
請負代金代理受領承諾申請書 | |
委任状 |
(準用)
第30条 第24条及び第27条の規定は、工事に要する物件の購入をする場合について、これを準用する。
(適用除外)
第31条 軽易な工事(法第3条第1項ただし書により、政令で定める軽微な工事をいう。)については、第6条から第10条まで、第14条、第15条、第17条、第28条及び第29条の規定は、適用しないことができる。この場合において第6条の規定は、40万円以下の工事の場合に限り、適用しないことができるものとする。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の片品村建設工事執行規則(昭和37年規則第1号)に基づいて締結されている建設工事の請負契約については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現に片品村建設工事執行規則に基づいて作成されている諸用紙のうち補正できるものについては、当分の間適宜補正して使用することができる。
附 則(平成8年5月8日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の片品村建設工事執行規則(平成7年片品村規則第4号)に基づいて締結されている建設工事の請負契約については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現に片品村建設工事執行規則に基づいて作成されている諸用紙のうち補正できるものについては、当分の間適宜補正して使用することができる。
附 則(平成15年11月6日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
様式第1号(規格A4)(第7条関係)
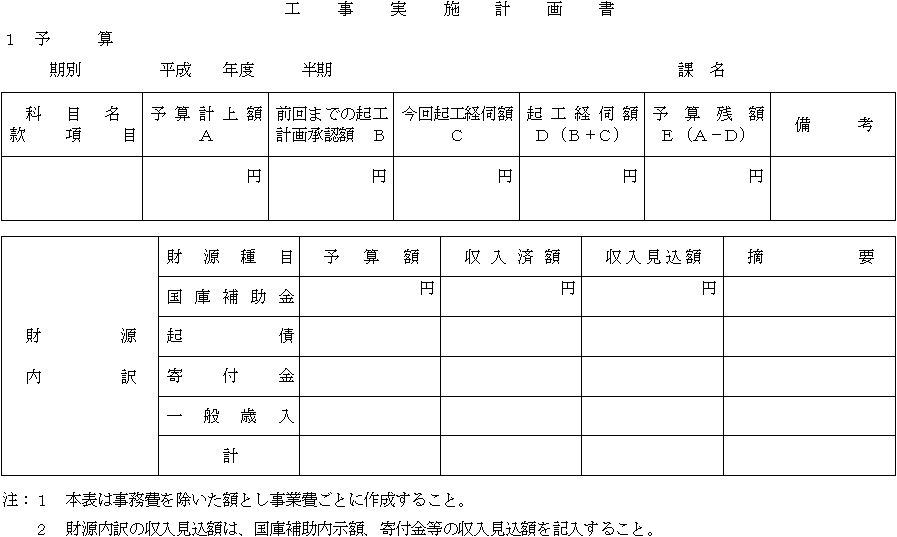
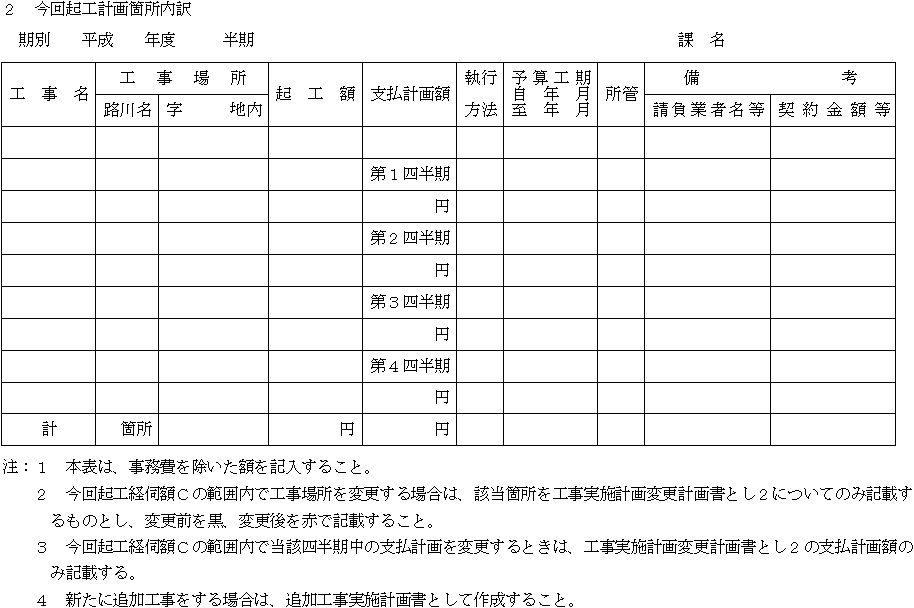
様式第2号(規格A4)(第10条関係)
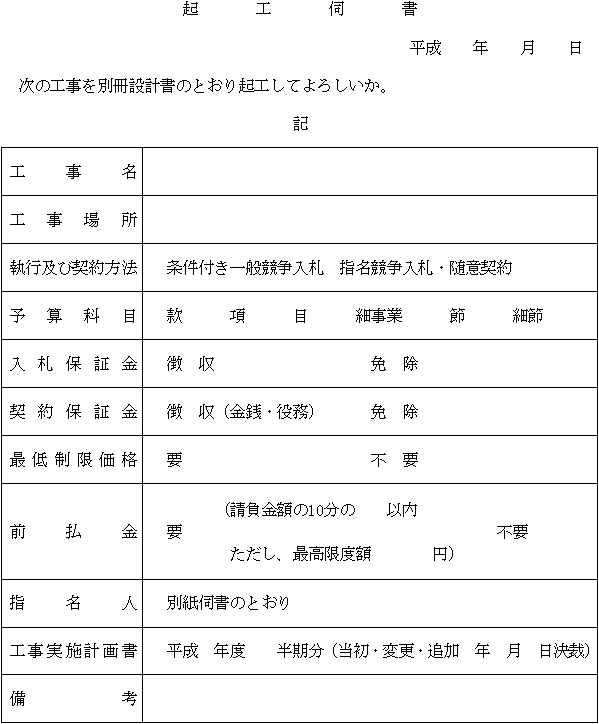
様式第3号(規格A4)(第11条関係)
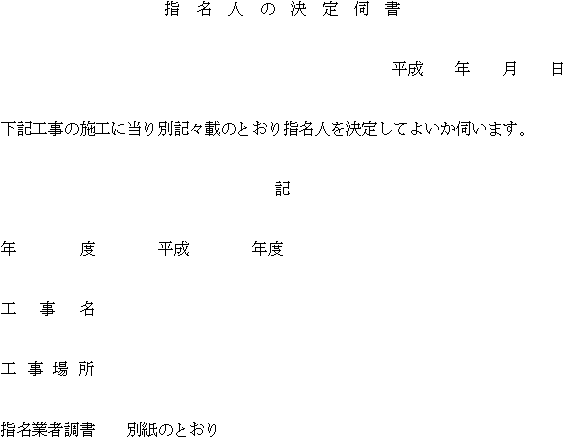
様式第4号(規格A4)(第11条関係)
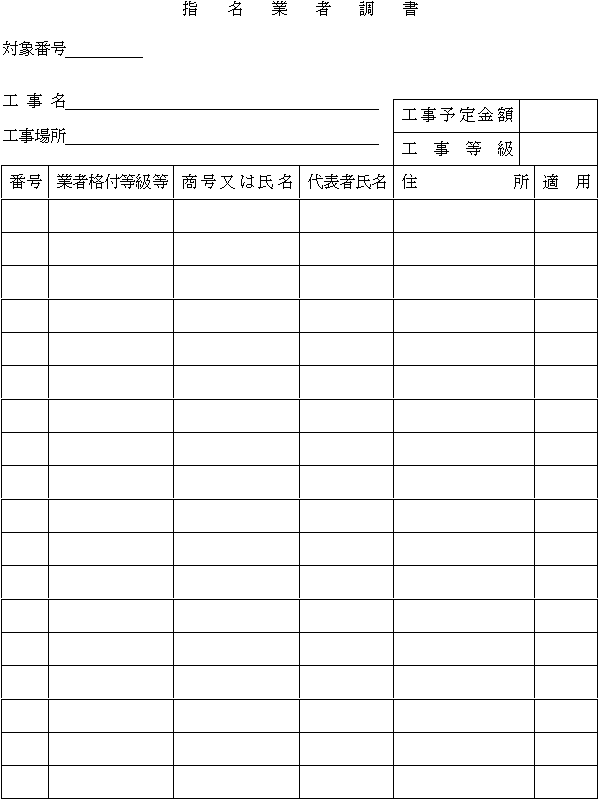
様式第5号(規格A4)(第12条関係)
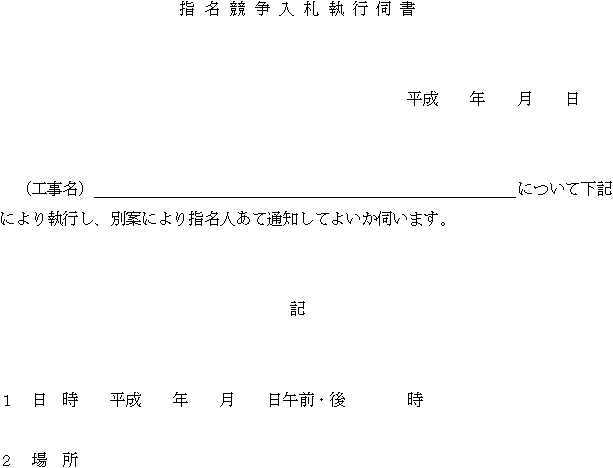
様式第6号(規格A4)(第12条関係)
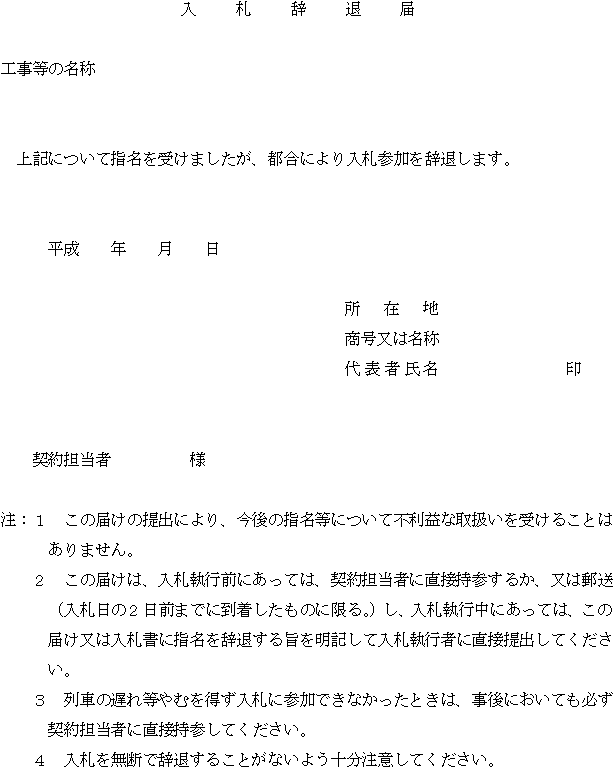
様式第7号(規格A4)(第13条関係)
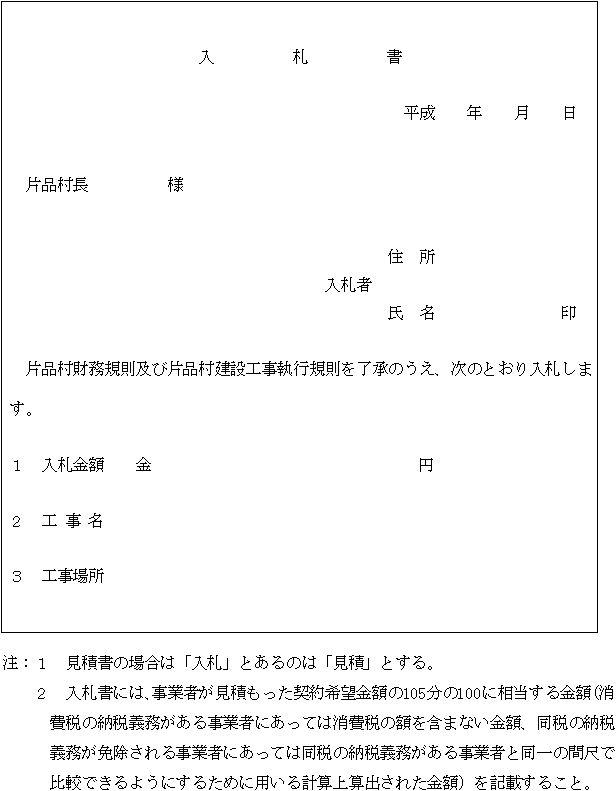
様式第8号(規格A4)(第13条関係)
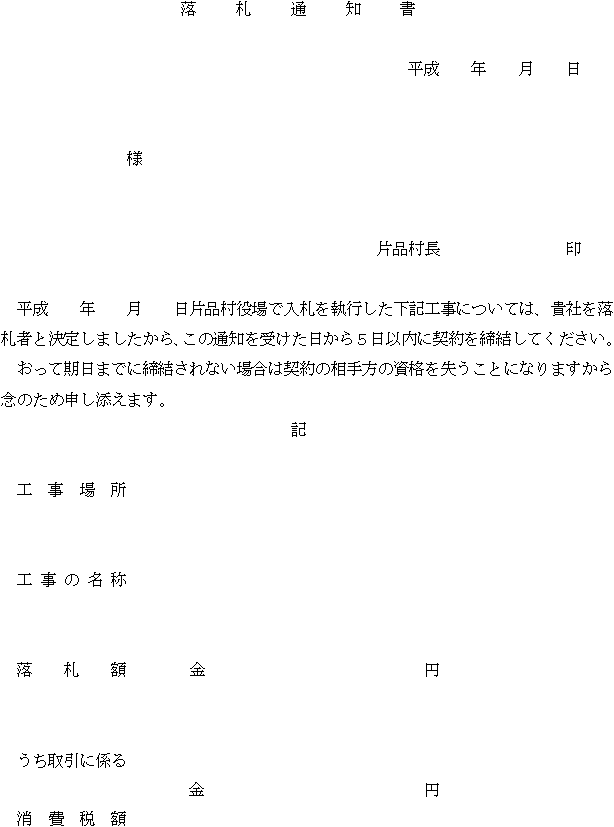
様式第9号(規格A4)(第13条関係)
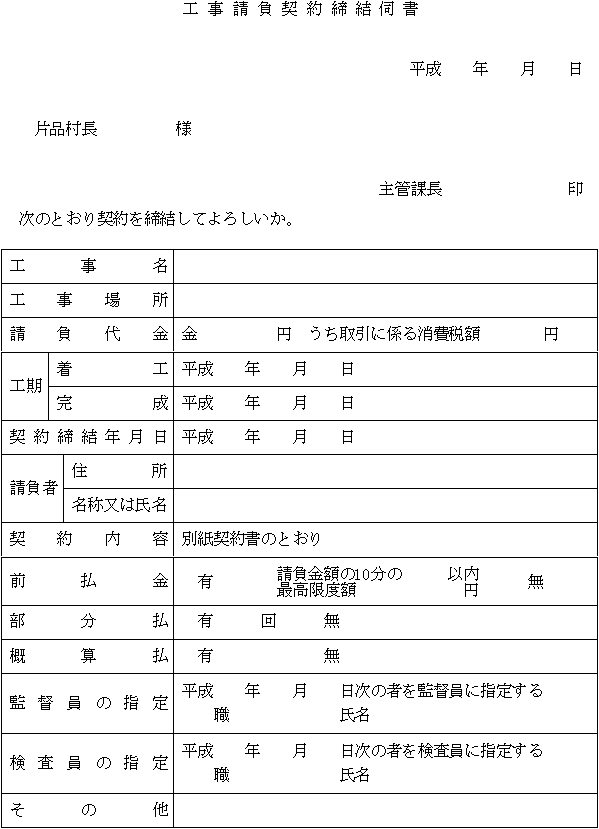
様式第10号(規格A4)(第14条関係)
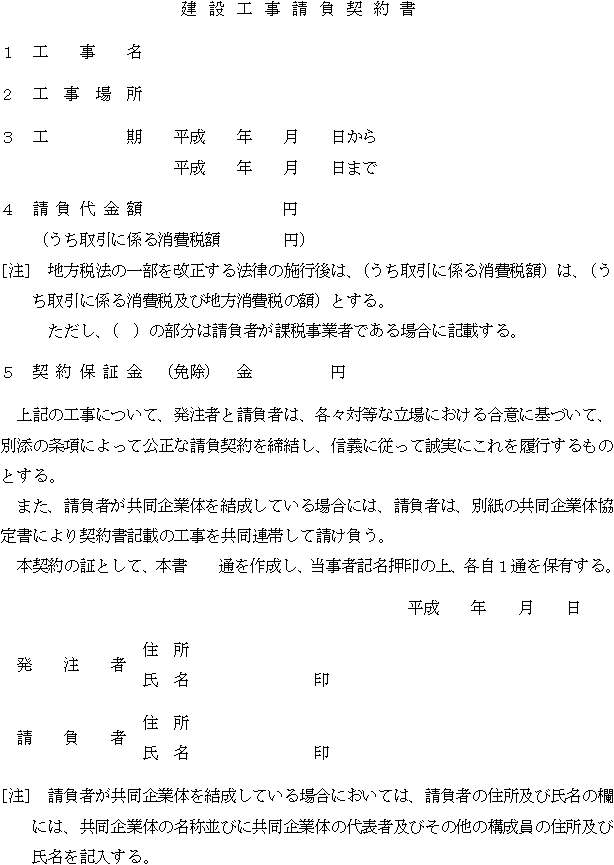
様式第10号の2(第14条関係)
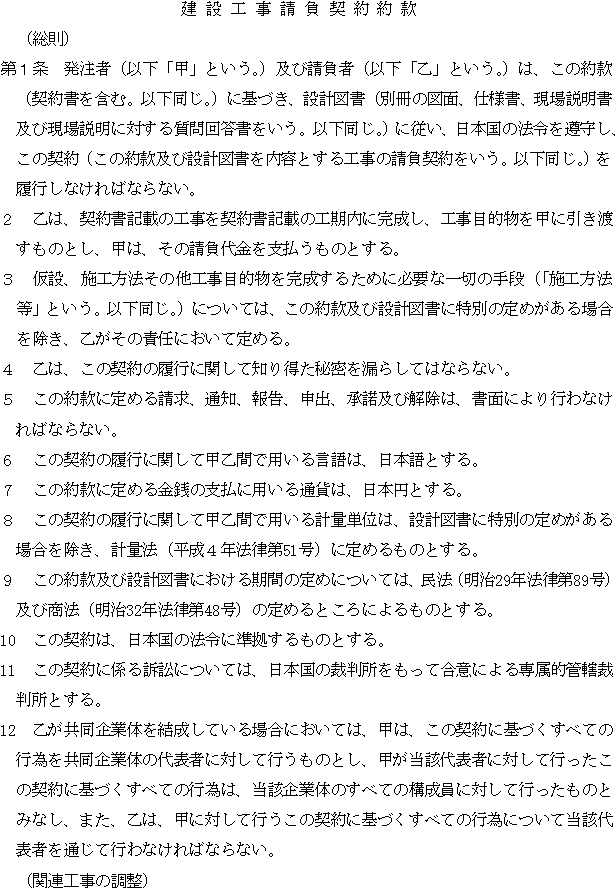
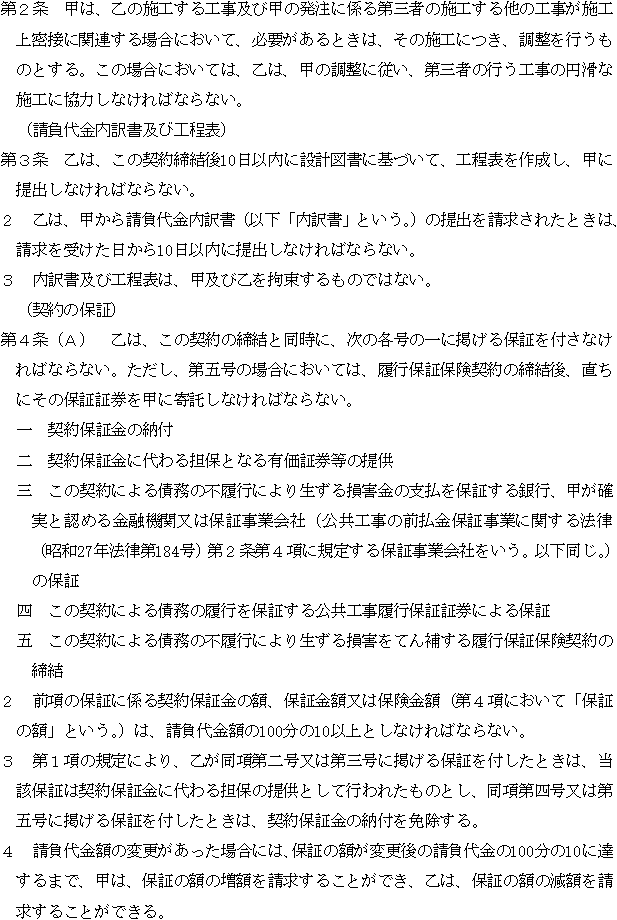
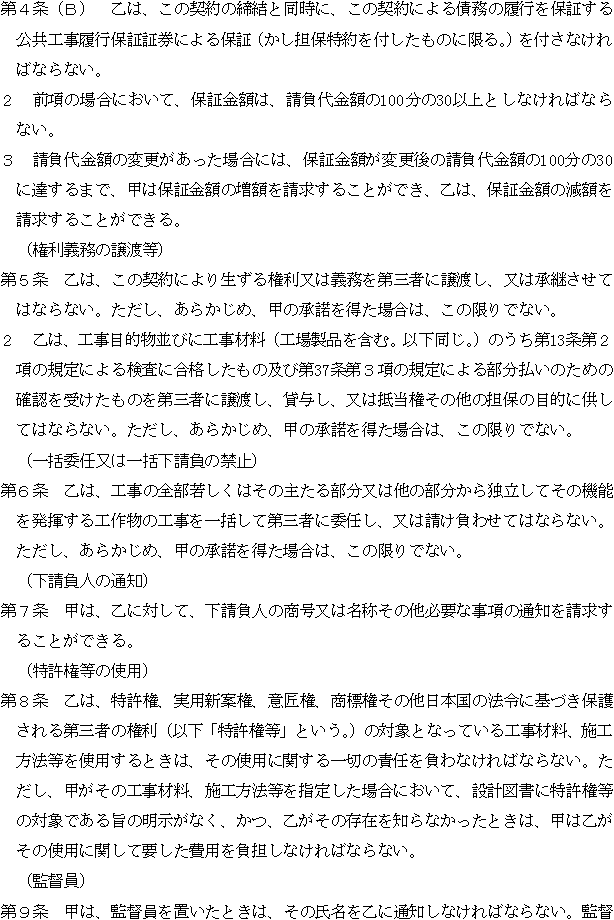
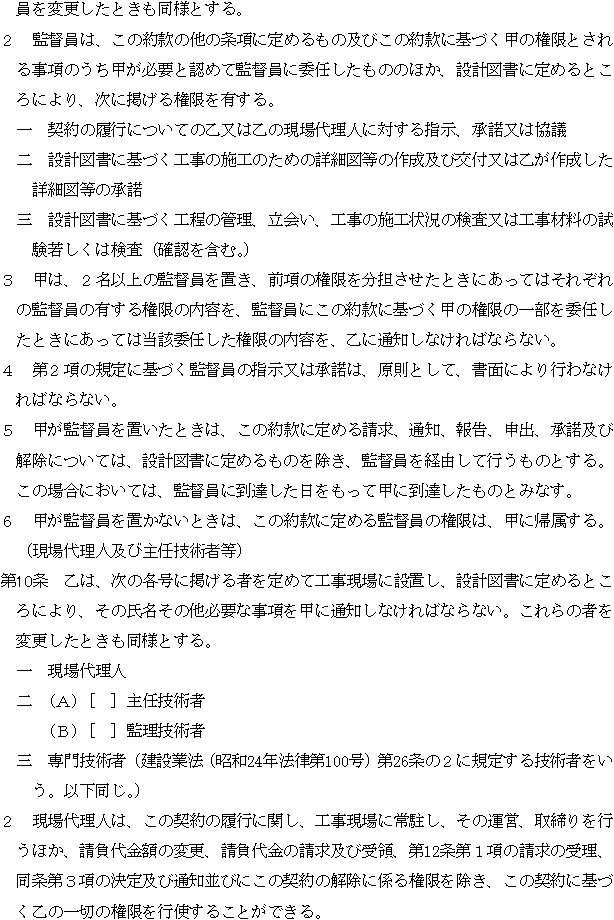
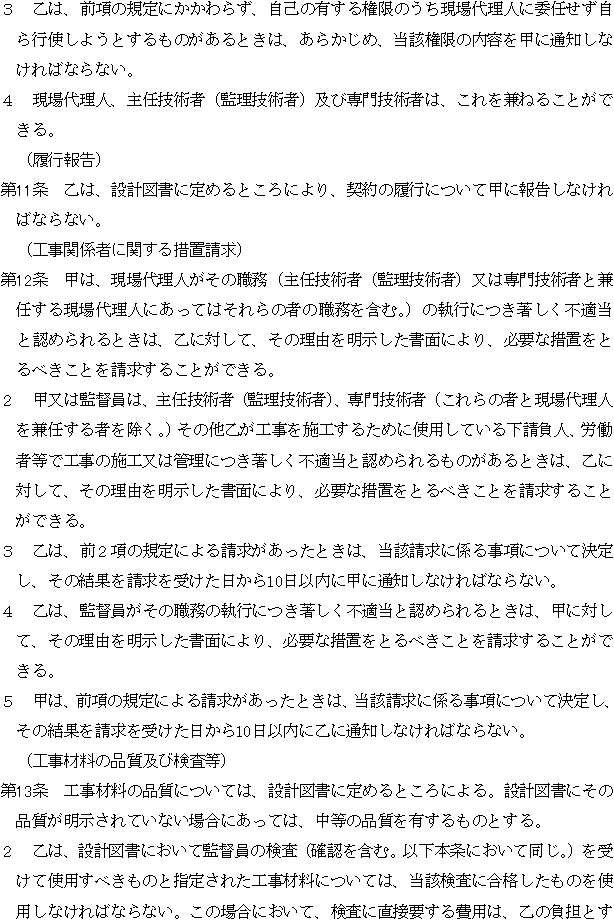
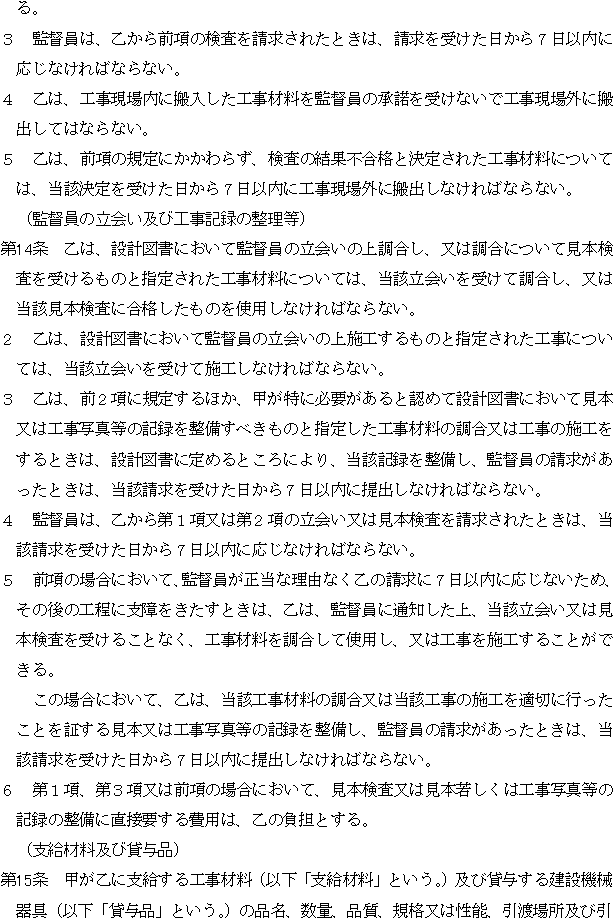
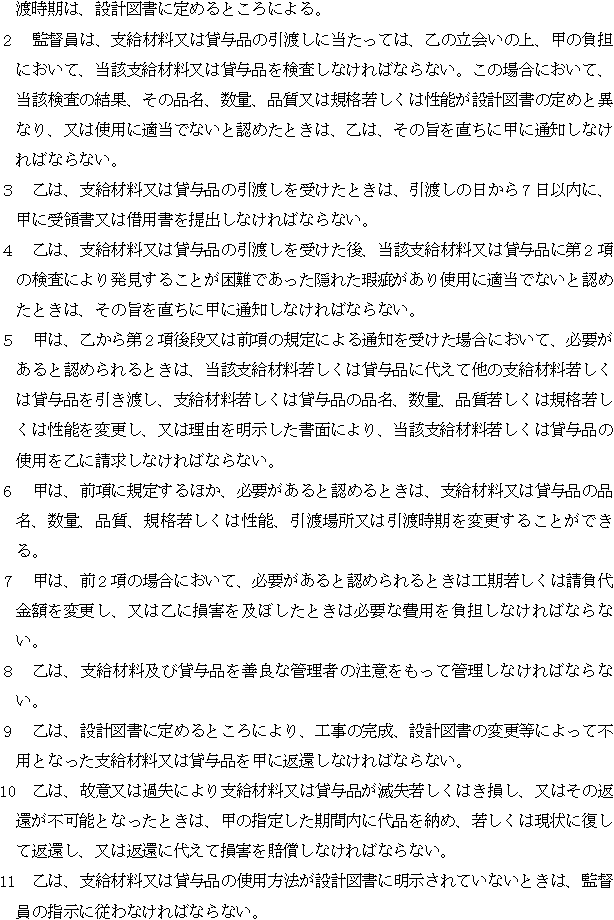
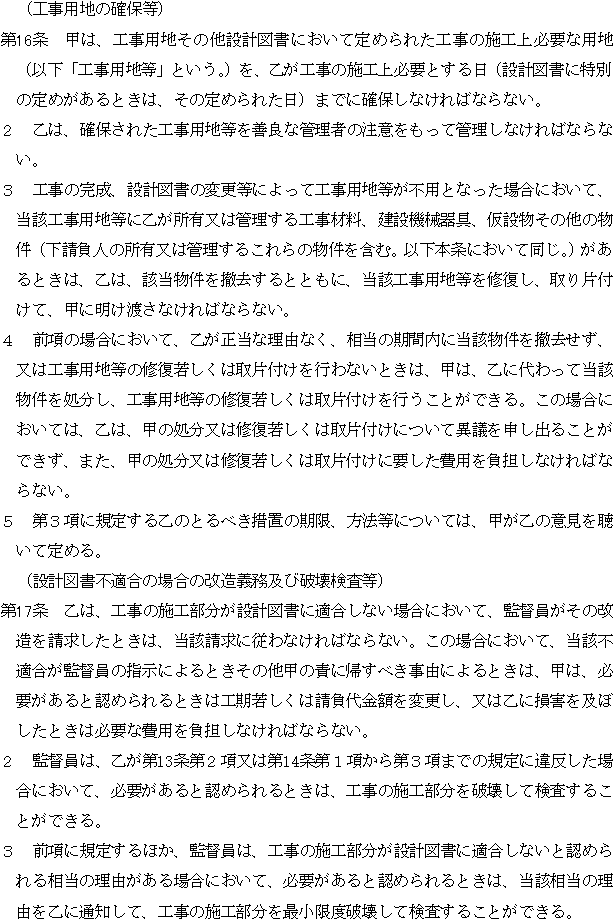
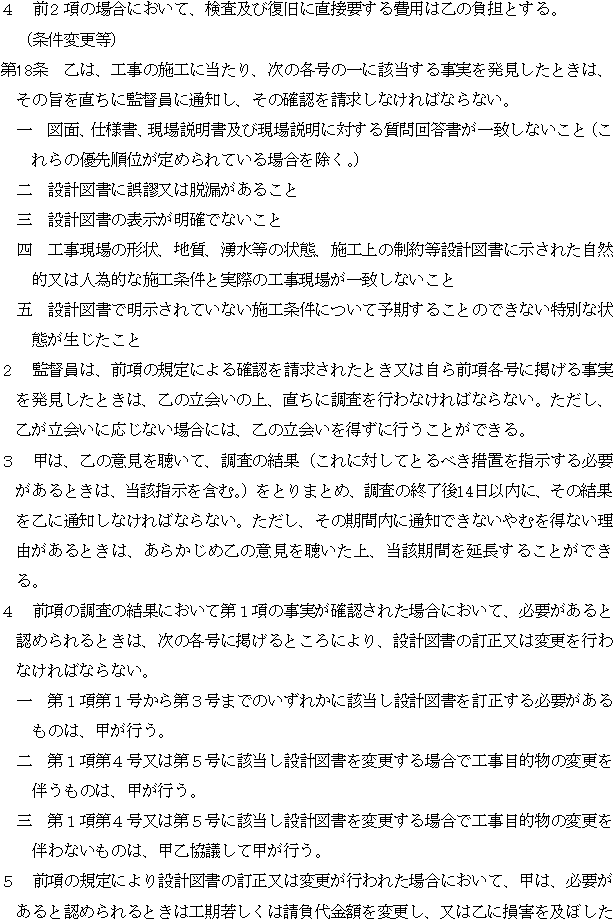
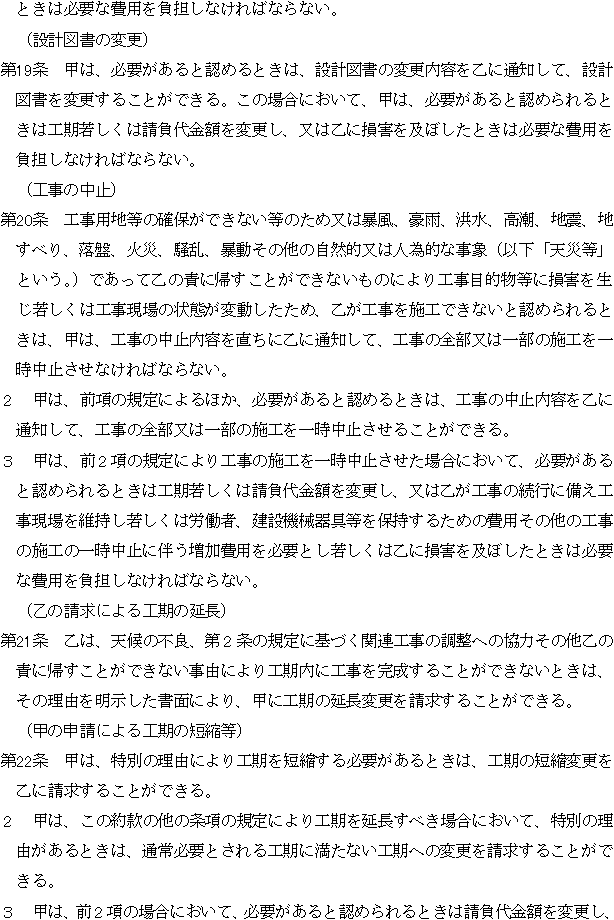
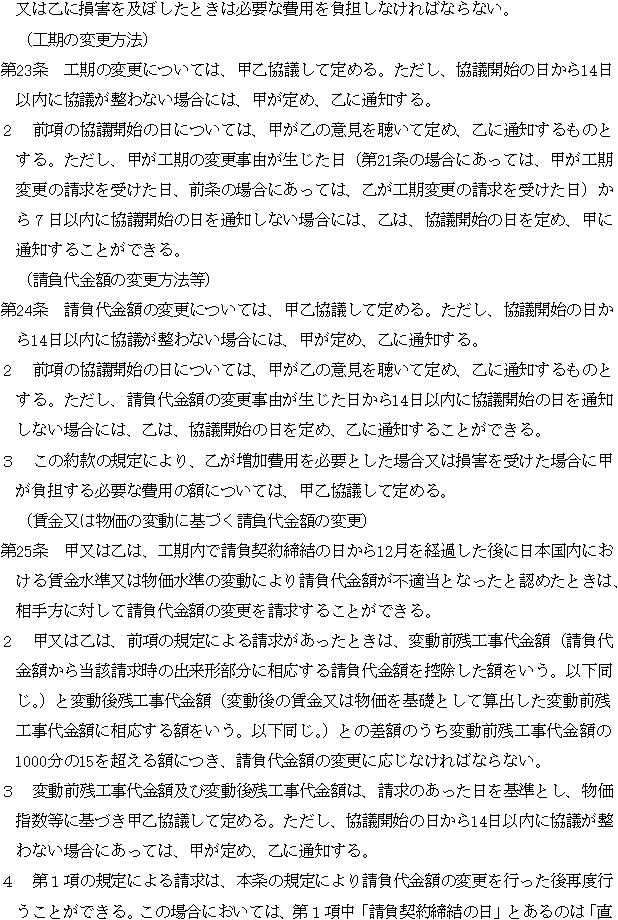
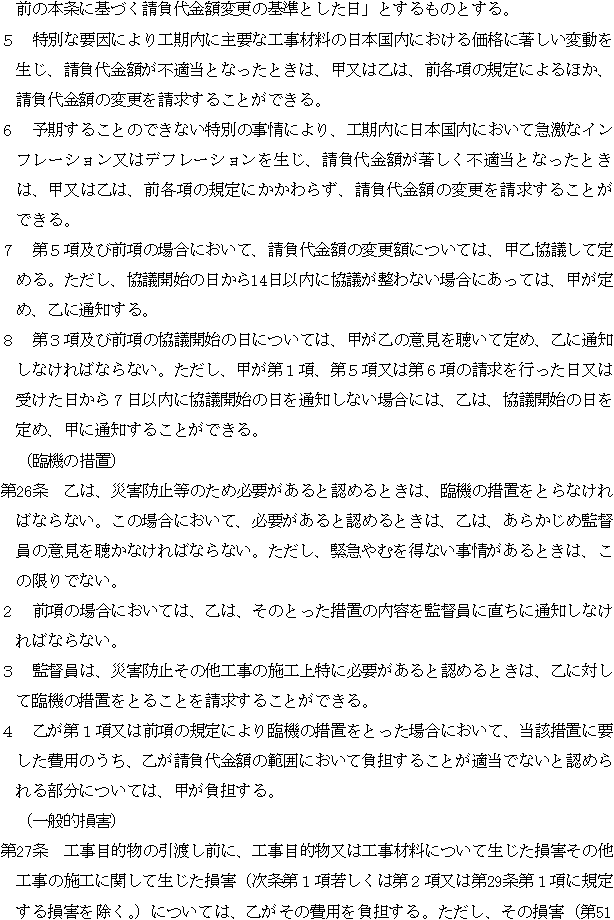
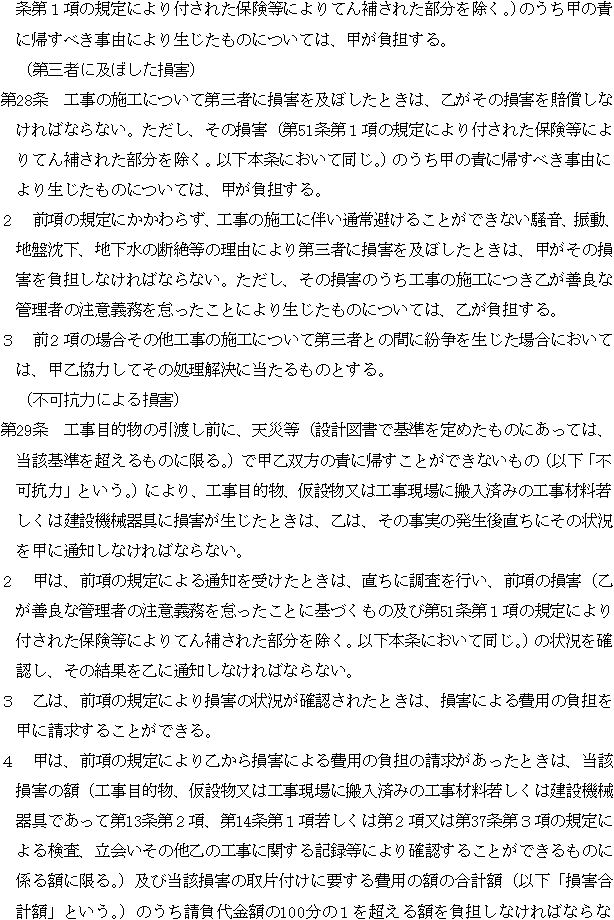
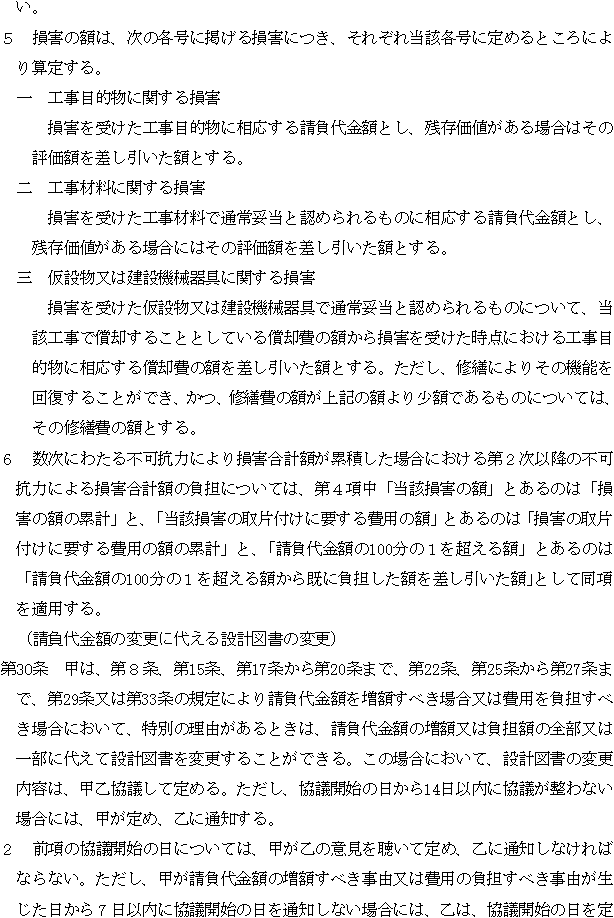
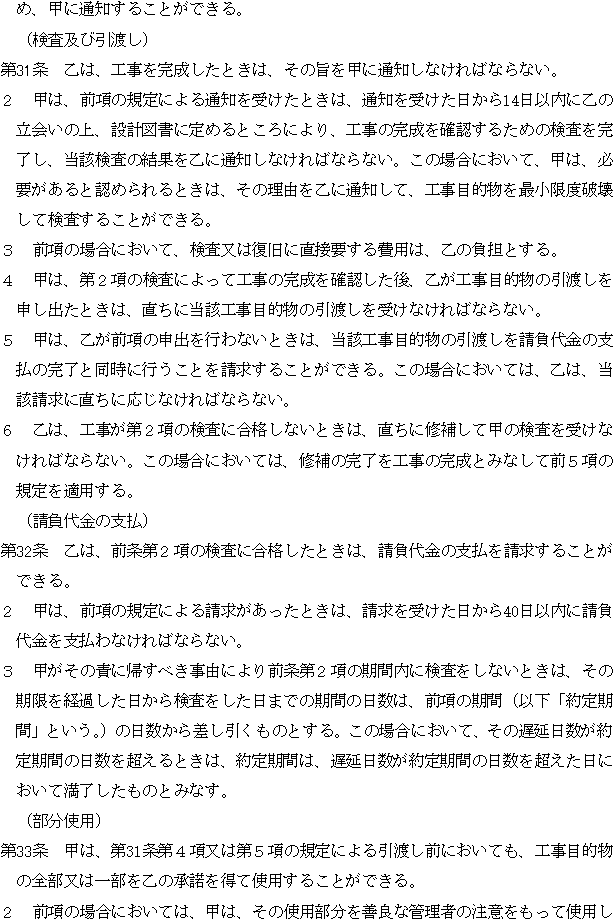
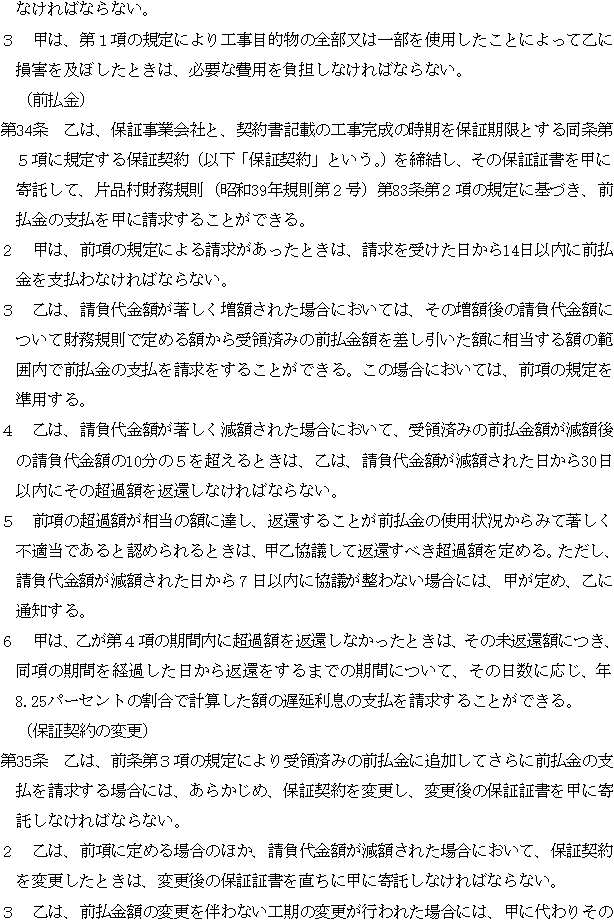
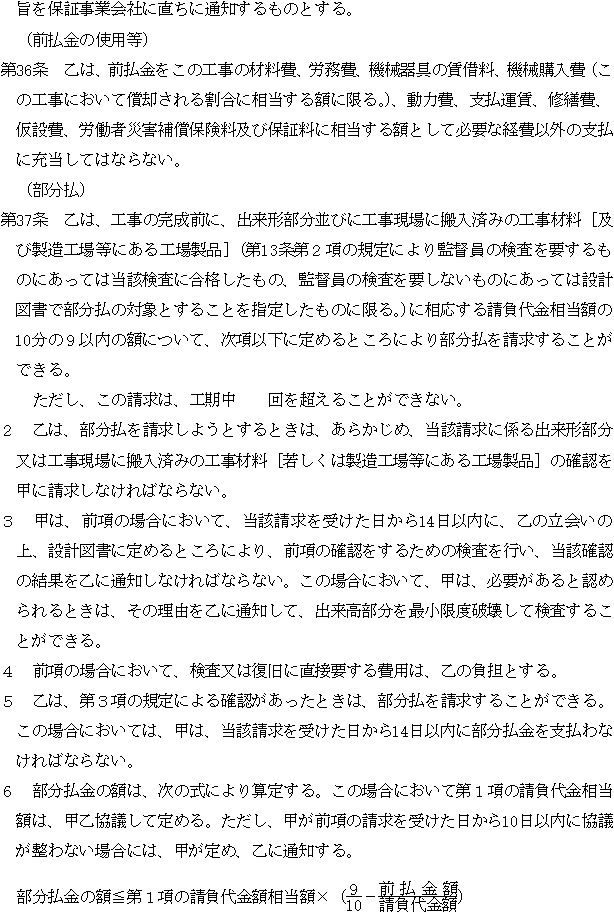
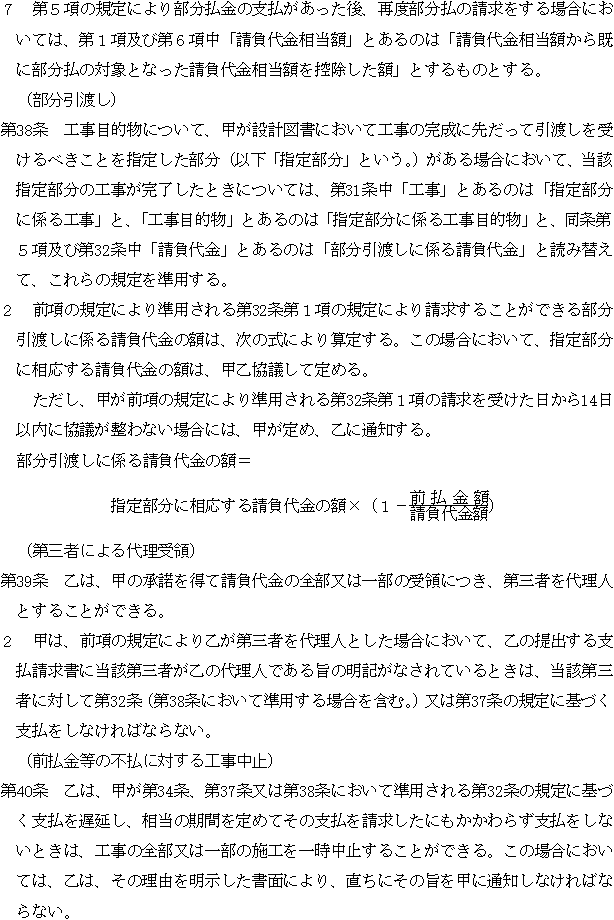
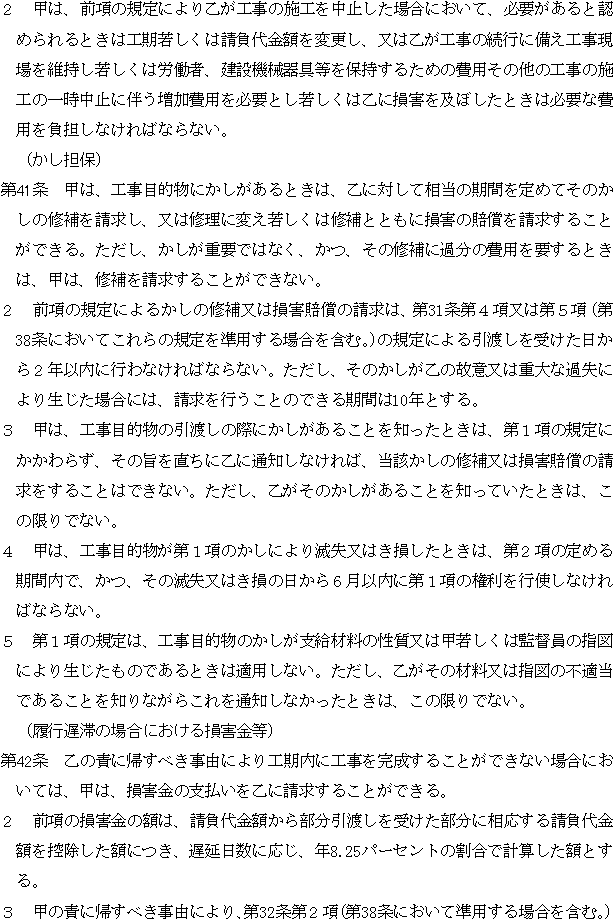
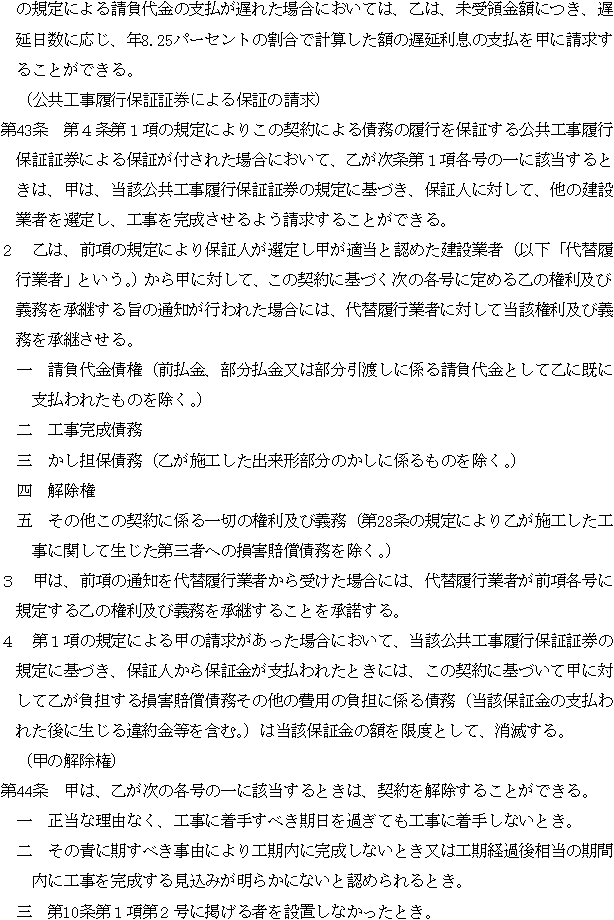
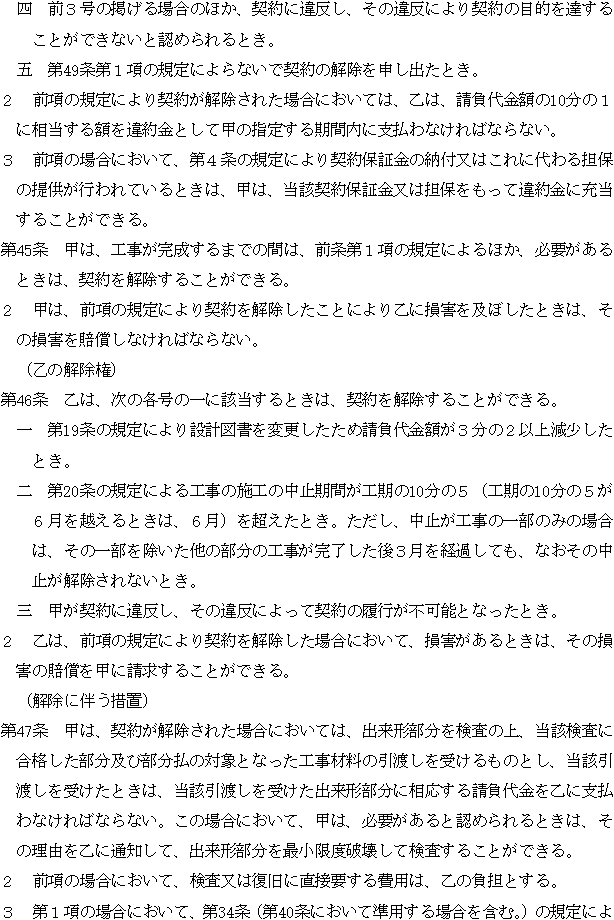
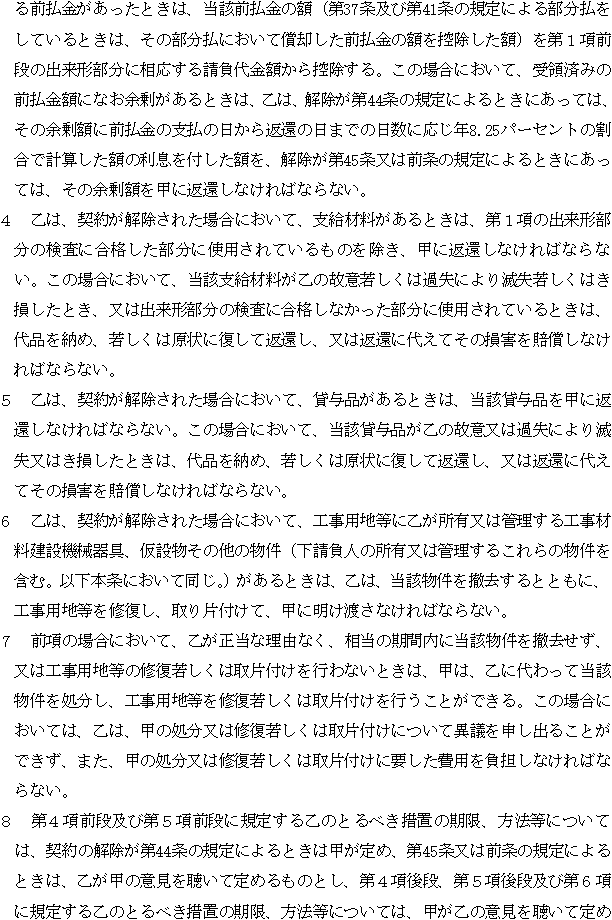
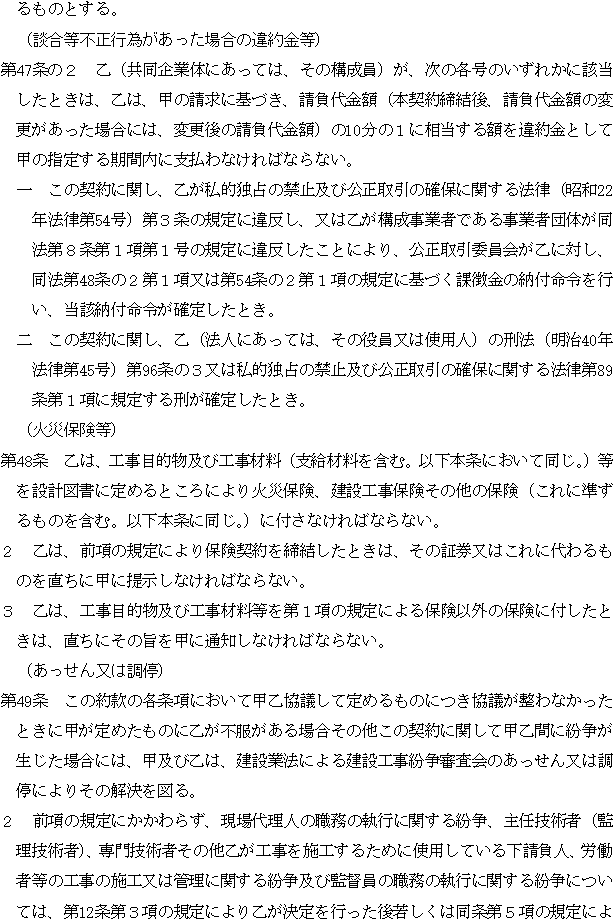
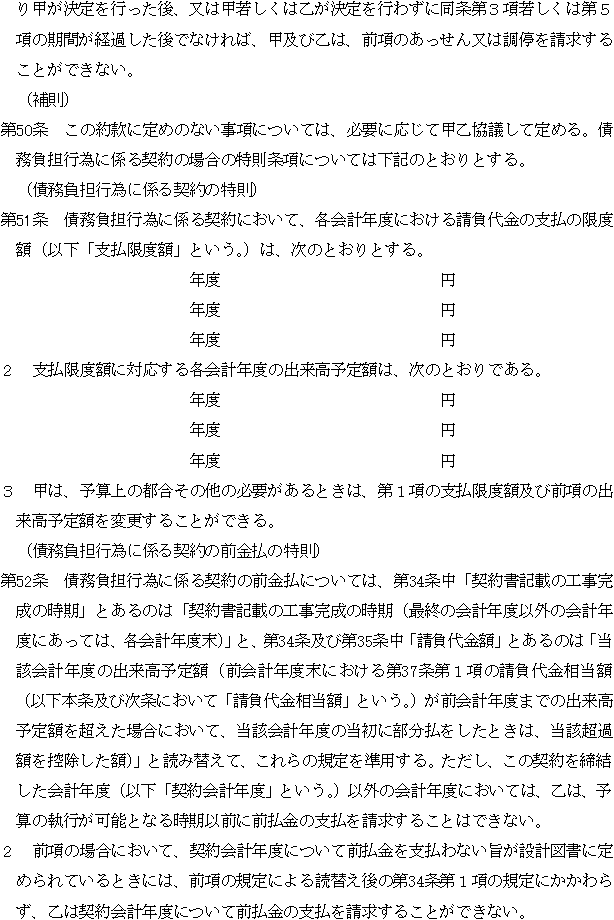
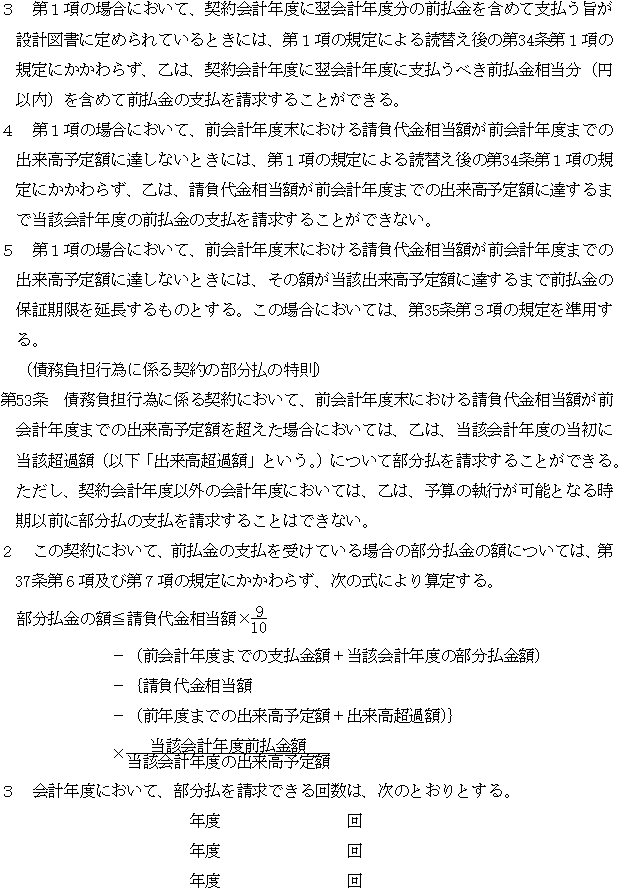
様式第10号の3(規格A4)(第14条関係)
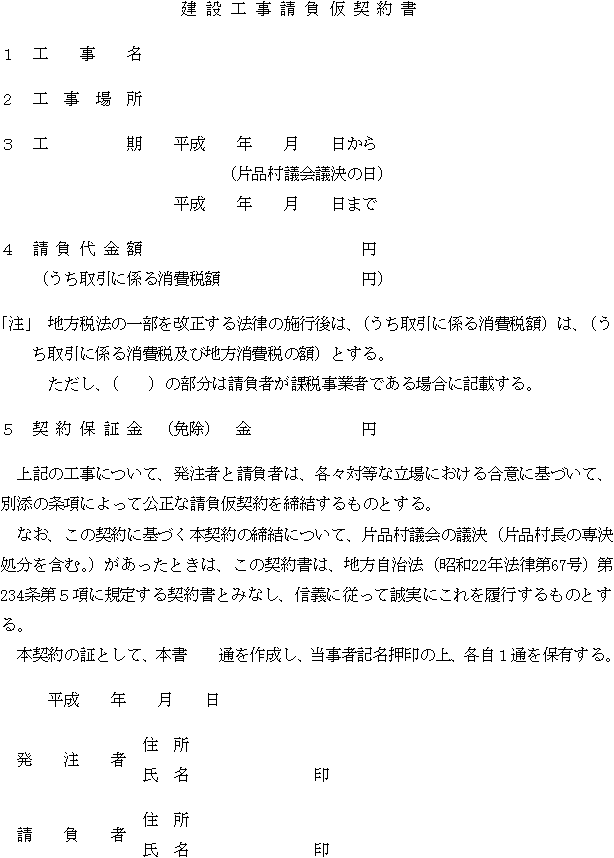
様式第11号(規格A4)(第14条関係)
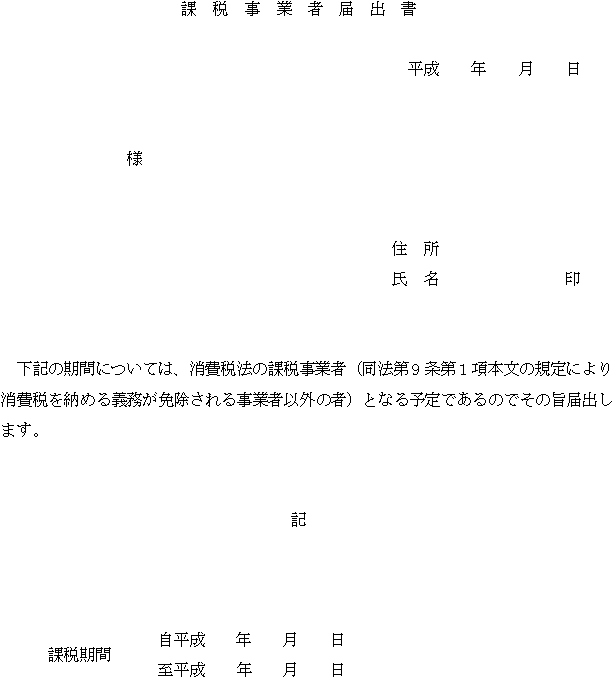
様式第12号(規格A4)(第14条関係)
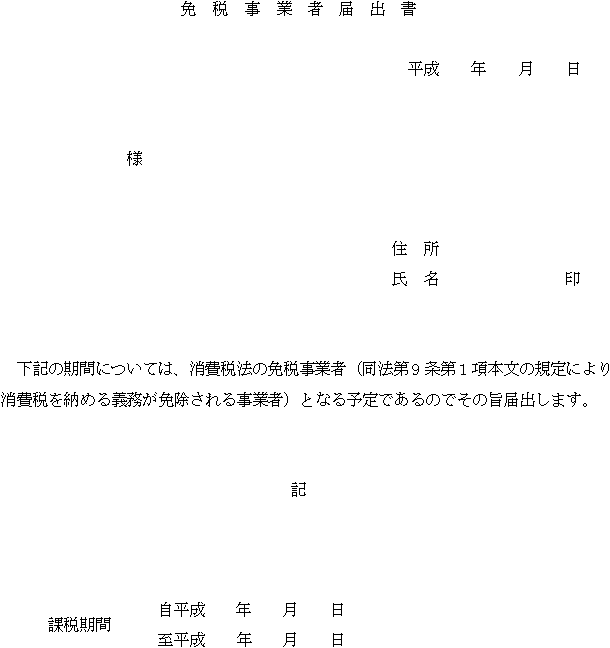
様式第13号(規格A4)(第15条関係)
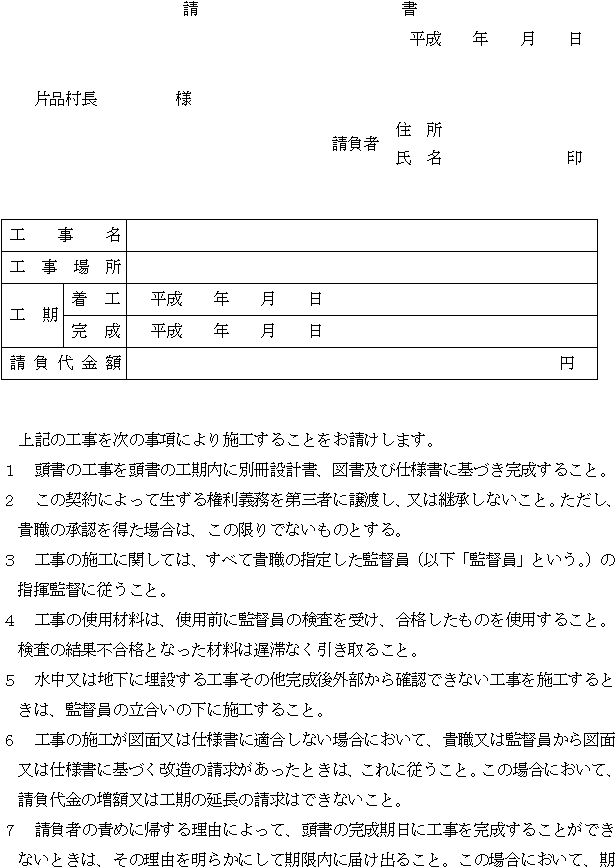
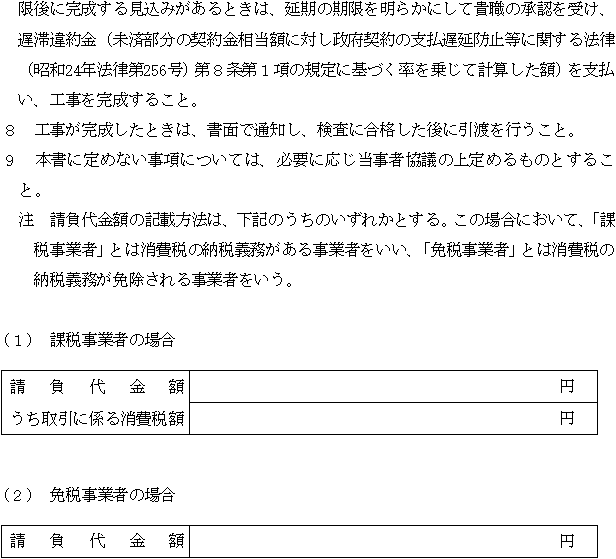
様式第14号(規格A4)(第17条関係)
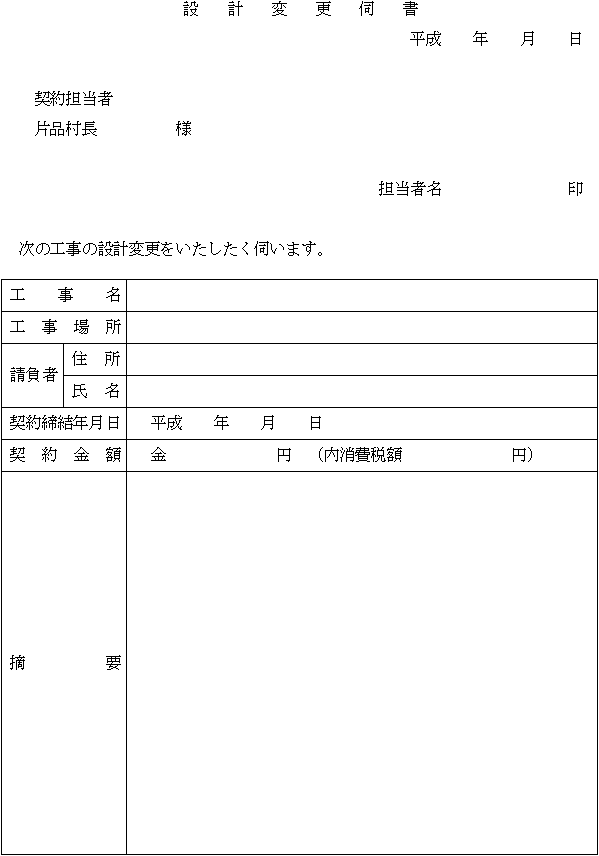
様式第15号その1(正)(規格はその1、その2共A4)(第19条関係)
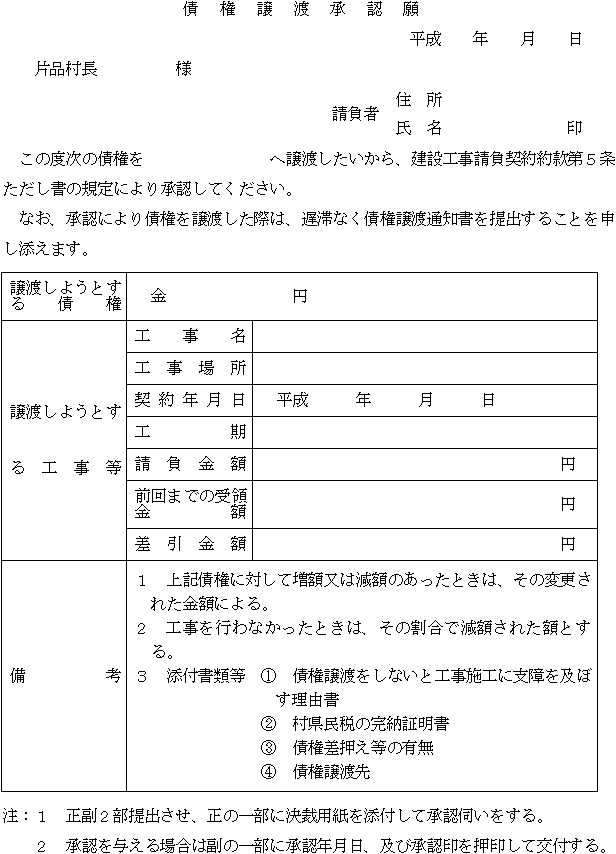
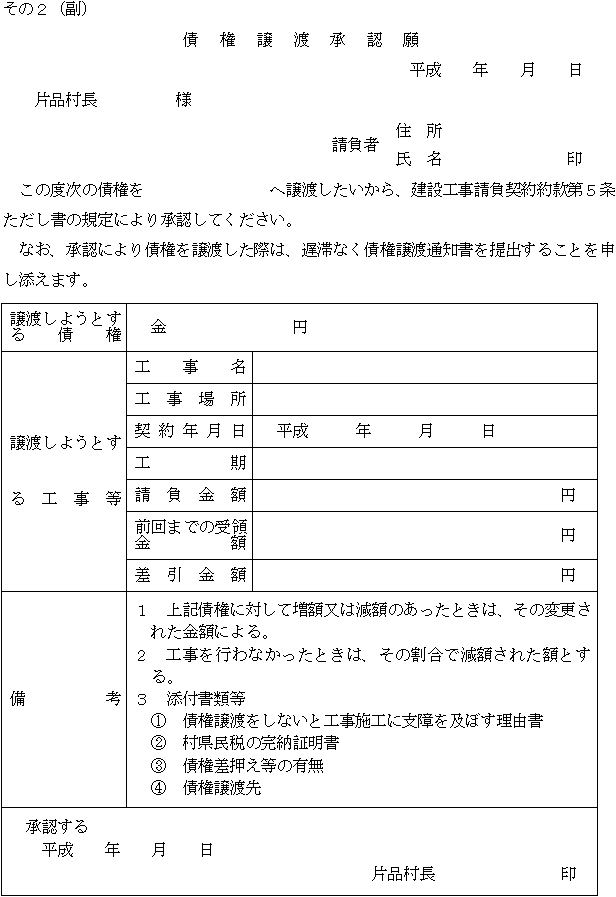
様式第16号(規格A4)(第20条関係)
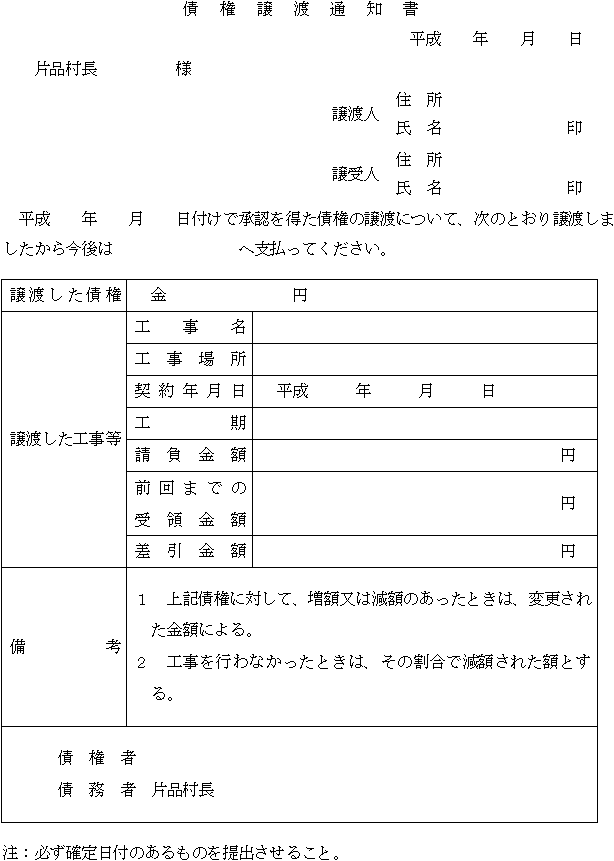
様式第17号(規格A4)(第21条関係)
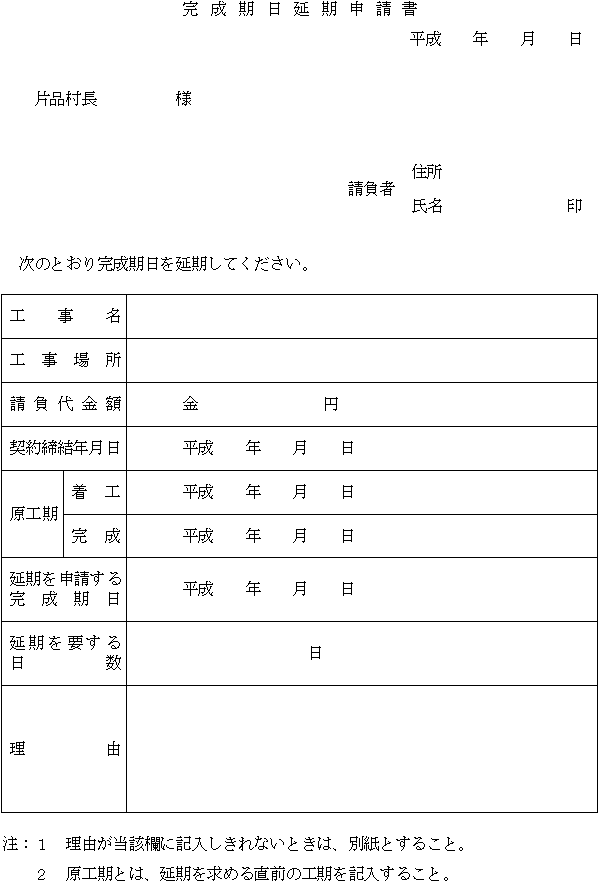
様式第18号(規格A4)(第22条関係)
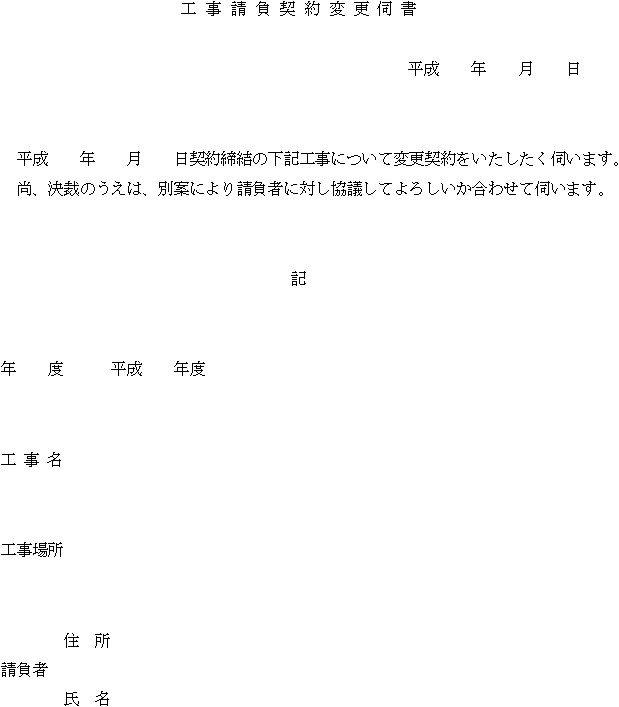
様式第19号(規格A4)(第22条関係)
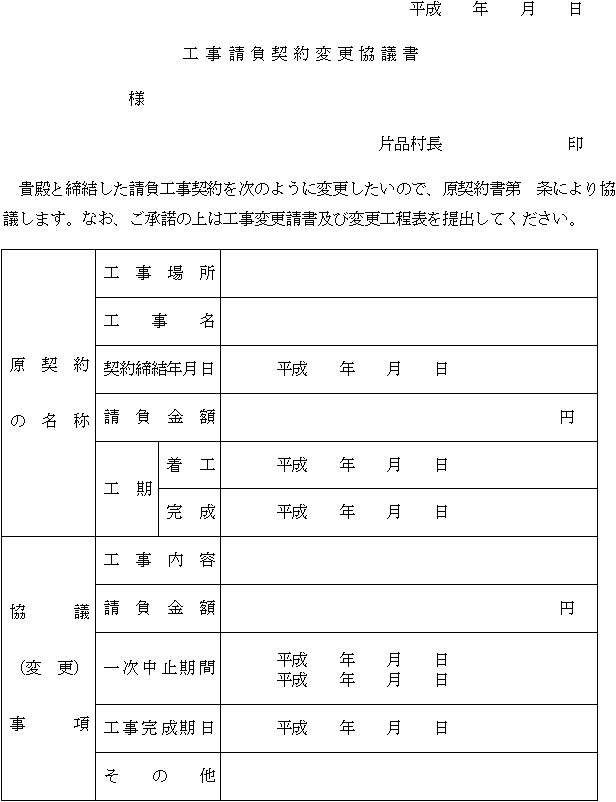
様式第20号(規格A4)(第22条関係)
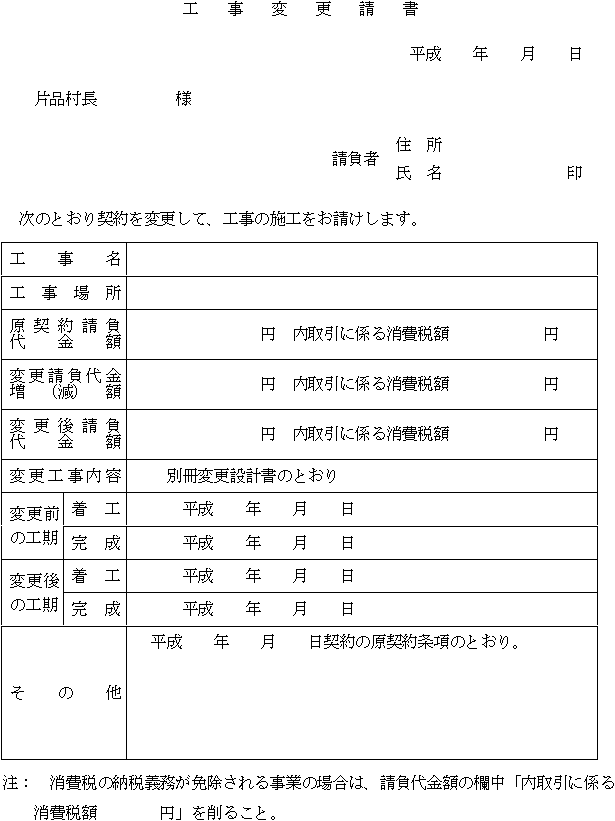
様式第21号(規格A4)(第25条関係)
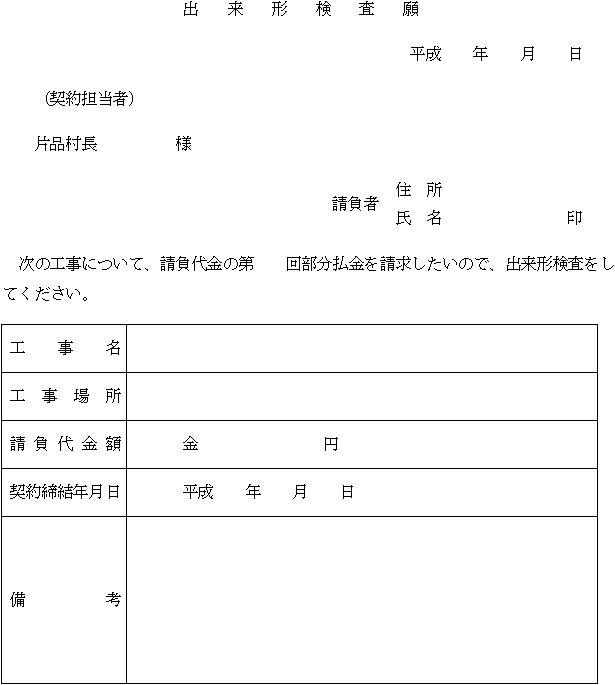
様式第22号(規格A4)(第25条関係)
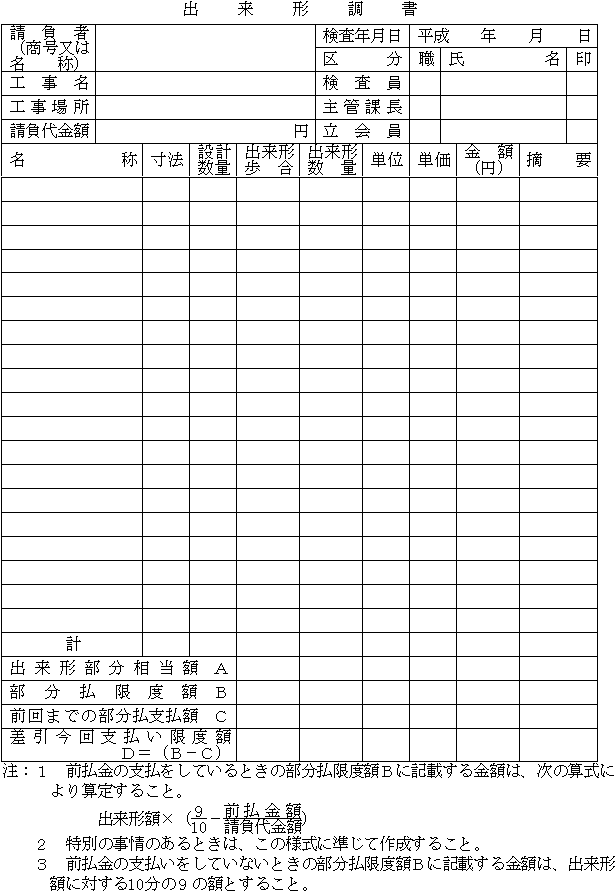
様式第23号(規格A4)(第26条関係)
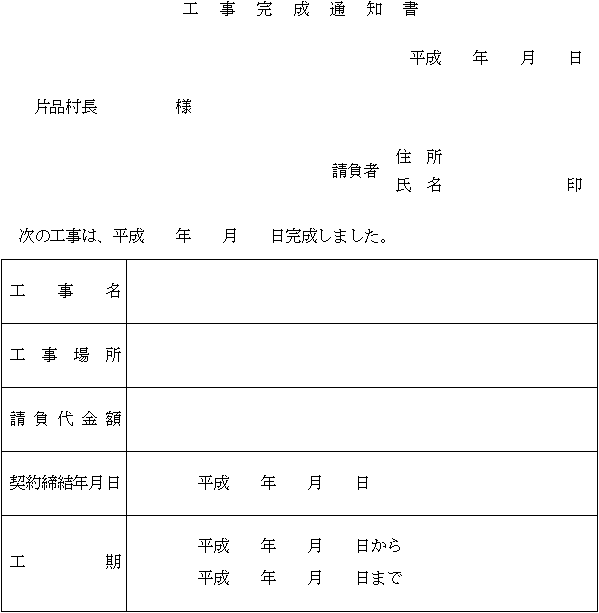
様式第24号(規格A4)(第28条関係)
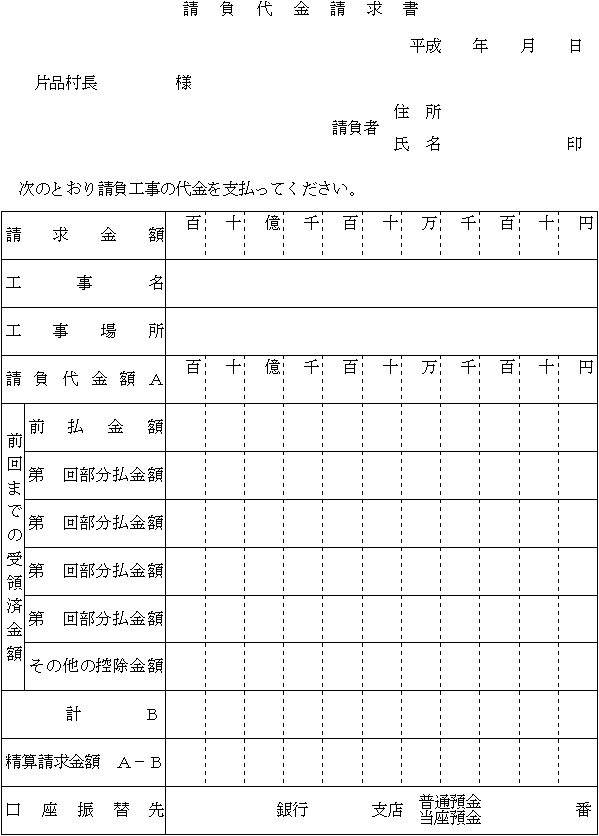
様式第25号(規格A4)(第29条関係)
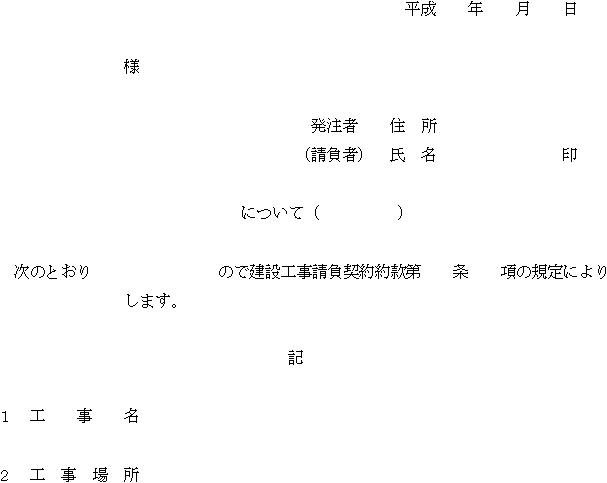
様式第26号(規格A4)(第29条関係)
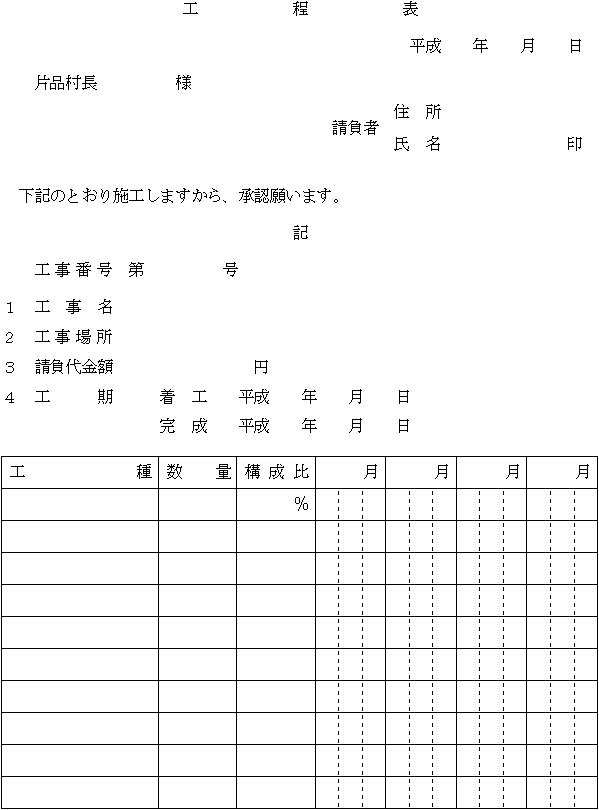
様式第27号(規格A4)(第29条関係)
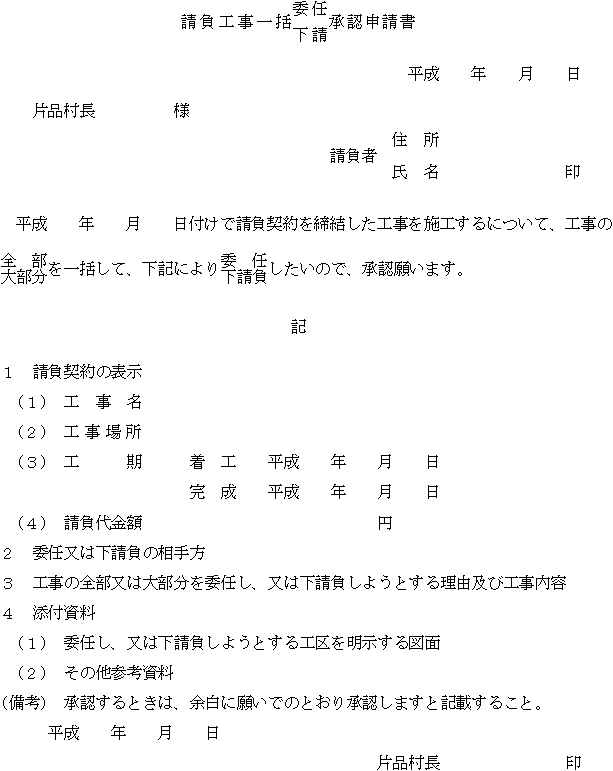
様式第28号(規格A4)(第29条関係)
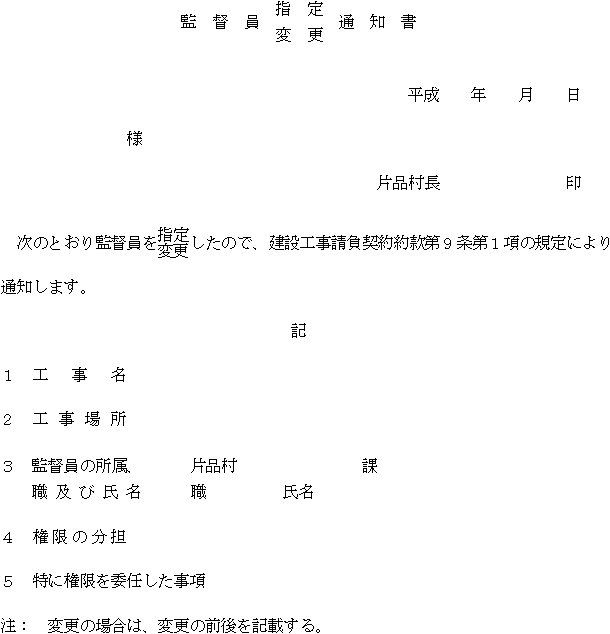
様式第29号(規格A4)(第29条関係)
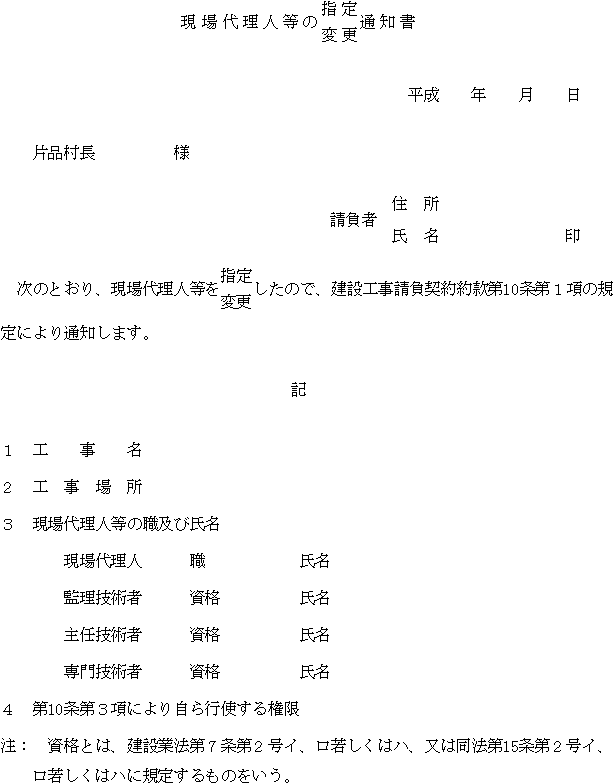
様式第30号(規格A4)(第29条関係)
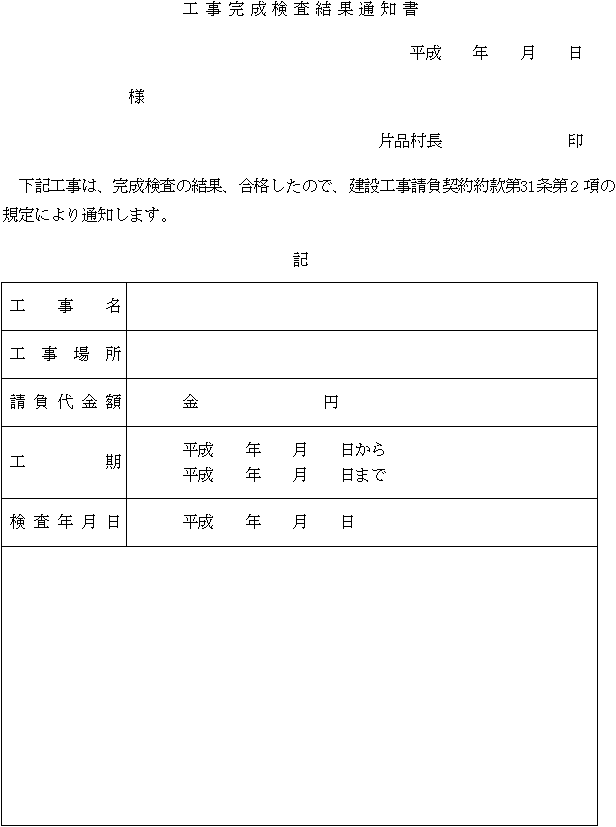
様式第31号(規格A4)(第29条関係)
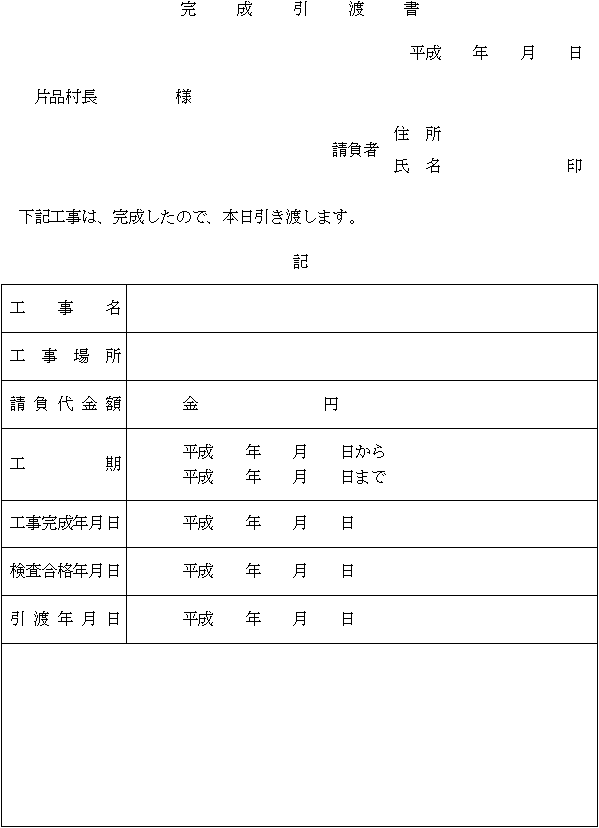
様式第32号(規格A4)(第29条関係)
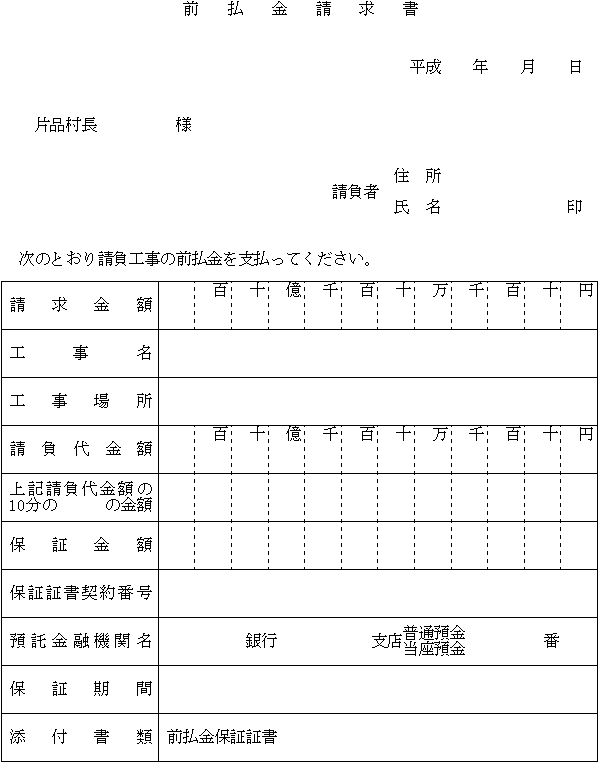
様式第33号(規格A4)(第29条関係)
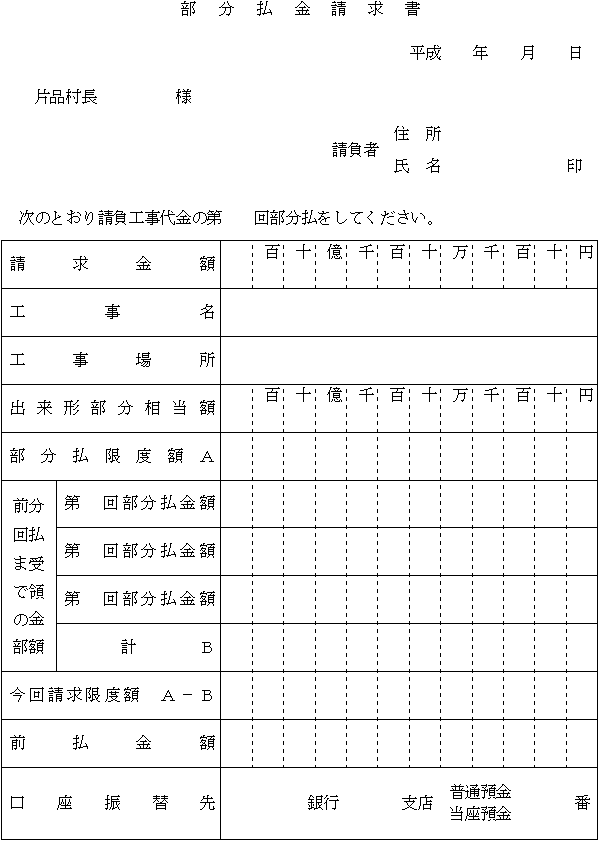
様式第34号(規格A4)(第29条関係)
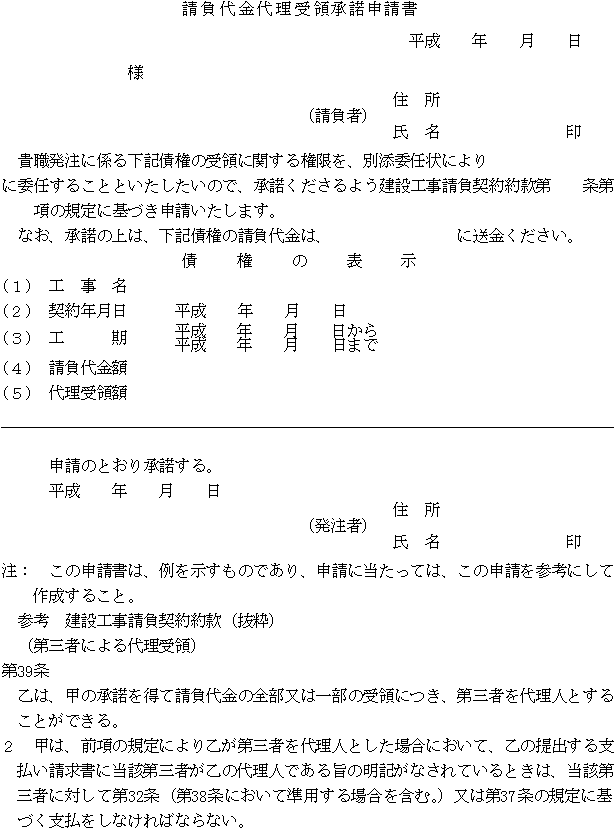
様式第35号(規格A4)(第29条関係)