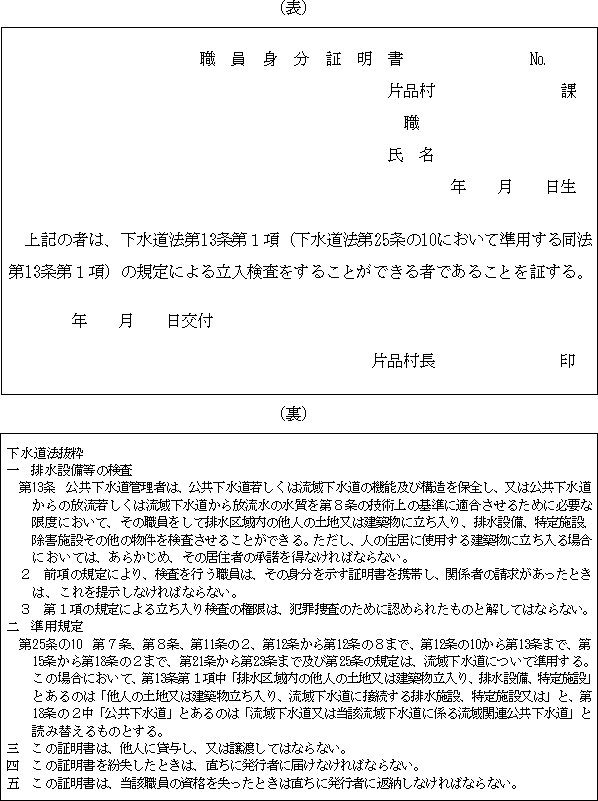○片品村下水道条例施行規則
平成12年10月10日規則第26号
片品村下水道条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、片品村下水道条例(平成12年条例第28号。以下「条例」という。)第26条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用月の始期及び終期)
第2条 条例第2条第10号に規定する使用月の始期及び終期は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道水量を算定するメーターの前回の点検日の翌日から次回の点検日までとする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、月の始めからその月の末日までとする。
(代理人の選定届)
(排水設備の設置延期)
2 村長は、前項の申請を承認したときは、申請者に排水設備設置延期許可書(別記様式第3号)を発行する。
(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)
第5条 条例第4条第2号に規定する排水設備の公共ます等への固着箇所及び工事の実施方法は次の基準によらなければならない。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共ますの接続孔と管低高とに、くい違いを生じないよう固着しなければならない。
(排水設備の構造基準)
第6条 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、排水設備の構造は次の各号によらなければならない。ただし、建物、土地の状況その他の特別の事情により村長の許可を受けたときは、この限りでない。
(1) 管渠の起点、屈曲点、合流点、内径若しくは管種を異にする接続箇所又は勾配が著しく変化する箇所及び直線部においては、内径の120倍に相当する間隔内に接続ますを設置すること。
(2) 配水管の土被りは、私道内で50センチメートル以上、宅地内で30センチメートル以上を標準とすること。
(3) 枝管の内径は、次のとおりとすること。
種類 | 内径 |
小便器、手洗器及び洗面器接続管 | 50ミリメートル以上 |
浴槽(家庭用)接続管及び炊事場接続管 | 75ミリメートル以上 |
大便器接続管 | 100ミリメートル以上 |
(4) 排水設備の接続ますの内のりは次のとおりとする。
種類 | 内径 | |
一種 | 配水管の内径又は排水渠の内のりが200ミリメートル以下で管底と地表面との差が1500ミリメートルまでのとき。 | 150ミリメートル以上 |
二種 | 配水管の内径又は排水渠の内のりが200ミリメートル以下で管底と地表面との差が1500ミリメートル以上のとき。 配水管の内径又は排水渠の内のりが200ミリメートルを超え300ミリメートル以下のとき。 | 300ミリメートル以上 |
三種 | 配水管の内径又は排水渠の内のりが300ミリメートルを超えるとき。 | 750ミリメートル以上 |
(附帯装置)
第7条 排水設備を設置するときは、次の各号の附帯設備を設けなければならない。
(1) ごみよけ装置
台所、浴室、洗濯場その他汚水中に固形物を排出する流し口には、有効間隔10ミリメートル以下の金属製のスクリーン(ストレーナー等)を取り付けなければならない。
(2) 防臭装置
手洗器、水洗便器等の器具との接続並びに流し場等の床流しのような場所には、検査清掃の容易な構造のトラップを設けなければならない。
(3) 油脂遮断装置
油脂類の販売店、自動車整備工場、料理店その他油脂類を多量に扱う業者の者は、この油脂類を多量に排出する場所の吐口には、油脂遮断装置を設けなければならない。
(4) 沈殿装置
病院、歯科医院及び洗車場等で土砂及びこれに準ずるものを多量に排出する場合には、深さ50センチメートル以上の砂溜りを設けなければならない。
(5) ポンプ施設
地下室その他自然流下が十分でない場所における排除の方法は、ポンプ施設によるものとし、汚水が逆流しないような構造にしなければならない。
(6) 管渠、ますその他の附帯設備は、不浸透な耐水構造とすること。
(排水設備等の共同設置)
第8条 土地建物等の状況により、単独で排水設備等を設置できないときは、村長の承認を得て使用者2人以上が共同して設置することができる。この場合に共同設置者は、その排水設備等に関する義務については連帯責任を負わなければならない。
2 前項の承認を受けようとするときは、設置者は代表を定め連署の上、共同排水設備等の代表者選定届(別記様式第4号)を村長に提出しなければならない。また、代表者を変更しようとするときは、共同排水設備等の代表者変更届(別記様式第4の2号)を村長に提出するものとする。
(水洗便所の設置基準)
第9条 水洗便所工事の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 便器は、使用に当たり完全に洗浄できる装置とすること。
(2) 洗浄用水槽は、洗浄のための相当の水圧が得られる高さに設置すること。
(3) 洗浄用水槽と大便器を連絡する管は、内径30ミリメートル以上とすること。
(4) 給水管には、必要に応じ凍結防止の装置をすること。
(排水設備等の計画の確認申請)
第10条 条例第5条の規定による村長の確認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、排水設備又は除害施設の新設等の場合は、排水設備新設(増設・改築)確認申請書(別記様式第5号)、除害施設新設(増設・改築)確認申請書(別記様式第5の2号)を村長に提出しなければならない。
2 前項の確認申請書には、次の各号に定める書類を添付するものとする。
(1) 申請地の位置及び目標を明示した見取り図
(2) 次の事項を表示した平面図(縮尺300分の1以上とする。ただし、申請地の状況により500分の1まで縮小することができる。)
ア 道路、境界及び公共下水道施設の位置
イ 排水設備又は除害施設の施工地内にある建物、水道、水洗便所、浴室、台所、洗濯場、井戸、手洗場その他汚水を排除する施設の位置
ウ 排水管渠、ます内径及び延長距離と位置
エ 排水設備の附帯装置の取付け場所
オ 除害施設とその附帯装置の位置
カ 他人の排水設備を使用するときはその位置
キ その他汚水排除の状況を明らかにするために必要な事項の表示
(3) 排水管渠の大きさ、勾配、接続ますと排水設備又は除害施設を固着させる公共下水道施設(汚水ます)の高さを表示した縦断図面(横縮尺500分の1以上、縦縮尺100分の1以上)
(4) 排水管渠、接続ます及び附帯装置の構造、能力、形状、寸法等を表示した詳細図
(計画確認の通知)
第11条 村長は、前条の申請により計画を確認したときは、申請者に対し、排水設備等計画確認書(別記様式第6号)を交付する。除害施設についても、村長は計画を確認したときは、除害施設計画確認書(別記様式第6の2号)を交付するものとする。
2 村長は、前項の交付日より6か月以内に申請者がその工事に着手しないときは、これを取り消すことができる。
(排水設備等の軽微な変更)
(1) 屋内の排水管に固着する洗面器、水洗便所の水槽及び便器の大きさ、構造又は位置の変更
(2) ごみよけ、防臭装置等の付帯装置で、確認を受けたときの能力を低下させない変更
(3) その他特に軽微な変更及び工事で村長が認めたもの
(排水設備等の工事の実施)
第13条 排水設備等の工事を行う場合、埋設又は被覆等のため工事完成後に検査のできない部分については、工事の実施中に申し出て村長の指示を受けなければならない。
(排水設備等の工事の完成届)
(排水設備等の工事検査)
第15条 村長は、前条の届出があった場合、速やかに検査を行い合格と認めたときは、届出者に対し、排水設備等検査済証(別記様式第8号)を交付する。
2 前項の検査には、工事を施工した下水道排水設備工事責任技術者を立ち合せるものとする。
(公共下水道使用開始等の届出)
2 前項の届出をした使用者で、水道水使用以外の汚水を水道水汚水に変更しようとするときは、公共下水道使用変更届(別記様式第9の2号)を村長に提出しなければならない。水道水汚水を水道水汚水以外の汚水に変更しようとするときも同様とする。
(排水設備等義務者変更届)
第17条 条例第14条第2項の規定による代理人又は使用者の変更の届出をしようとする者は、排水設備等義務者(使用者)変更届(別記様式第10号)を変更の生じた日から7日以内に、村長に提出しなければならない。
(除害施設)
第18条 条例第8条に規定する除害施設は、その除害施設の新設等を必要とされた原因に適合する処理方法によらなければならない。
(除害施設管理責任者を置くべき工場又は事業場)
第19条 水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1第2号から第24号まで、第26号から第28号まで、第30号から第42号まで、第44号から第59号まで及び第61号から第66号に掲げる施設(同表第62号に掲げる施設で鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第2条第2項の鉱山に設置されるものを除く。)のいずれかが設置されている工場で排出水量(1日当たりの平均的な排出水の量をいう。)が500立方メートル以上のもの及び特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和46年政令第264号)別表第1に規定する施設が設置されている工場
(除害施設管理責任者の選任基準)
第20条 条例第11条の規定に基づく除害施設管理責任者の選任は、当該工場又は事業場における除害施設の維持管理に関し、専門的知識及び経験を有すると認められる者のうちから行わなければならない。
(除害施設管理責任者の届出)
2 前項の届出をした者は、その届出に係る除害施設管理責任者を変更したときは、その日から30日以内に除害施設管理責任者変更届(別記様式第11の2号)を村長に提出しなければならない。
(使用料の徴収)
第22条 条例第15条に規定する使用料の徴収は、下水道料金納入通知書により徴収するものとする。
2 集金による場合の領収書は、出納員の領収印があるものに限り有効とする。
3 使用者が使用料を口座振替による納入をしようとするときは、預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書(別記様式第12号)を該当金融機関を経て主管課長に提出しなければならない。
4 前項の徴収方法をとるときは、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関の自動振替により徴収するものとする。
5 使用料徴収後、算定に過不足があった場合には、翌月分使用料徴収の際に清算する。
(汚水排除量の認定)
第23条 条例第16条第2項第2号の規定による水道水以外の水を使用した場合の使用期ごとの汚水の排除量の認定は、次の各号によるものとする。
(1) 井戸水、湧水等を家事のみに使用した場合の排除汚水量は、下水道専用メーターを設置し、第2条第1項に定めるところにより、排水量とみなす。
(2) 前項の井戸及び湧水が水道と併用されている場合の、排除汚水量は、水道水による基本水量に、前号の排水量を加えた量をもって排水量とみなす。
(3) 家事以外に使用された井戸水、湧水等による排除汚水量は、使用者の世帯人員、業態、揚水設備、水の使用状況等の態様を考慮して村長が算定する。
(4) 土木建築等に関する工事用の汚水については、その現場の水の使用状況を考慮して排水量を村長が認定する。
2 使用者が前項各号のいずれにも該当しない場合の汚水は、前項各号の規定を勘案して村長が認定する。
3 前第1項及び第2項の汚水排出量の認定の基準となる事実に異動を生じたときは、その事実が生じた日から7日以内に汚水排除量認定基準異動届(別記様式第13号)を村長に提出しなければならない。
(汚水排除量の申告)
第24条 条例第16条第2項第3号の規定による汚水排除量の申告をしようとする者は、氷雪製造業等汚水排除量申告書(別記様式第14号)を村長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申告を必要とする業種は、氷雪製造業、清涼飲料水製造業、酒造業、水菓子製造業及び旅館業とする。
3 村長は、前第1項の規定による申告があった場合は、その量を決定し、使用者に対し氷雪製造業等汚水排除量決定通知書(別記様式第14の2号)により通知するものとする。
(世帯人口の確認)
第25条 世帯人口の員数は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票により、毎月1日現在をもってその月の世帯人員とする。
(督促)
(使用料等の減免)
2 使用料の額を減免する場合の軽減の額は、その都度村長が定め下水道使用料減額(免除)決定通知書(別記様式第16の2号)により通知する。
3 使用料の軽減又は免除を受けた者は、その軽減又は免除の事由が消滅したときは、遅滞なく村長に届出なければならない。
(行為及び占用の許可申請)
第28条 条例第19条第1項の規定により法第24条第1項の許可を受けようとする者又は条例第21条第1項の規定により公共下水道の敷地若しくは施設を占用しようとする者は、工事(行為、占用)許可申請書(別記様式第17号)を村長に提出しなければならない。
(行為及び占用の許可)
第29条 村長は前条の申請に基づき、行為の許可又は占用の許可をしたときは、工事(行為・占用)許可証(別記様式第18号)を交付する。
(原状回復の届出)
(職員の身分証明)
第31条 法第13条第2項及び第32条第5項の規定による職員である身分を示す証明は、職員身分証明書(別記様式第20号)とする。
2 職員は法令又は条例規則の規定により検査、調査等を行う場合においては、前項の身分証明書を携帯しなければならない。
(その他必要な事項)
第32条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第32号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月18日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月11日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
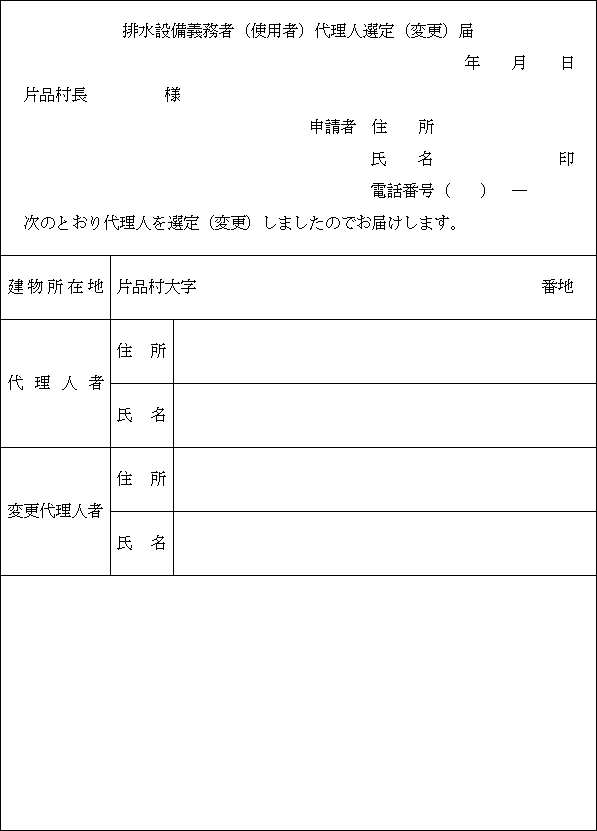
様式第2号(第4条関係)
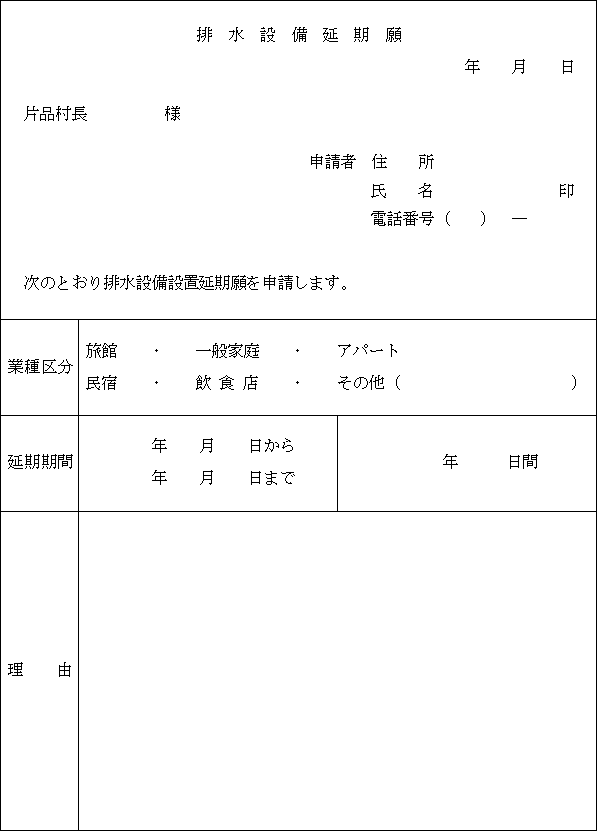
様式第3号(第4条関係)
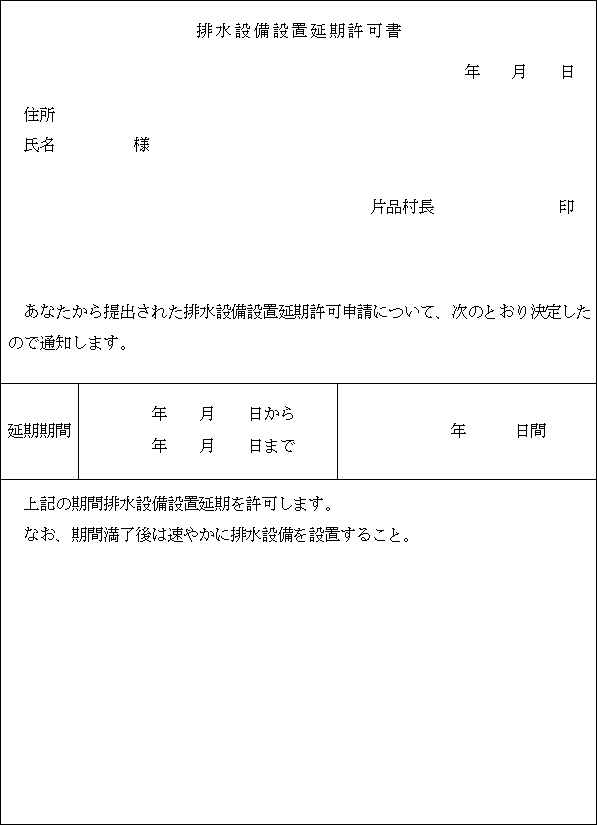
様式第4号(第8条関係)
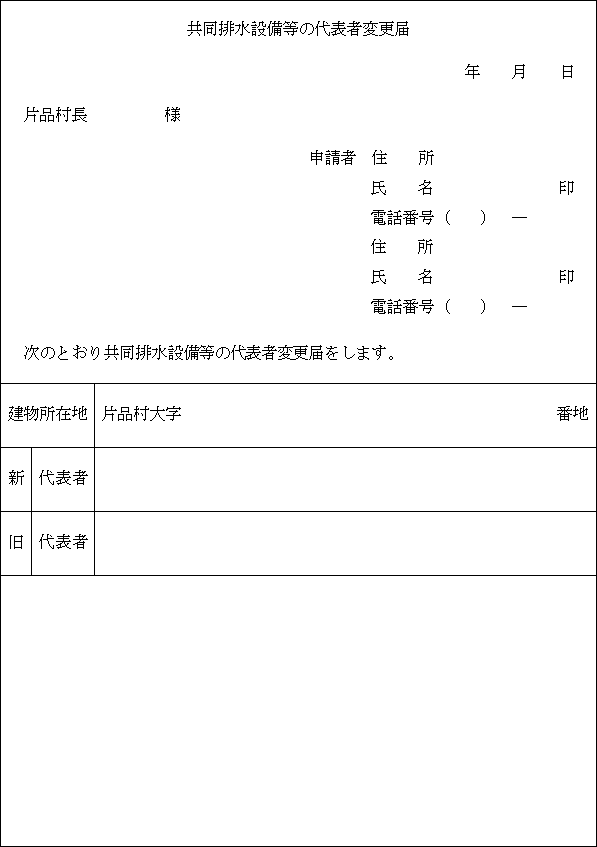
様式第4の2号(第8条関係)
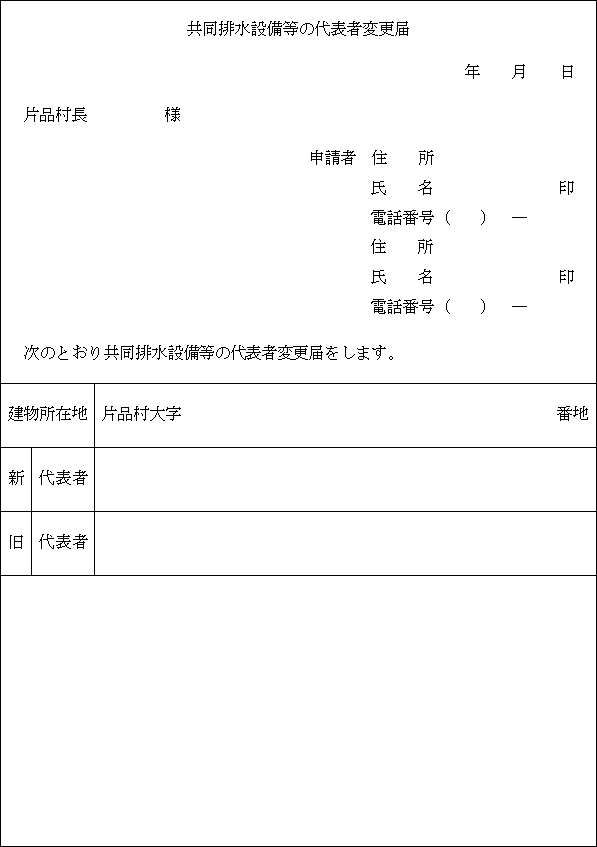
様式第5号(第10条関係)
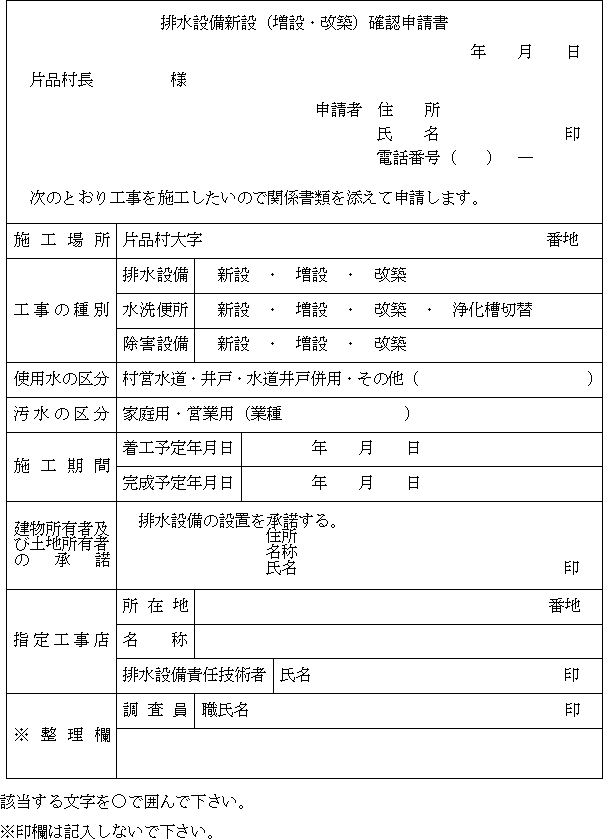
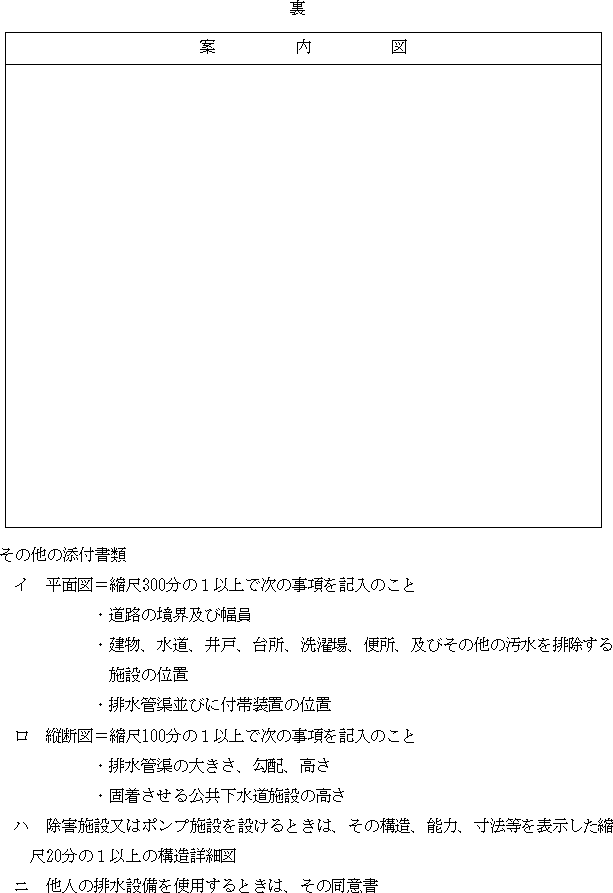
様式第5の2号(第10条関係)
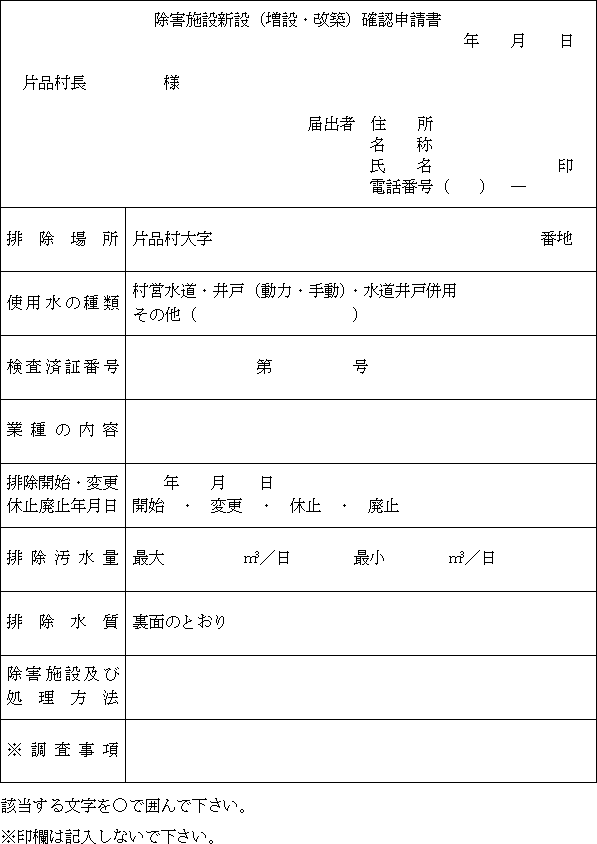
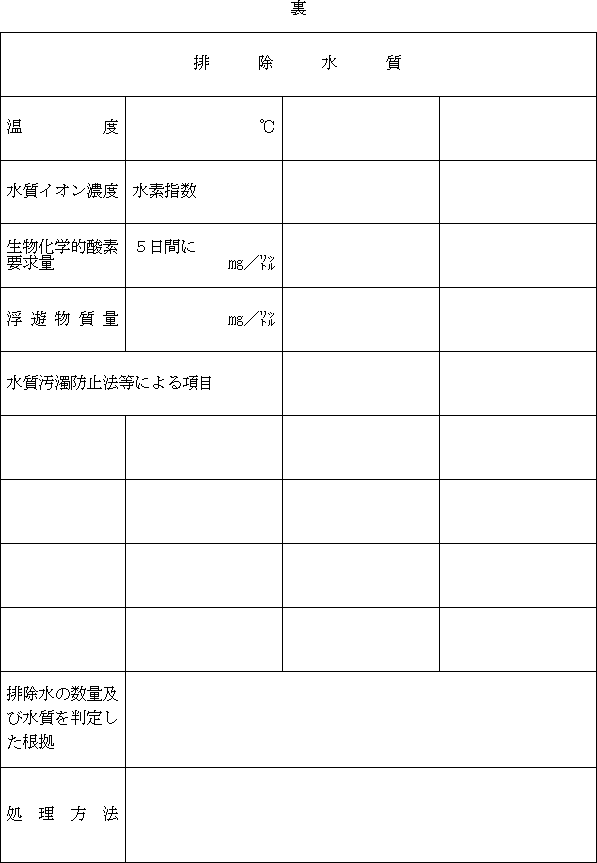
様式第6号(第11条関係)
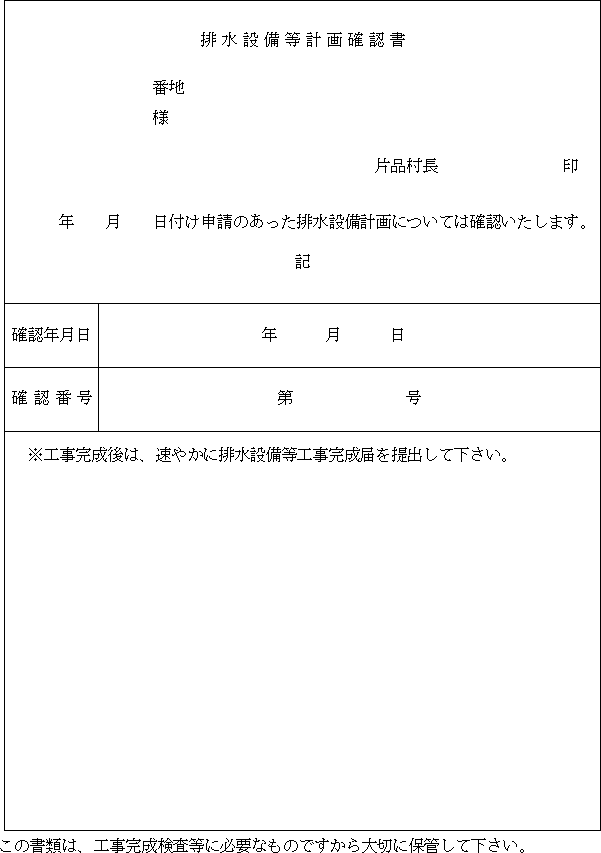
様式第6の2号(第11条関係)
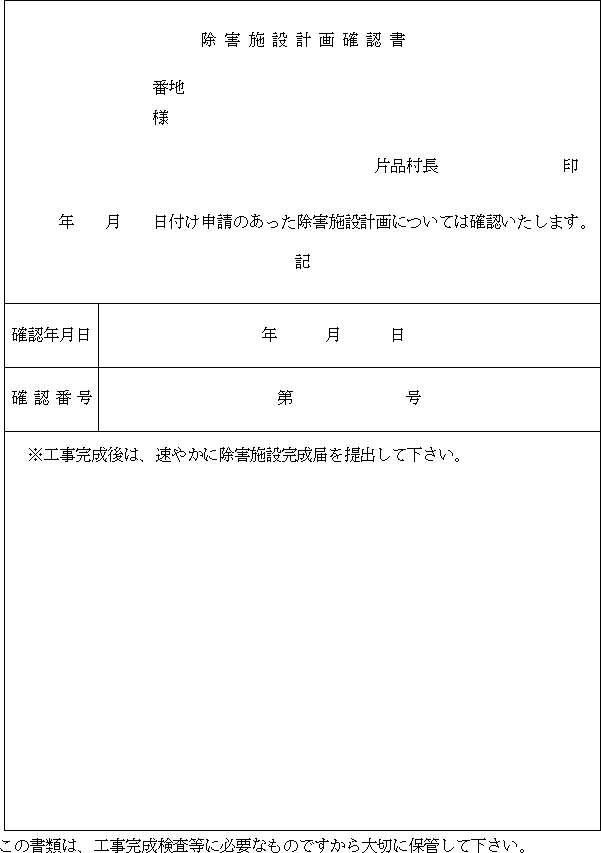
様式第7号(第14条関係)
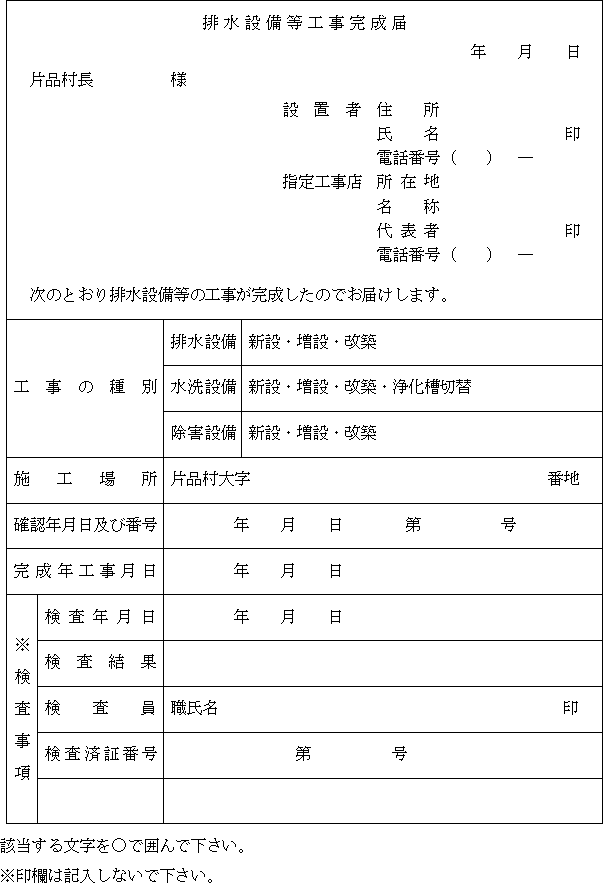
様式第7の2号(第14条関係)
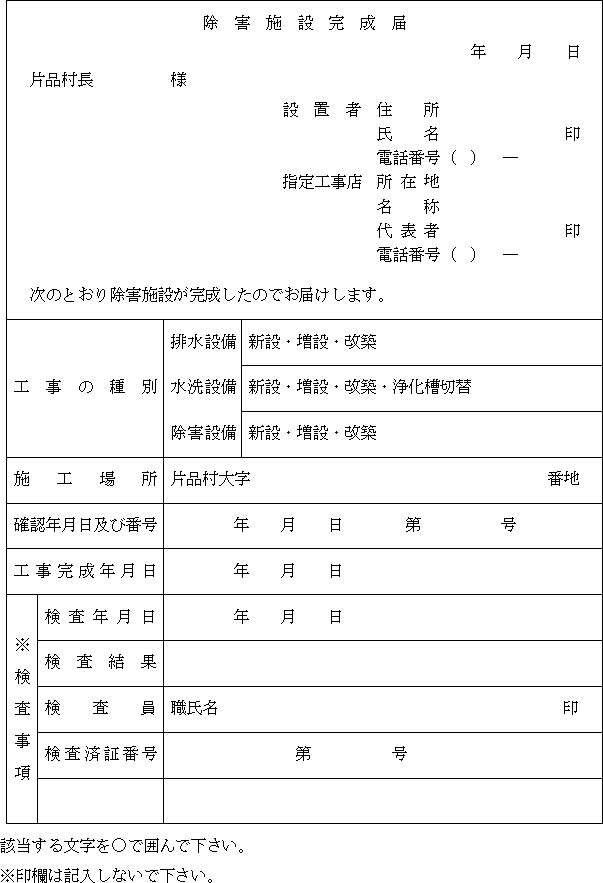
様式第8号(第15条関係)
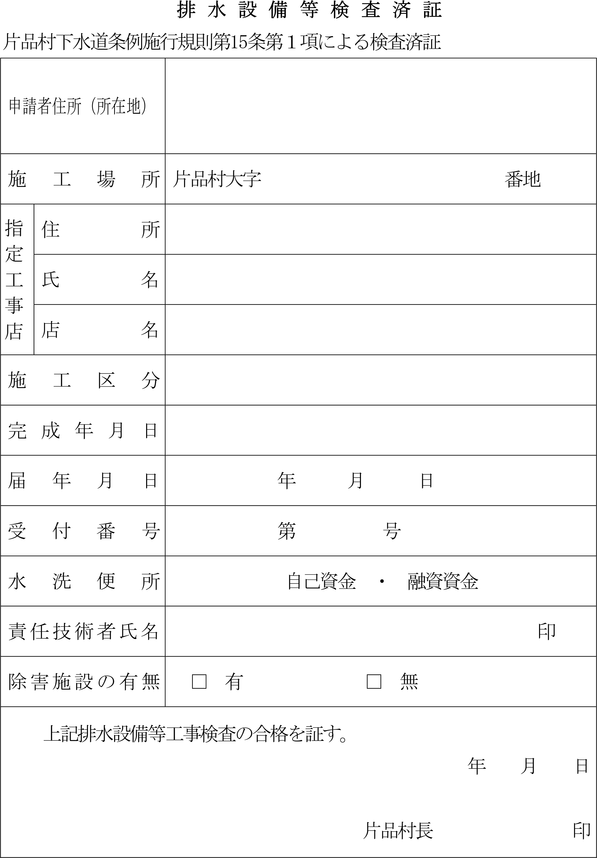
様式第9号(第16条関係)
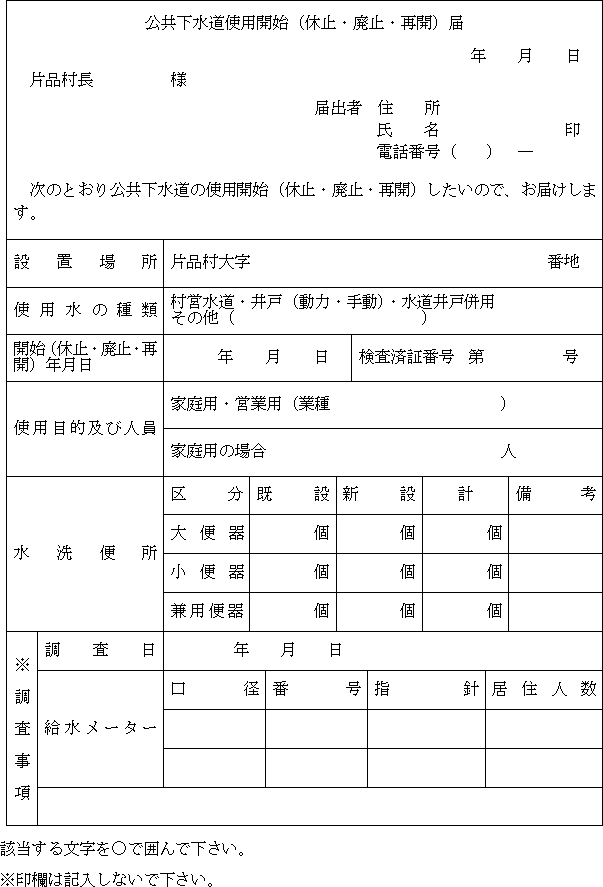
様式第9の2号(第16条関係)
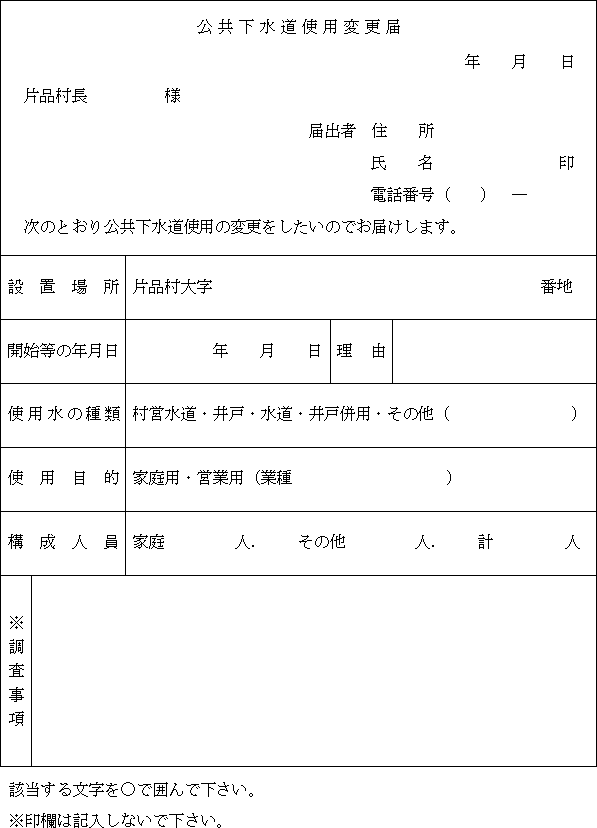
様式第10号(第17条関係)
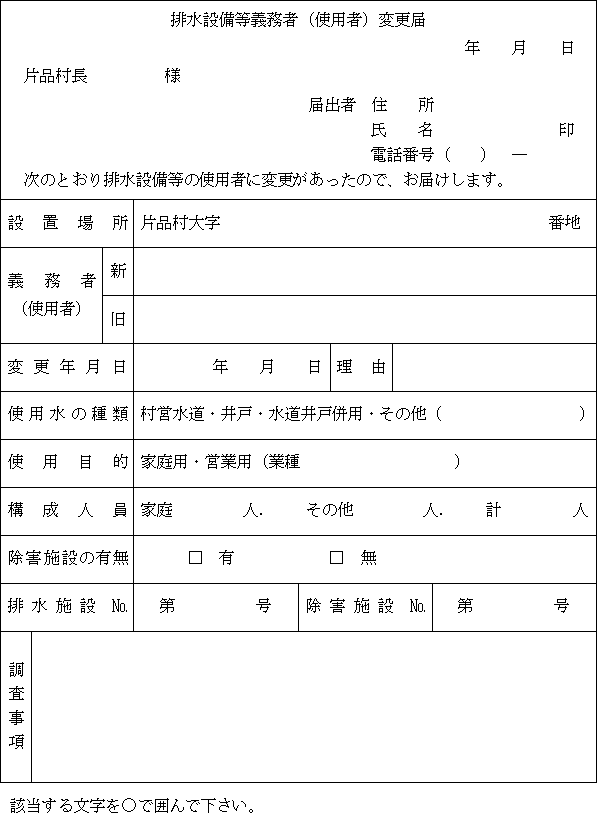
様式第11号(第21条関係)
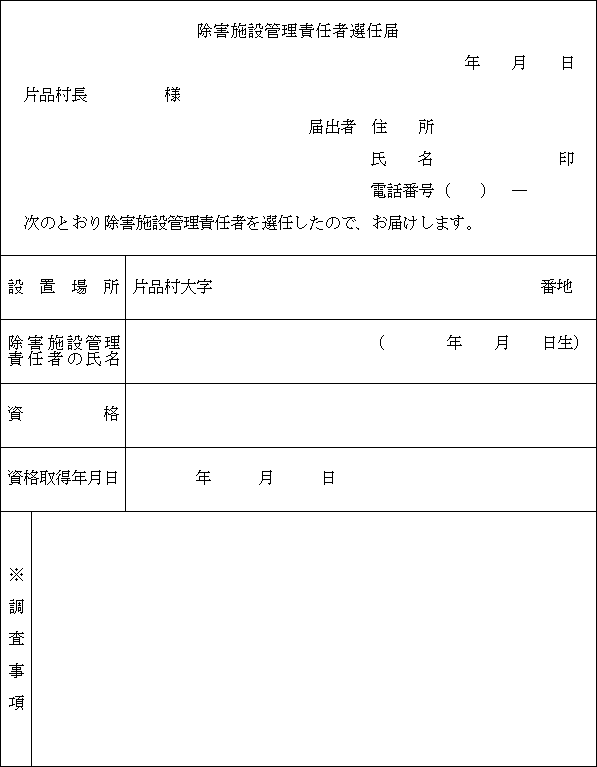
様式第11の2号(第21条関係)
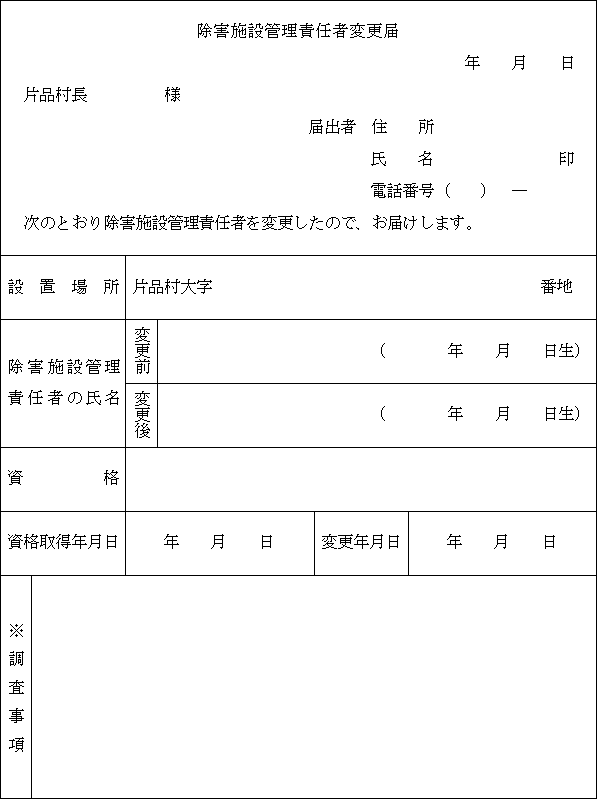
様式第12号(第22条関係)
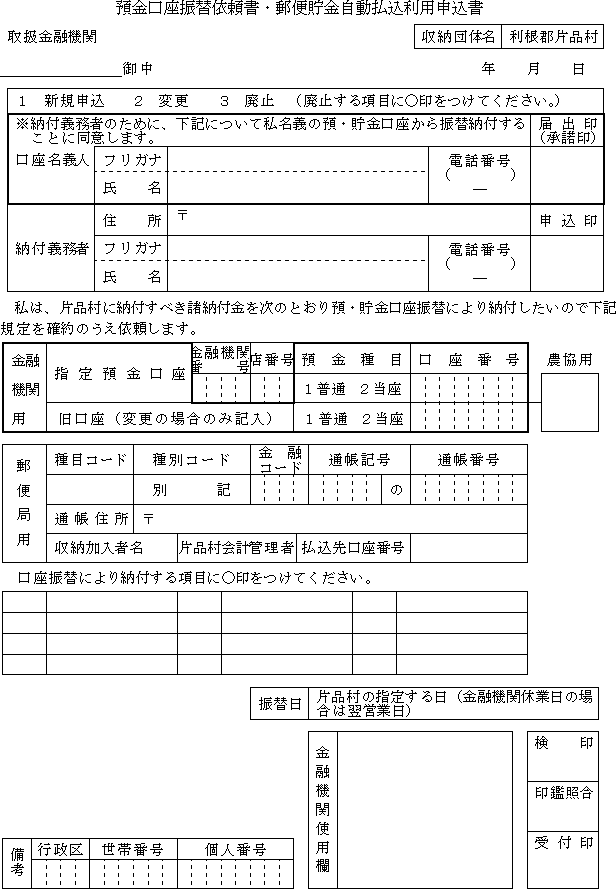
様式第13号(第23条関係)
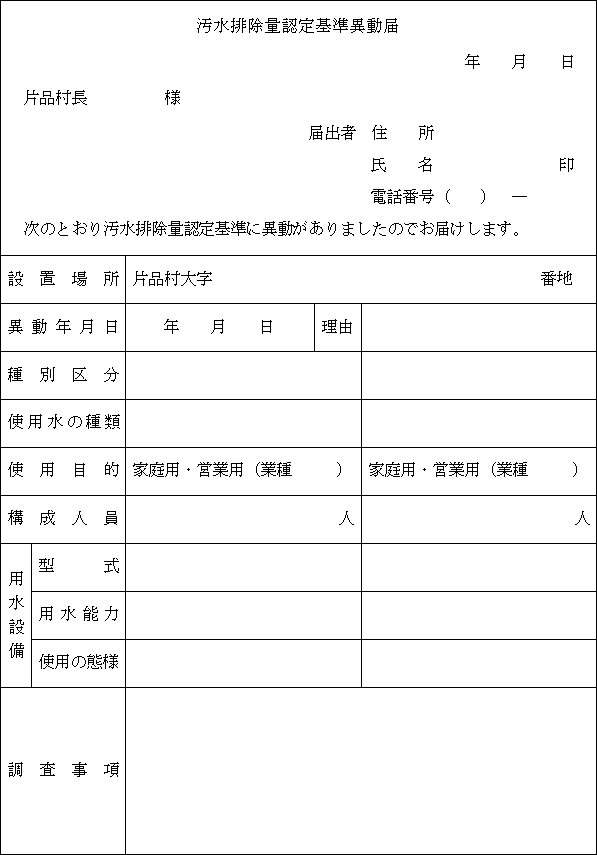
様式第14号(第24条関係)
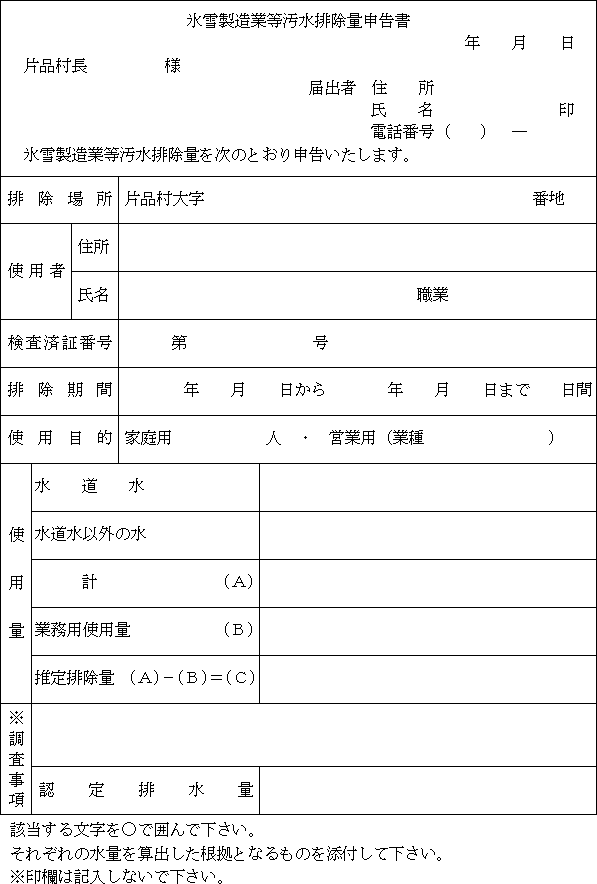
様式第14の2号(第24条関係)
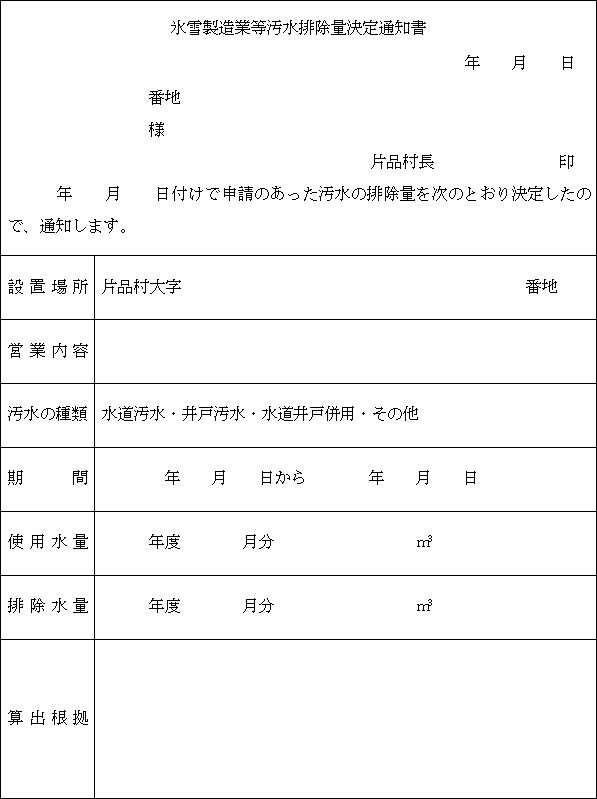
様式第15号(第26条関係)
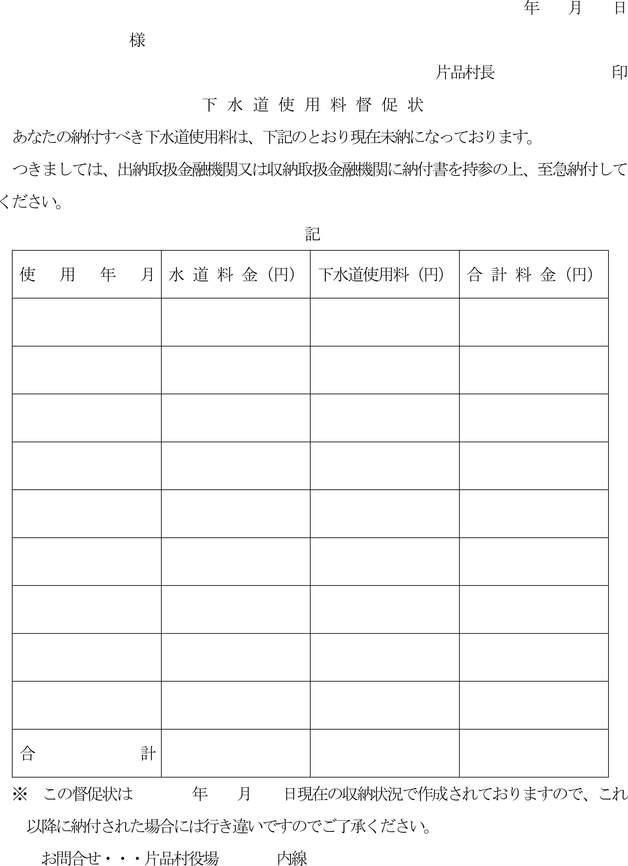
様式第16号(第27条関係)
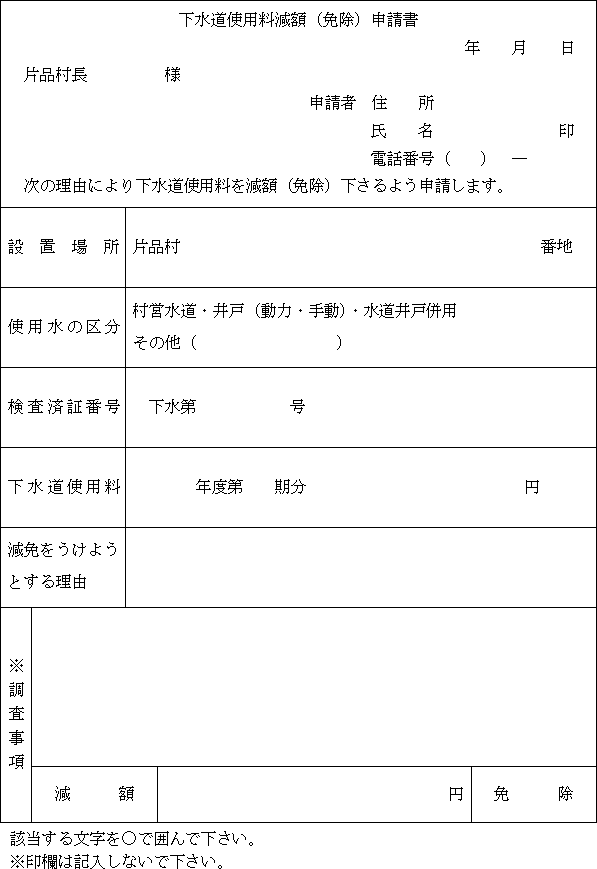
様式第16の2号(第27条関係)
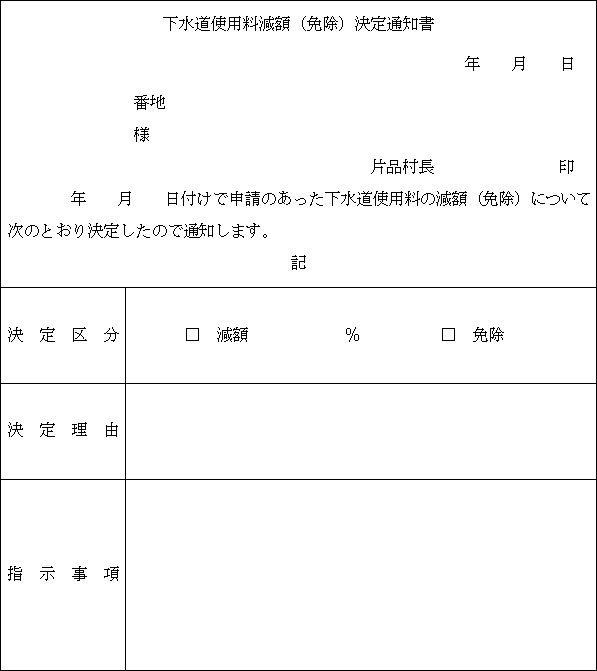
様式第17号(第28条関係)
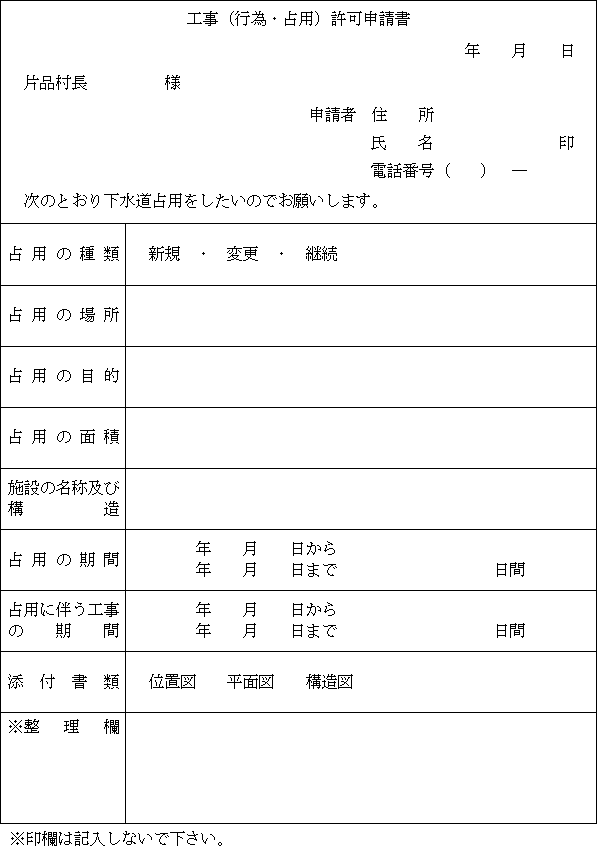
様式第18号(第29条関係)
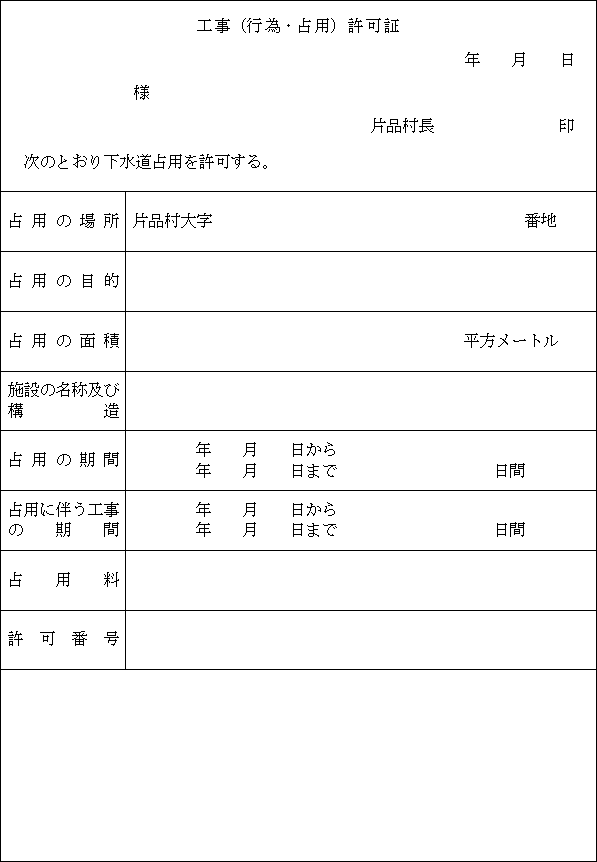
様式第19号(第30条関係)
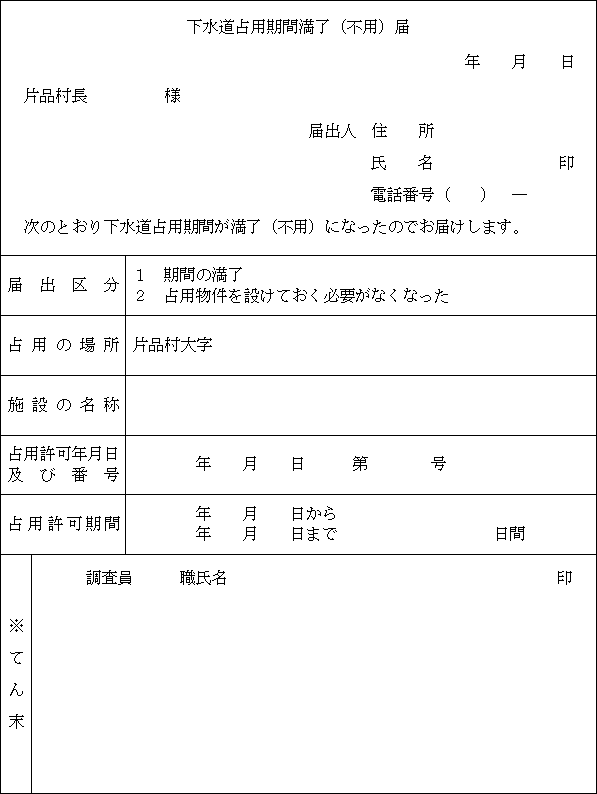
様式第20号(第31条関係)