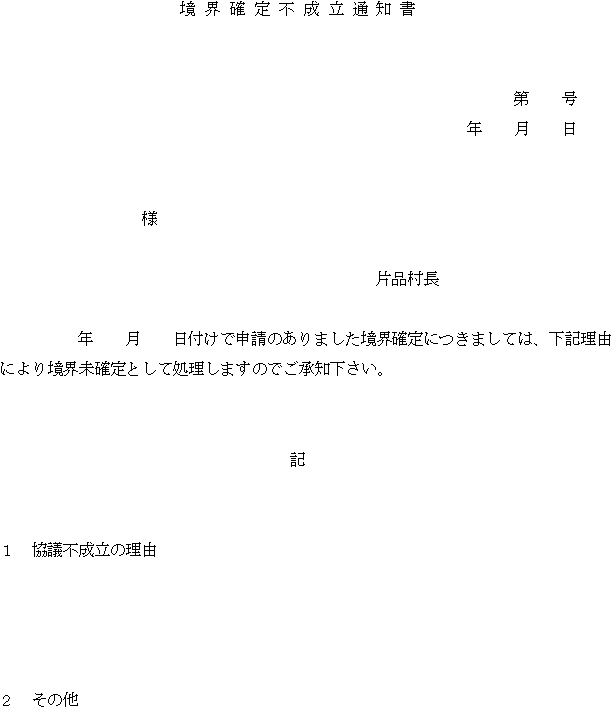○片品村公共物使用等に関する規則
平成16年3月25日規則第2号
片品村公共物使用等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、片品村公共物使用等に関する条例(昭和57年条例第21号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(工作物の設置及び流水・水面の占用等の許可申請)
第2条 条例第4条第1号、第2号及び第3号の規定に基づき、公共物に工作物を新築し、改築し、若しくは除去し、又は流水・水面を占用し、若しくは使用し、又は流水を停滞し、若しくは引用しようとする者は、公共物使用工作物設置・流水引用許可申請書(別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 公共物の改良工事を行う場合は、公共物改良工事施行許可申請書(別記様式第2号)を村長に提出しなければならない。
(工作物の設置及び流水・水面の占用等の許可)
第3条 村長は、前条第1項に規定する占用許可の申請を受け、これを許可すべきものと認めたときは、公共物使用許可書(別記様式第3号)を申請者に交付しなければならない。
2 村長は、前条第2項に規定する改良工事の許可申請を受け、これを許可すべきものと認めたときは、公共物改良工事施行許可書(別記様式第4号)を申請者に交付しなければならない。
(公共物の敷地の占用許可申請)
(公共物の敷地の占用許可)
第5条 村長は、前条に規定する占用許可の申請を受け、これを許可すべきものと認めたときは公共物使用許可書(別記様式第3号)を申請者に交付しなければならない。
(生産物採取の許可申請)
(生産物採取の許可)
第7条 村長は、前条に規定する採取許可の申請を受け、これを許可すべきものと認めたときは公共物の生産物採取許可書(別記様式第7号)を申請者に交付しなければならない。
(排出水の流入許可申請)
(排出水の流入許可)
第9条 村長は、前条に規定する流入許可の申請を受けた場合は、普通河川に工場等排出水流入施設調査票(別記様式第9号)により調査し、これを許可すべきものと認めたときは、工場等排出水流入許可書(別記様式第10号)を申請者に交付しなければならない。
(住所、氏名等の変更届)
(使用の廃止)
第11条 条例第4条の規定に基づき、村長の許可を受けた者が許可期間の満了前に許可を受けた行為を廃止しようとするときは、あらかじめ村長に届け出なければならない。
(許可期限更新の申請)
第12条 条例第6条の規定による許可の期間は、許可を受けた者の申請により更新することができる。
2 前項により更新しようとする者は、期間満了15日前までに、公共物継続許可申請書(別記様式第12号)を村長に提出しなければならない。
(許可期限更新の許可)
第13条 村長は、前条第2項に規定する継続許可申請を受け、これを許可すべきものと認めたときは、第3条、第5条及び第9条の規定を準用する。
(権利義務移転の申請)
(権利義務移転の許可)
第15条 村長は、前条に規定する権利義務移転の許可申請を受け、これを許可すべきものと認めたときは、公共物権利義務移転許可書(別記様式第14号)を申請者に交付しなければならない。
(許可事項変更の申請)
(許可事項変更の許可)
第17条 村長は、前条に規定する許可事項変更の許可申請を受け、これを許可すべきものと認めたときは、公共物使用許可事項変更許可書(別記様式第16号)を申請者に交付しなければならない。
(使用料の徴収方法)
第18条 使用料の徴収については、次の各号による。
(1) 使用期間が1年未満のものは、許可の際全額を徴収する。
(2) 使用期間が1年以上のものは、初年度は前号の方法により徴収し、次年度からは会計年度の初めにおいて、それぞれの年度に属する料金を徴収する。
(使用料の減免手続)
(境界確定の申請)
第20条 公共物との境界確定並び、これに伴う地籍訂正及び地図訂正に対する承諾書交付申請をしようとする者は、公共物境界確定申請書(別記様式第18号)に次の書類を添付し村長に提出しなければならない。
(1) 申請者が公共物に隣接する土地について権限を有することを証する書面(登記簿謄本又は売買契約書の写し等)
(2) 申請者以外の、隣接土地所有者一覧表(別記様式第19号)
(3) 境界確定のうえ、地籍訂正及び地図訂正に対する承諾書の交付を必要とする場合は対象地の実測平面図、求積図、地籍訂正及び地図訂正する土地に隣接する所有者の、公共物隣接境界承諾書(別記様式第20号)
(4) 案内図
(5) 公図写
(境界確定申請の調査)
第21条 村長は、前条に規定する境界確定申請を受け、境界立会に先立ちその土地の沿革、地域の慣行等を参考資料として収集調査し、境界確定は申請者及び隣接土地所有者等が立会いのうえ、原則として公図を基準に付近の地形、建物等を参考にして公正妥当な境界確定をしなければならない。
(境界確定の協議)
第22条 境界確定の協議が成立したときは、関係者立会いのうえ申請者の準備する境界杭を現地の必要箇所に設置するものとし、境界立会いを行った職員は立会い結果を、村長に復命(別記様式第21号)しなければならない。
(境界確定書の交付)
第23条 村長は、境界確定の協議が成立した場合、申請者に次の書類を添付させ境界確定書(別記様式第22号)の交付をすることができる。
(1) 境界確定図(座標数値の記載されているもの)
(2) 実測平面図(境界標柱等の位置を表示し、境界を朱線で明示されたもの)
2 村長は、境界確定書が提出された場合内容を審査のうえ2部押印し1部を申請者に交付する。
3 村長は、境界確定書提出時に申請者より、地籍訂正及び地図訂正に対する承諾書の請求があった場合、併せて地籍訂正承諾書(別記様式第23号)を交付するものとする。
4 村長は、境界確定の協議が成立しなかった場合、その理由を付して境界確定不成立通知書(別記様式第24号)を申請者に通知するものとする。
(申請書の提出部数)
第24条 この施行規則に関する、村長に提出する申請書等の部数は2部とする。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
様式第1号
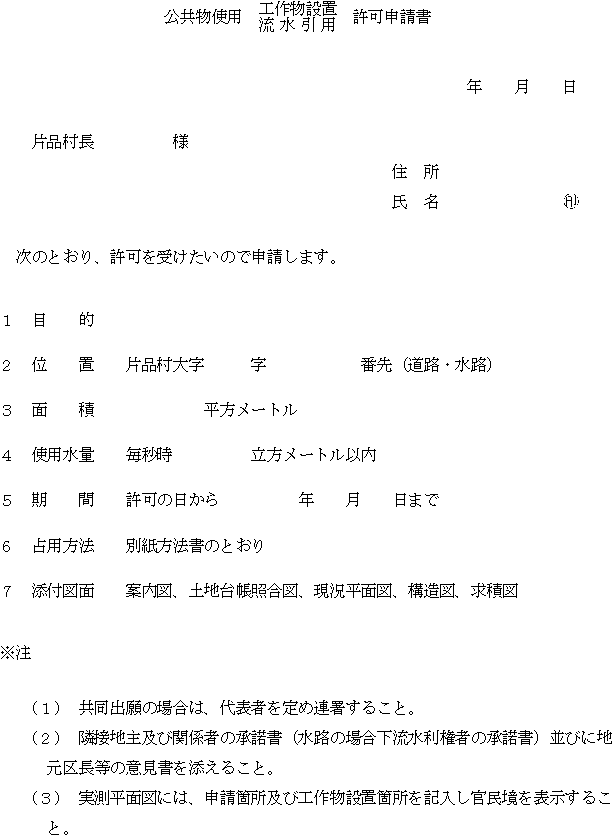
様式第2号
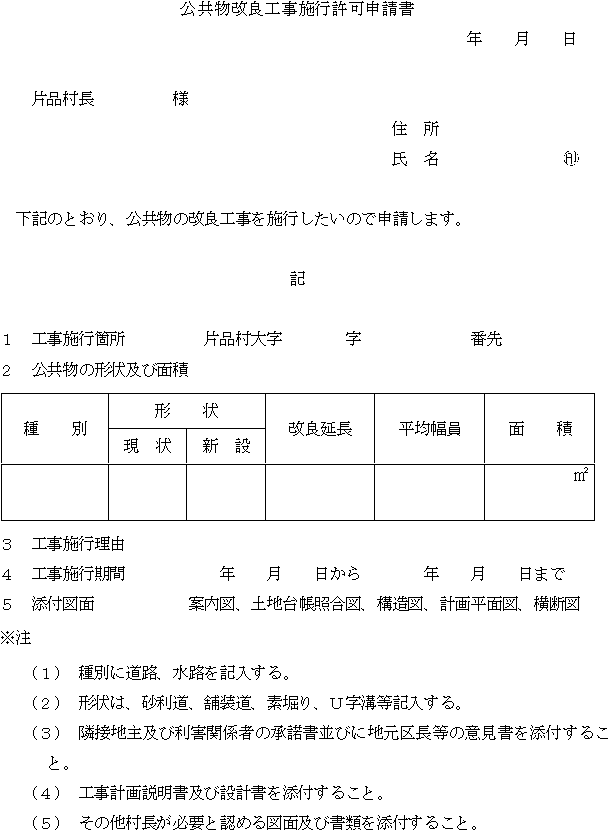
様式第3号
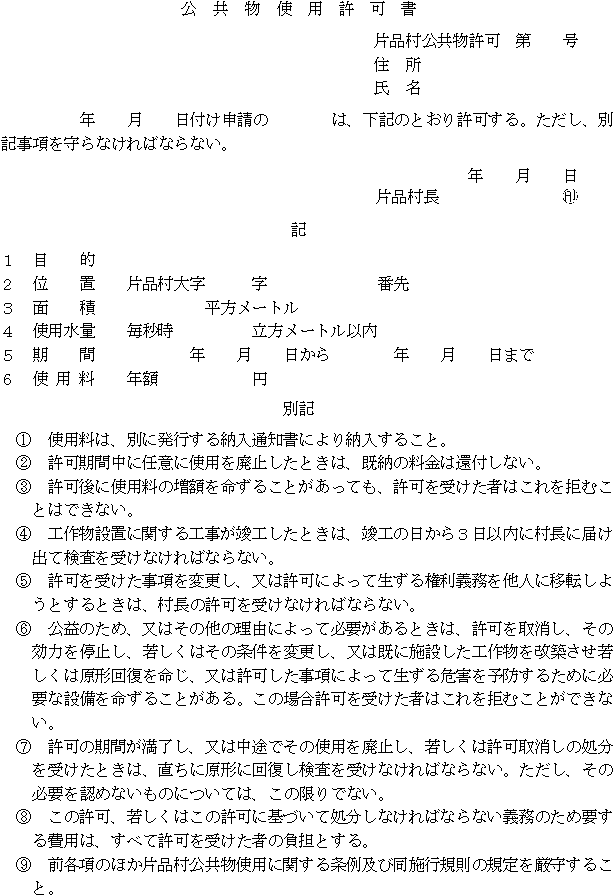
様式第4号

様式第5号
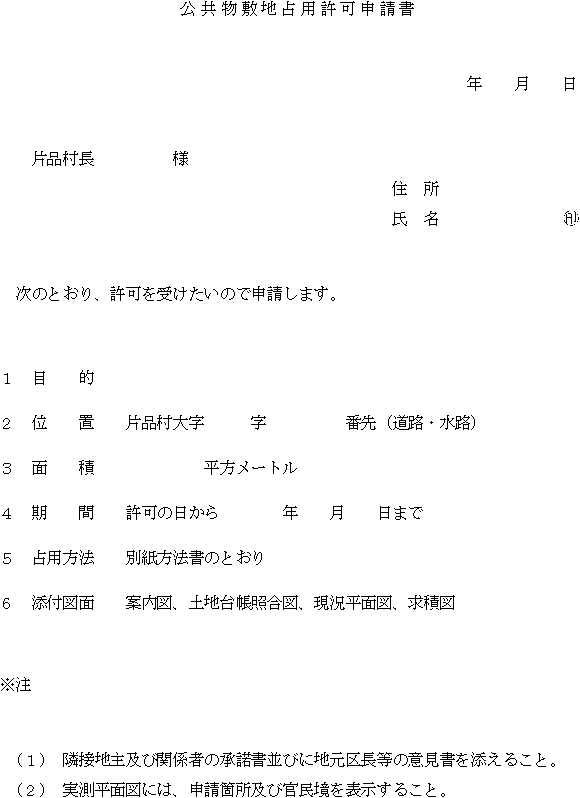
様式第6号
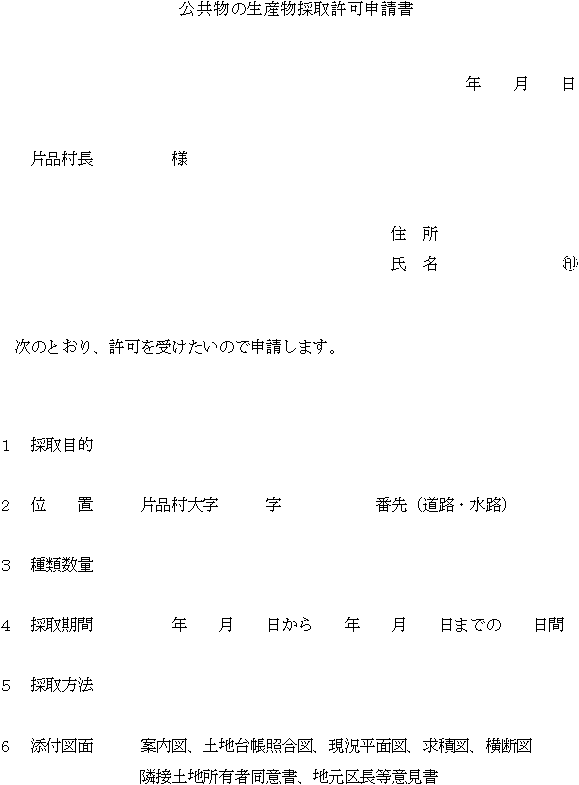
様式第7号
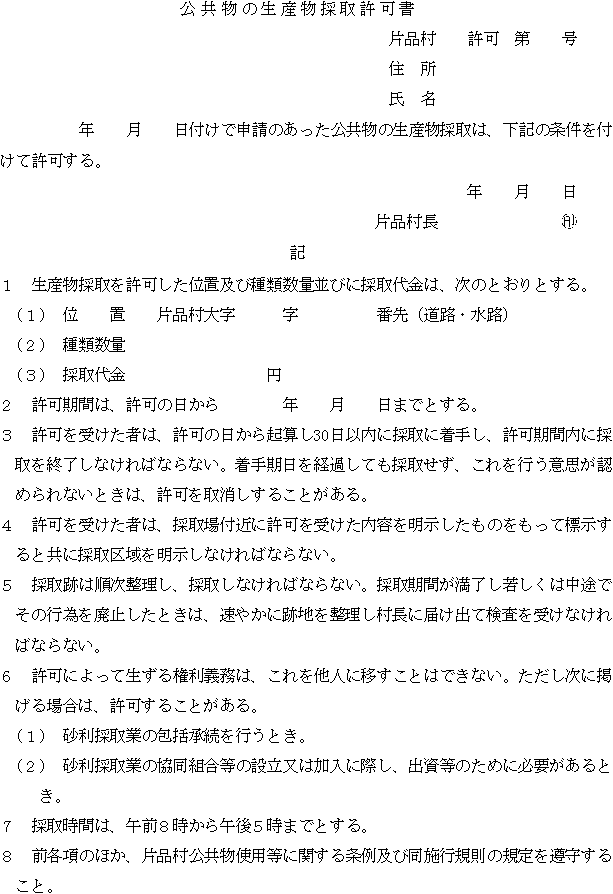
様式第8号
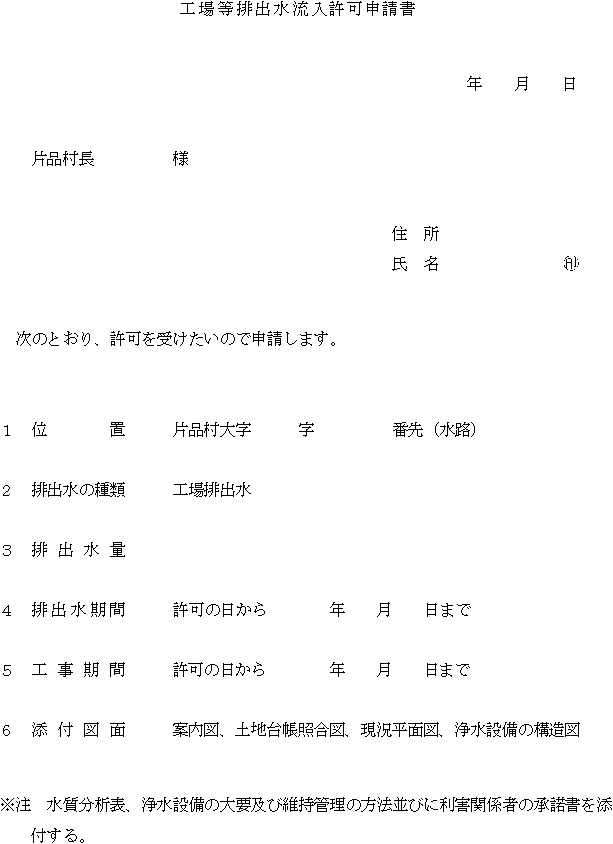
様式第9号
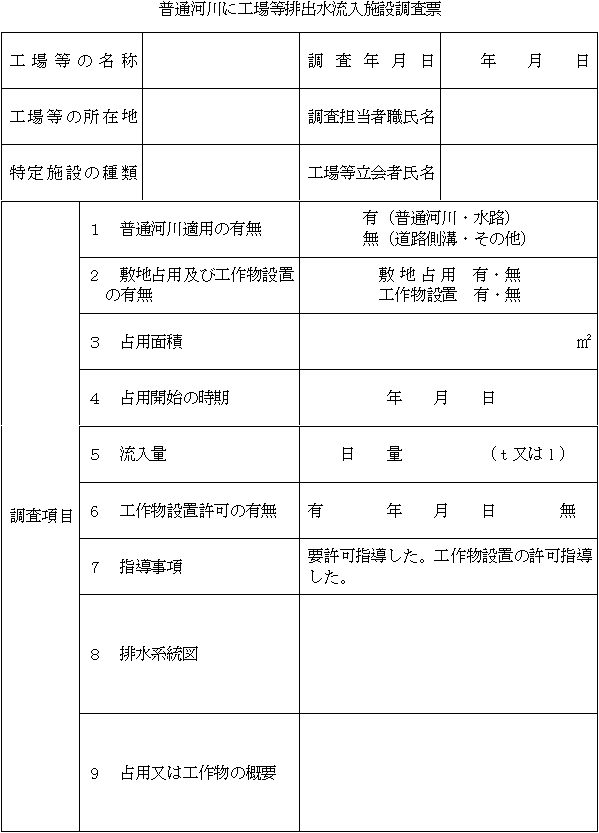
様式第10号
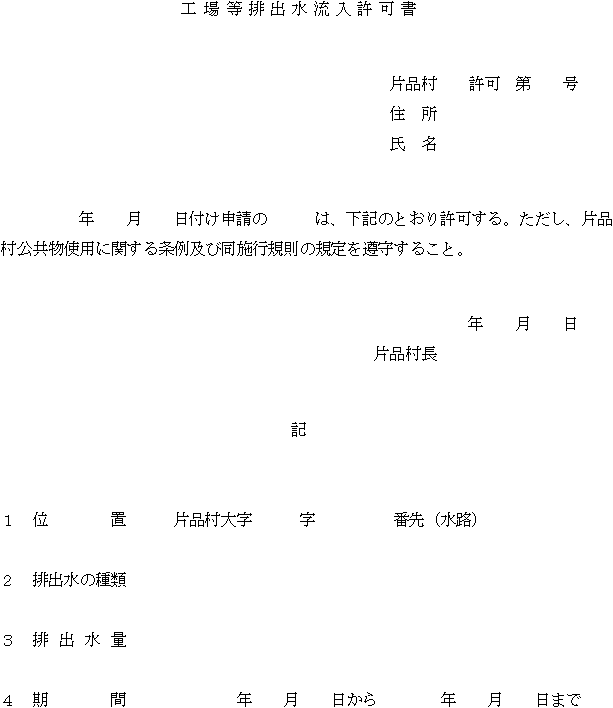
様式第11号
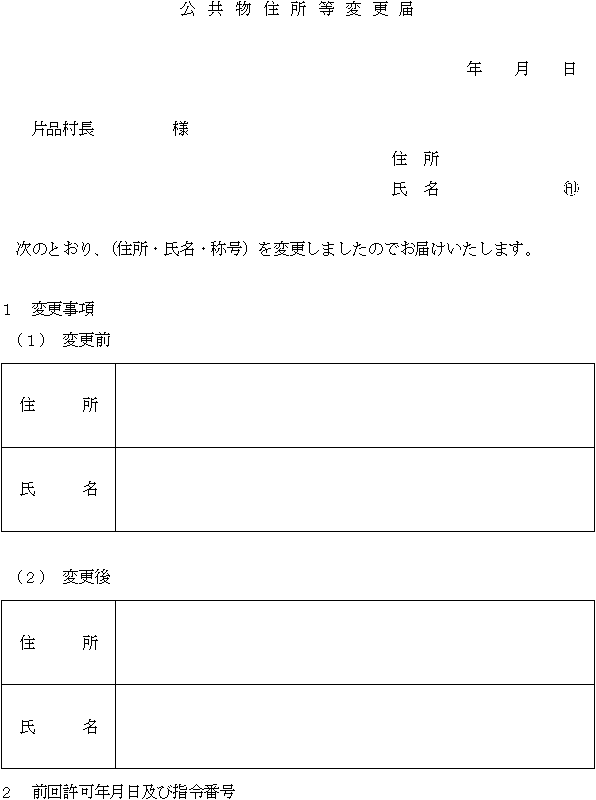
様式第12号
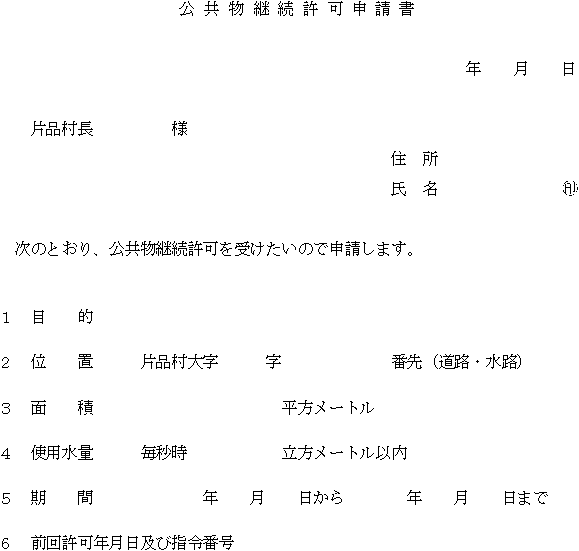
様式第13号
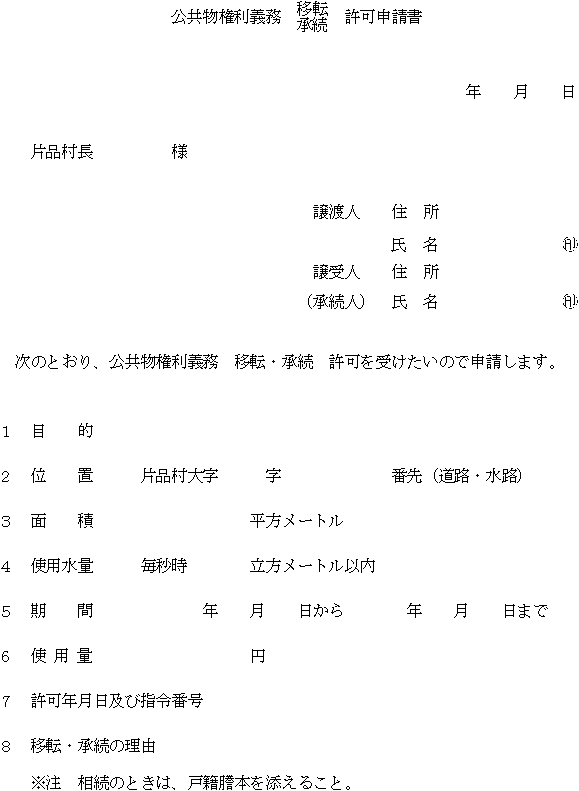
様式第14号
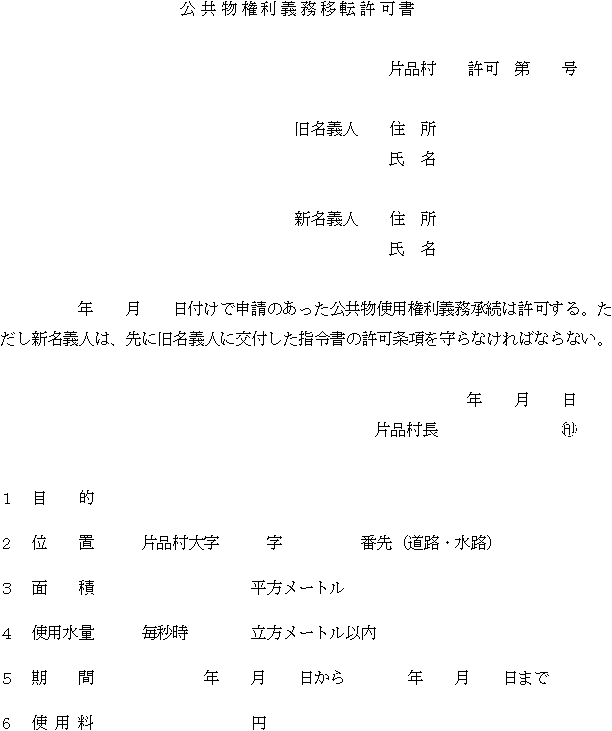
様式第15号
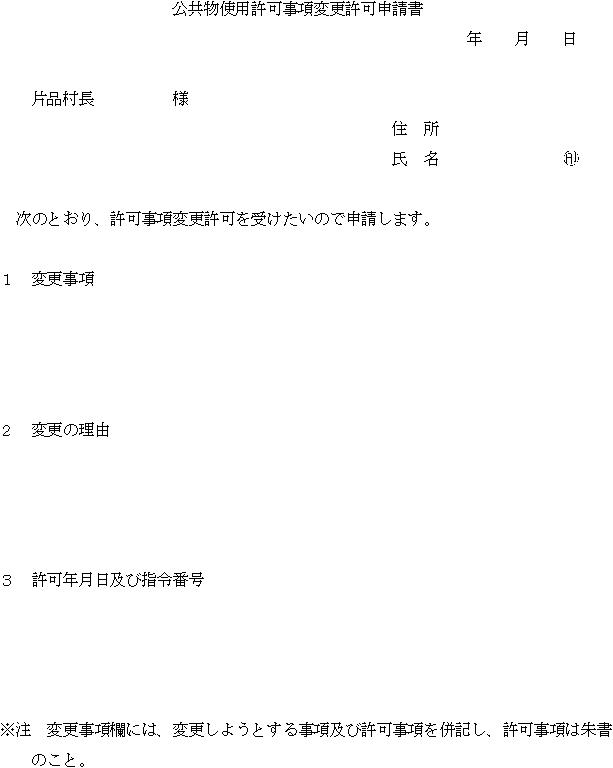
様式第16号
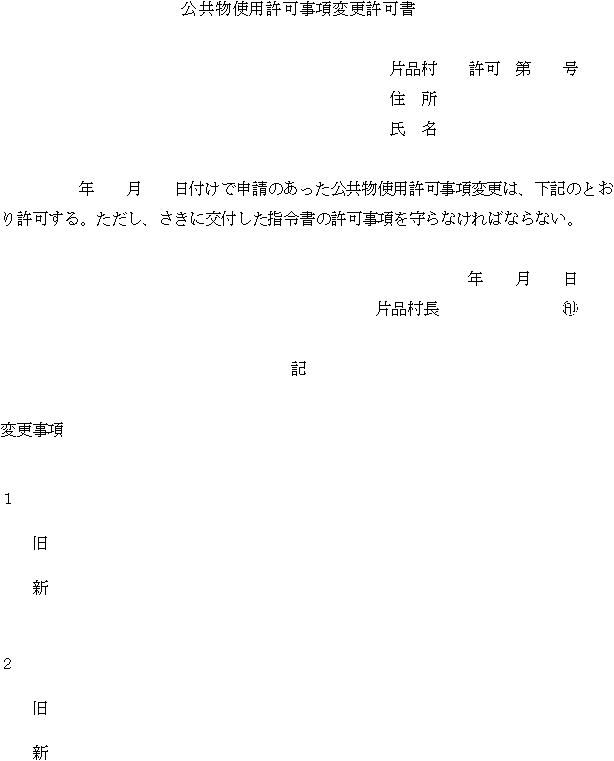
様式第17号
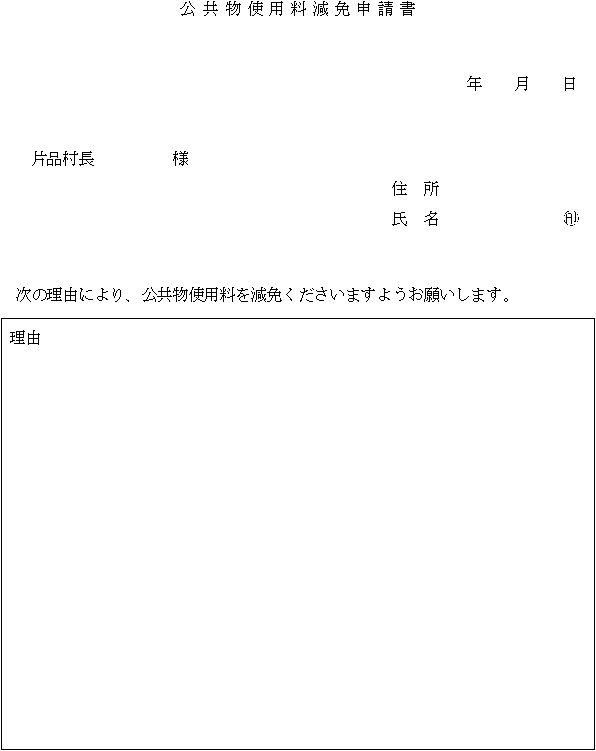
様式第18号
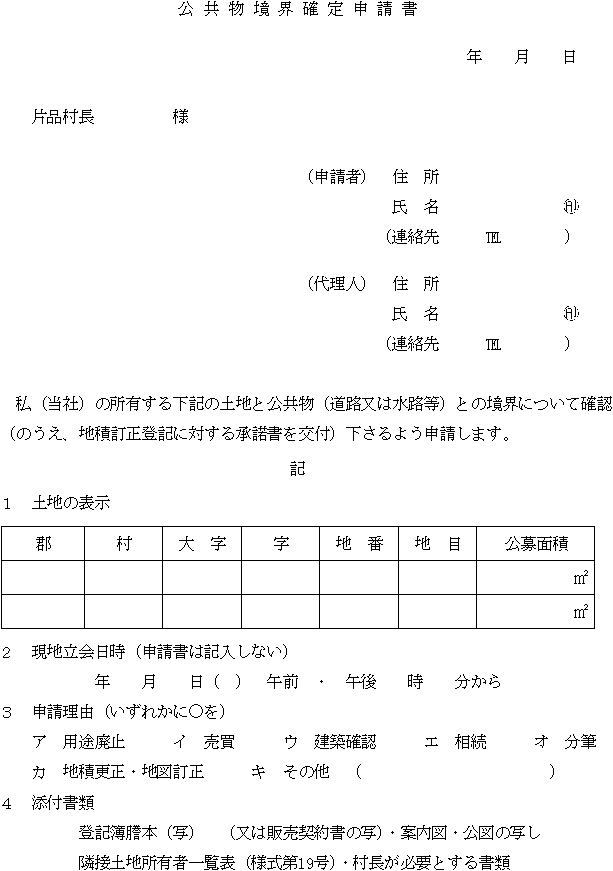
様式第19号
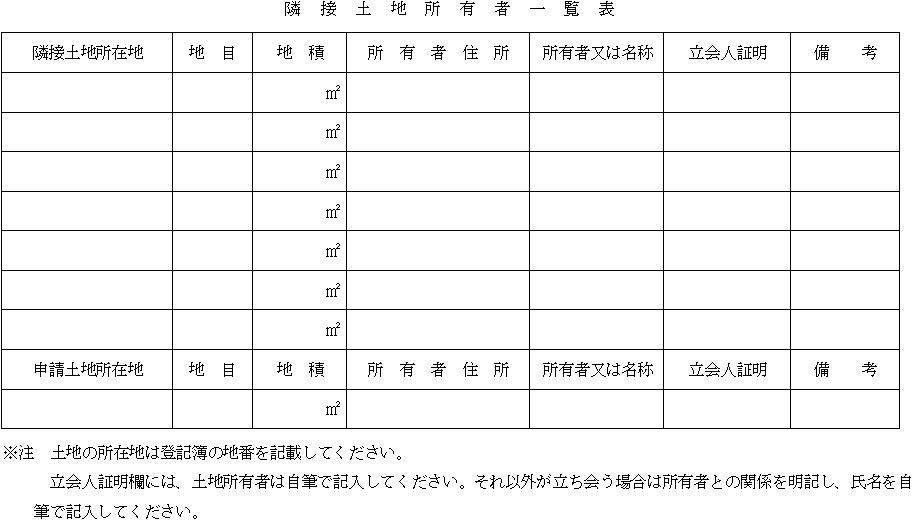
様式第20号
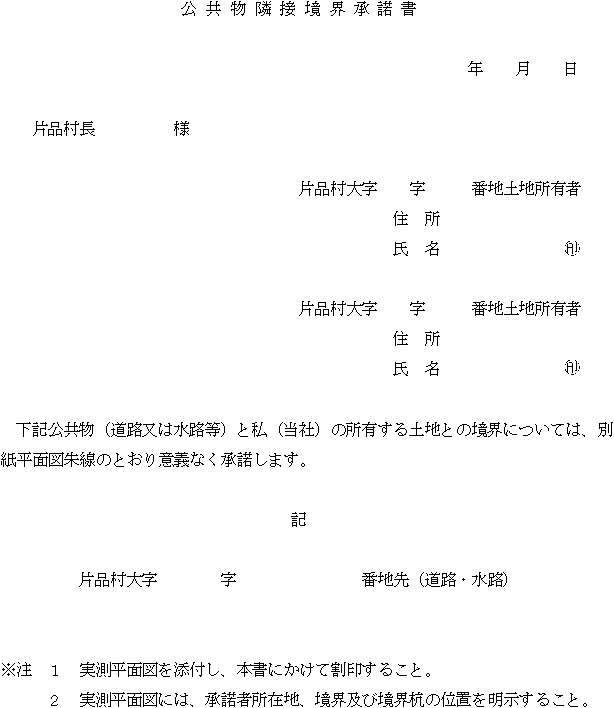
様式第21号
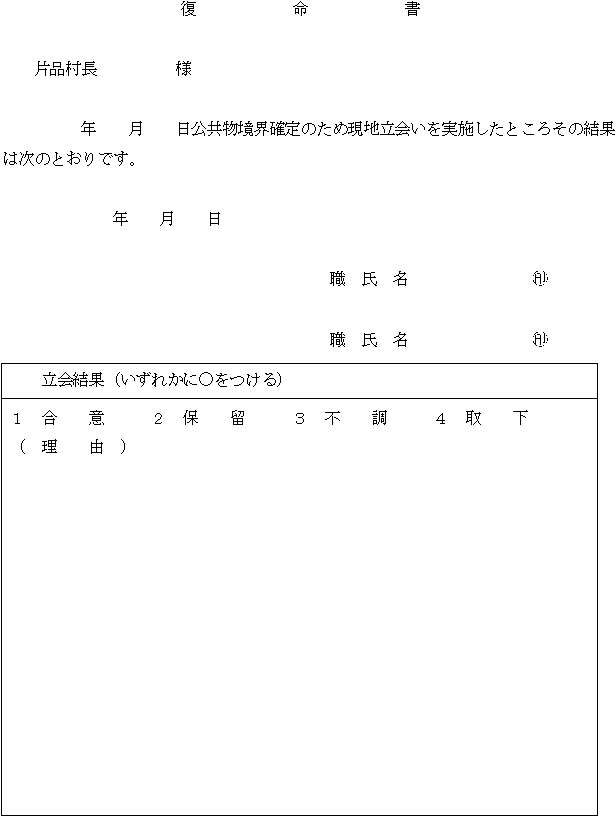
様式第22号
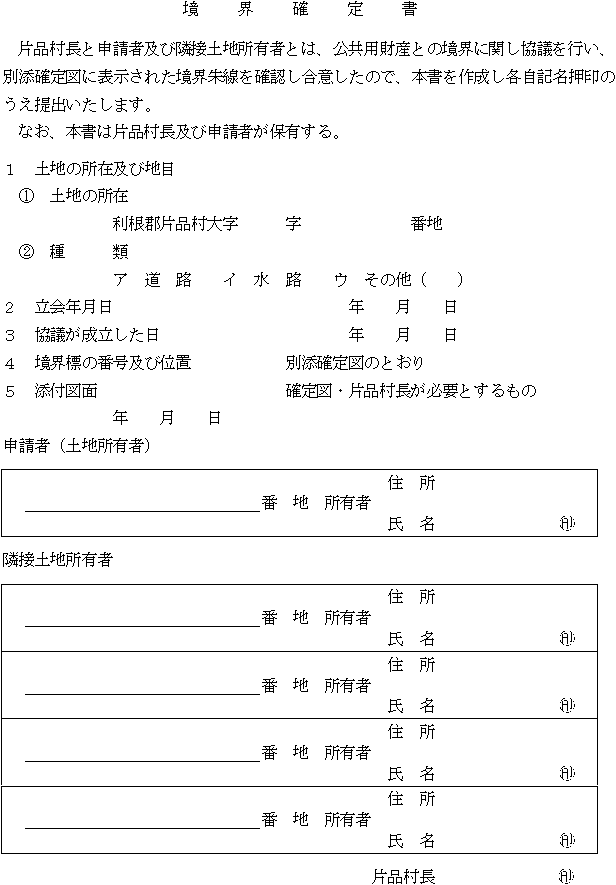
様式第23号
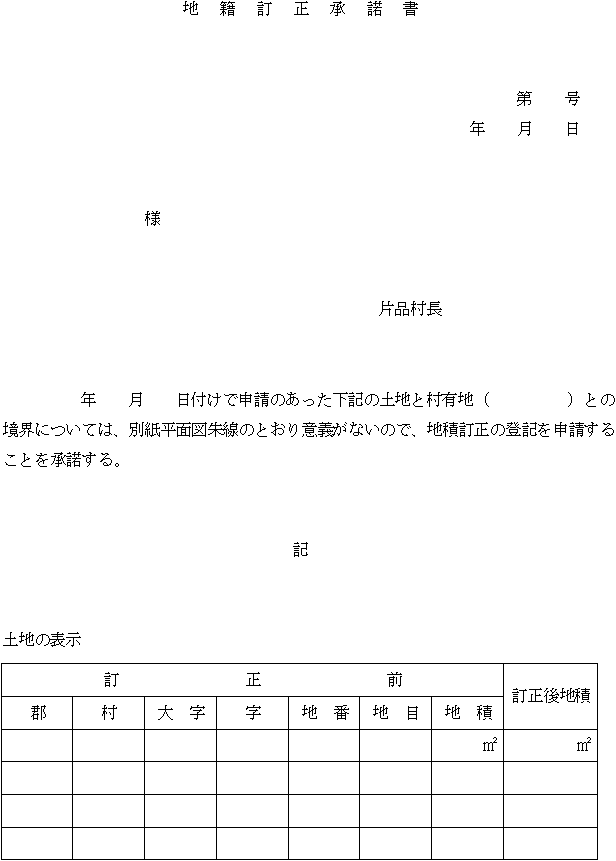
様式第24号