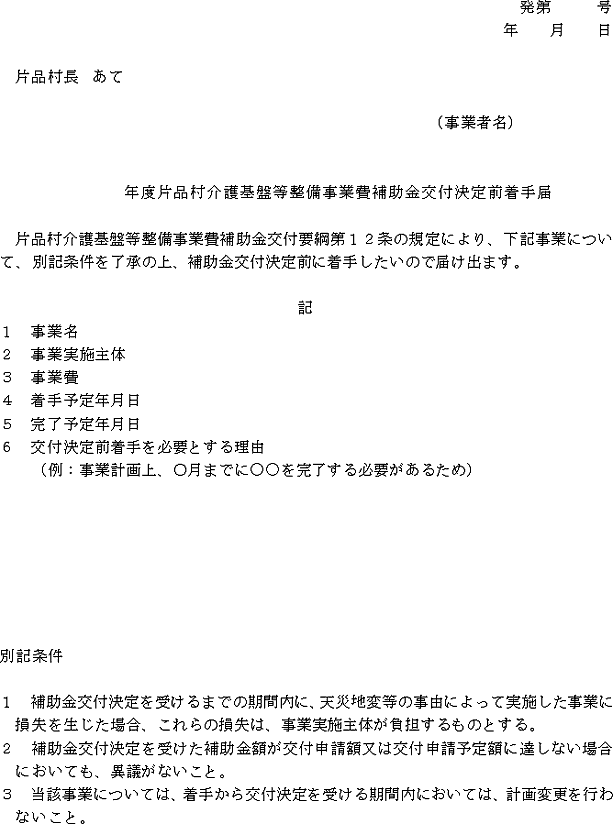○片品村介護基盤等整備事業費補助金交付要綱
平成29年9月1日要綱第16号
片品村介護基盤等整備事業費補助金交付要綱
(目的)
第1条 この補助金は、病床の機能分化及び連携に伴って増加する退院患者に対応しつつ、今後急増する高齢者単身世帯、夫婦のみの世帯、認知症高齢者等が可能な限り住み慣れた地域において継続して日常生活を営むことを可能とするため、地域密着型サービス(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。)その他の地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を促進することを目的とする。
(通則)
第2条 片品村介護基盤等整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に当たっては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)、厚生労働省所管補助金等交付規則(平成12年厚生省令第6号)、群馬県補助金等に関する規則(昭和31年群馬県規則第68号)、片品村補助金等交付規則(平成23年規則第15号)、群馬県地域医療介護総合確保基金条例(平成26年群馬県条例第74号)、地域医療介護総合確保基金管理運営要領(平成26年9月12日0912医政発第5号・老発0912第1号・保発0912第2号)及び群馬県介護基盤等整備事業費補助金交付要綱(平成21年介高第30175-2号。以下「県要綱」という。)の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。
(交付の対象等)
第3条 この補助金は、地域医療介護総合確保計画(地域における医療と介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第4条第1項の規定により群馬県が作成した計画をいう。以下同じ。)に基づき、県要綱第3条に規定する事業(以下「補助事業」という。)を交付の対象とする。
(補助金の対象除外)
第4条 この補助金は、次に掲げる費用については、交付の対象としないものとする。
(1) 既に実施している事業に係る費用
(2) 他の国庫負担又は補助制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業に要する費用
(3) 土地の買収、整地その他の個人の資産を形成する費用
(4) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に係る費用
(5) その他施設等整備に関する事業として適当と認められない費用
(交付額の算定方法)
第5条 この補助金の交付額は、予算の範囲内において県要綱第5条の規定に基づき算定するものとする。
(交付申請)
第6条 この補助金の交付を申請しようとする者は、別に定める期日までに別記様式第1号により申請書を村長に提出しなければならない。
(交付決定)
第7条 村長は、補助金の交付申請に基づき、当該申請に係る書類の審査、現地調査等により、当該補助金を交付すべきものと認めたときは、別記様式第2号により交付の決定を行う。
2 村長は、補助金の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて交付の決定をすることができる。
3 村長は、補助金の交付の決定をしたときは、次に掲げる事項を記載した文書を交付申請者に交付するものとする。この場合において、当該事項の一部の記載を行う必要がないと認めるときは、当該記載を省略することができる。
(1) 補助事業者(補助事業を行う者をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所
(2) 補助事業の名称、目的及び内容
(3) 補助金の額
(4) 補助事業者の自己負担割合又は金額
(5) 補助事業を完了すべき日
(6) 次条に規定する条件
(7) 補助事業者の義務に関する事項
(8) その他必要な事項
4 交付の決定に異議のある者は、特に定めのある場合のほか、交付の決定のあった日から15日以内に、村長に異議の申立て又は申請の取下げをしなければならない。
5 前項の異議の申立て又は申請の取下げは、文書をもってしなければならない。
(交付の条件)
第8条 この補助金の交付の決定には、次に掲げる条件が付されるものとする。
(1) 補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、村長の承認を受けなければならない。
(2) 補助事業を中止(一部の中止を含む。以下同じ。)又は廃止をする場合には、村長の承認を受けなければならない。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに村長に報告してその指示を受けなければならない。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械、器具その他の財産については、知事が別に定める期間を経過するまで、村長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
(5) 前号の承認に当たり、補助金の全部又は一部に相当する金額を村に納付させることがある。
(6) 村長の承認を受けて、第4号に定めた財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を村に納付させることがある。
(7) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業終了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
(8) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに別記様式第3号に準じて村長に報告しなければならない。この場合において、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の支部、支社、支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っているときは、本部、本社、本所等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。
(9) 前号本文の規定により村長に報告があった場合において、この助成金に係る仕入控除税額があることが確定したときは、当該仕入控除税額を村に返還しなければならない。
(10) この補助金と補助事業に係る収入及び支出との関係を明らかにした帳簿を作成し、当該補助事業に係る収入及び支出についての証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。
(11) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金については、この限りでない。
(12) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、村が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(13) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(14) この補助金の交付と対象経費を重複して、他の法律又は予算制度に基づく補助を受けてはならない。
(15) この補助金の交付を受けて消防法施行令(昭和36年政令第37号)第12条の規定によりスプリンクラー設置義務のない施設を新たに整備する場合は、本体施設の整備と併せて、スプリンクラー設備の設置を行うこと。
(16) 補助事業の遂行において次に掲げる者(以下「暴力団等」という。)から不当な要求行為を受けたときは、村に報告し、警察に通報すること。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている者
エ 暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている者
オ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者
カ 暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者
キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している者
ク 暴力団員と密接な交友関係を有する者
(17) 前各号に掲げる条件に違反した場合は、この補助金の全部又は一部を村に納付させることがある。
2 前項により付した条件に基づき、村長が承認又は指示する場合には、あらかじめ知事の承認又は指示を受けなければならない。
3 補助事業者から財産処分による収入又は補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の納付があった場合には、その納付額の全部又は一部を村に納付させることがある。
4 村は助成をした補助事業者が暴力団等であることが判明したときは、当該助成を取り消すこととする。
5 村は、補助事業者が暴力団等から不当な要求行為を受けたことが判明したときは、県に報告し、及び警察に通報するものとする。
(変更申請)
第9条 この補助金の交付決定後の事情の変更により、申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合には、別記様式第4号により行うものとする。
(変更交付決定)
第10条 村長は、前条に規定する追加交付申請等に基づき当該申請に係る書類の審査、現地調査その他の方法により、当該補助金を変更して交付すべきものと認めたときは、別記様式第5号により変更交付決定を行う。
(交付決定までの標準的期間)
第11条 村長は、第6条又は第9条による申請書が到達した日から起算して原則として2月以内に交付の決定(変更交付決定を含む。)を行うものとする。
(交付対象事業の着手)
第12条 交付対象事業の着手は、原則として、補助金交付決定通知書を受けて行うものとするが、当該年度において、やむを得ない事業により、補助金交付決定前に着手(以下「交付決定前着手」という。)することができるものとする。
2 補助事業者は、前項の交付決定前着手を行う必要がある場合は、補助金交付決定を受けるまでのあらゆる損失等は自らの責任となることを承知の上で、交付決定前着手届(別記様式8号)をあらかじめ提出するものとする。
(補助金の概算払)
第13条 村長は、必要があると認めるときは、予算の範囲内において概算払をすることができるものとする。
(実績報告等)
第14条 補助事業者は、別記様式第6号の報告書に関係書類を添えて、補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、当該承認通知を受理した日から起算して20日を経過した日)又は補助事業の完了の日の属する年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに、村長に提出するものとする。ただし、補助事業が翌年度にわたるときは、別記様式第7号による年度終了実績報告書をこの補助金の交付決定に係る村の会計年度の翌年度の4月15日までに、村長に提出するものとする。
(補助金の額の確定、交付、返還)
第15条 補助事業の完了に係る成果の報告を受けた場合においては、村長は、報告書等の書類の審査、現地調査等により、その成果がこの補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該額を交付するものとする。この場合において、交付すべき補助金の額を超える補助金が既に交付されているときは、当該補助事業者は、確定額を超えている部分に相当する額を、村長の定める期限内に返還しなければならない。
(補助事業者の義務)
第16条 補助事業者は、善良な管理者の注意をもって事業を行わなければならない。
(状況報告)
第17条 補助事業者は、別に定めるところにより、補助事業の執行状況を村長に報告しなければならない。
(補助事業遂行等の指示)
第18条 村長は、補助事業者が提出する報告等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って補助事業を遂行すべきことを指示することができる。
2 村長は、補助事業者がその指示に違反したと認めるときは、その者に対し、補助事業の遂行の一時停止を命ずることができる。
(事情変更による交付の決定の取消し等)
第19条 村長は、補助金の交付の決定をした場合においても、その後の事情の変更により補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
2 前項の取消しによって補助事業者に損害を与えた場合であって、申請に基づき村長が相当と認めたときは、適正化法施行令第6条第1項に規定する経費に相当する額の補助金を交付するものとする。
(交付の決定の取消し)
第20条 補助事業者が次のいずれかに該当する場合は、村長はこの補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正な手段によって補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令、条例、規則若しくはこれに基づく処分に違反したとき。
(4) 補助事業を予定の期間内に完了しなかったとき、又は完了することが不可能若しくは著しく困難であると村長が認めたとき。
(5) この補助金に係る県の交付決定の全部又は一部が取り消されたとき。
2 前項の規定による取消しは、交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。
(補助金の返還)
第21条 補助事業者は、この補助金の交付の決定が取り消されたときは、交付の決定を取り消された補助金を村長の定める期限内に返還しなければならない。
(是正のための措置)
第22条 第20条第1項の規定により交付の決定を取り消す場合においては、村長は、補助事業者に対し、補助金の交付の決定を取り消すことができる旨を告げ、その是正を求めるものとする。
(他の補助金の一時停止)
第23条 村長は、補助事業者が補助事業に係る返還金、加算金及び延滞金の全部又は一部を納付しないときは、これらの返還金、加算金及び延滞金の納付しない額を限度として、当該補助事業者に対して交付すべき補助金を交付しないことができる。
(加算金及び延滞金)
第24条 補助事業者は、第20条第1項に掲げる事由又はこれに準ずる事由によってこの補助金の返還を命ぜられたときは、その返還を命ぜられた補助金を受領した日から返還の日までの日数に応じ補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については既納額を控除した額)100円につき1日3銭の割合で計算した額の範囲内で村長の定める額の加算金を納付しなければならない。
2 補助事業者が補助金の返還を命ぜられこれを納期日までに返還しなかったときは、納期の翌日から納付の日までの日数に応じ、その延滞額100円につき1日3銭の割合で計算した額の範囲内で村長の定める額の延滞金を納付しなければならない。
3 第1項に規定する加算金の最高額の計算方法は、適正化法施行令第10条の規定の例によるものとする。
(理由の提示)
第25条 村長は、補助金の交付の決定の取消し、補助事業の遂行の指示若しくは一時停止の命令又は補助事業の是正のための措置の指示を行うときは、当該補助事業者に対してその理由を示さなければならない。
(その他)
第26条 村長は、必要があるときは、補助事業者に対して報告をさせ、又は職員をして必要な調査をさせることができる。
2 前項の報告の聴取又は調査に対して、補助事業者は協力しなければならない。
第27条 特別の事情により第5条、第6条、第9条及び第14条に定める算定方法及び手続によることができない場合には、あらかじめ村長の承認を受けてその定めるところによるものとする。
附 則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月26日要綱第9号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度の事業から適用する。
附 則(令和5年2月22日要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第6条関係)
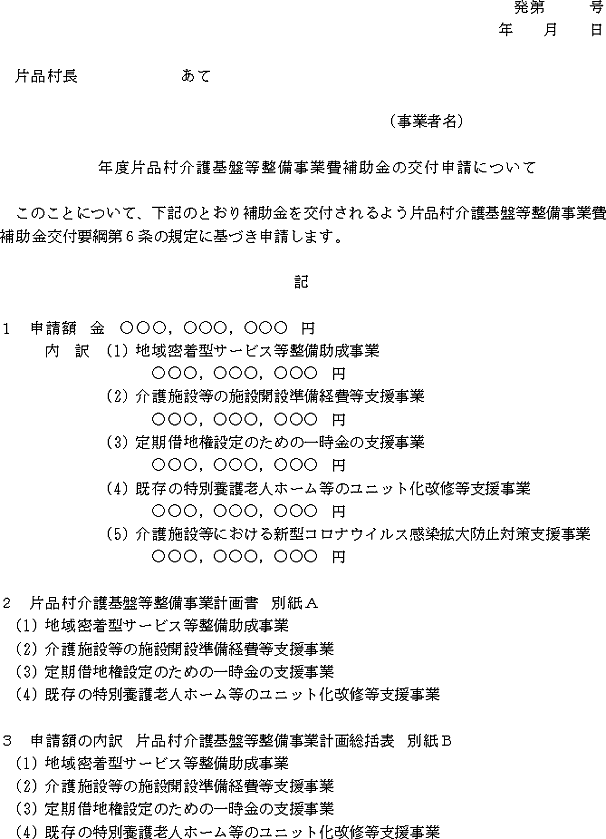
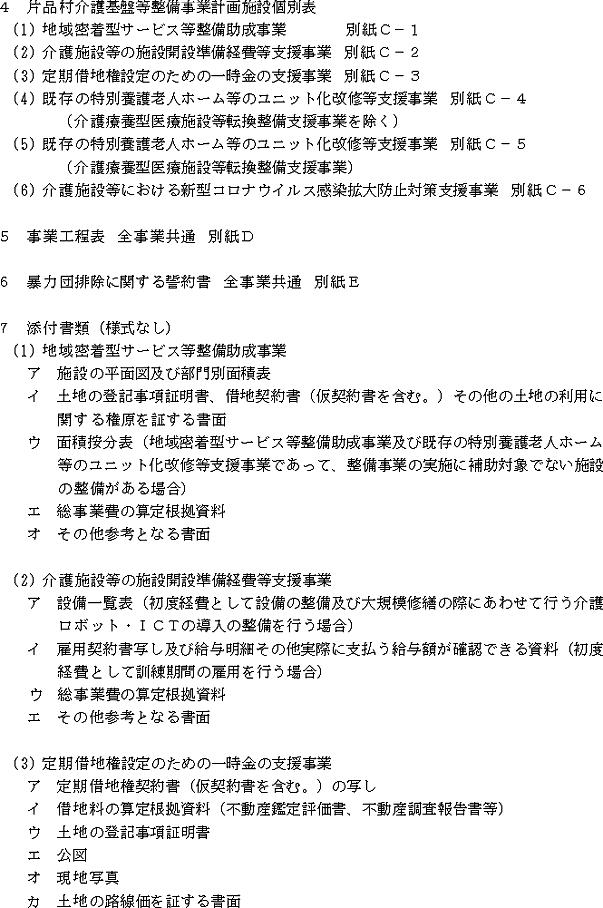
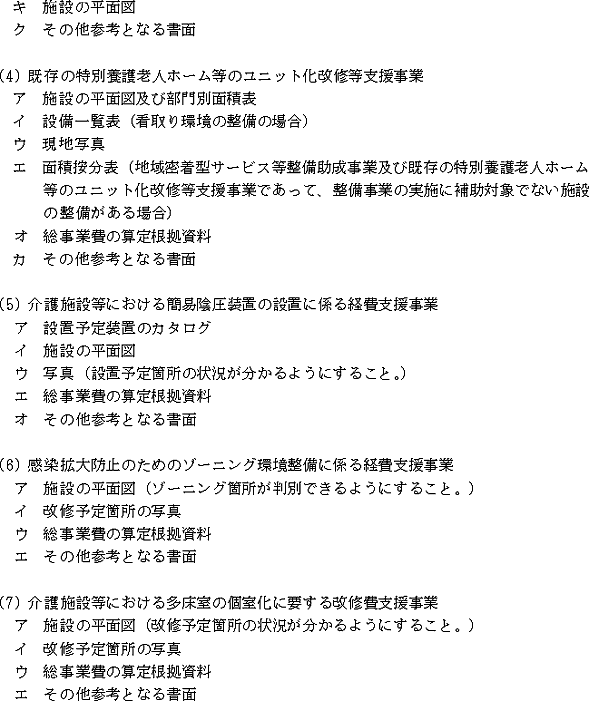
別記様式第2号(第7条関係)
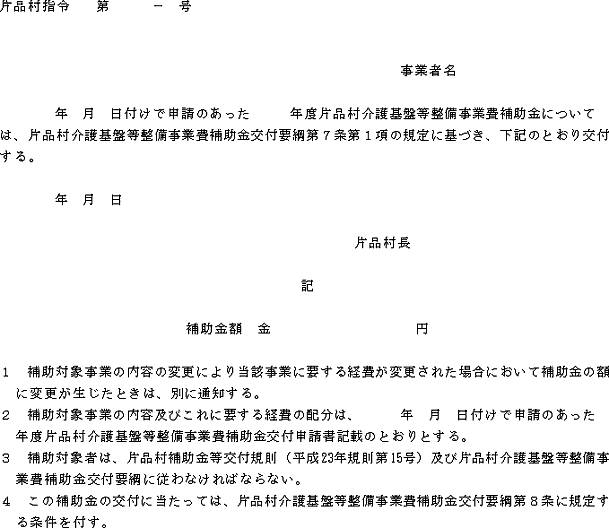
別記様式第3号(第8条関係)
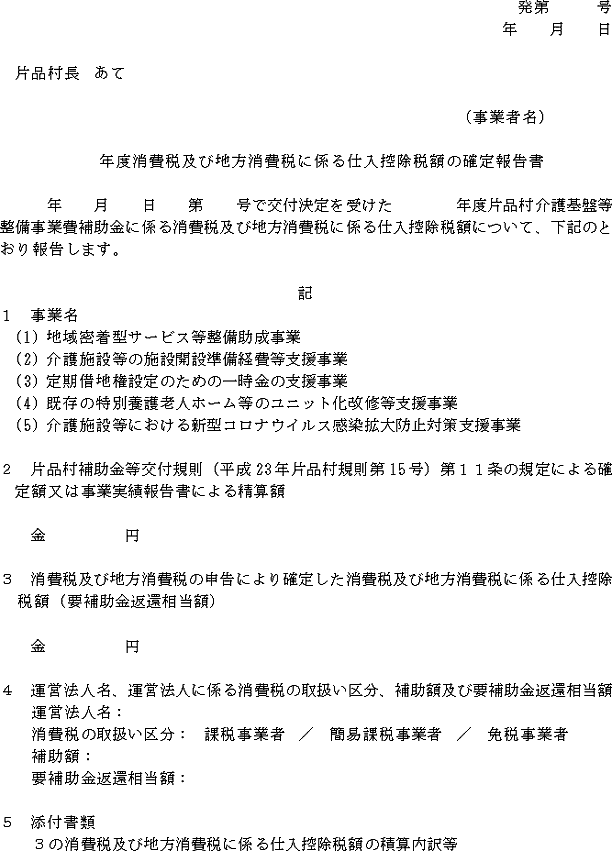
別記様式第4号(第9条関係)
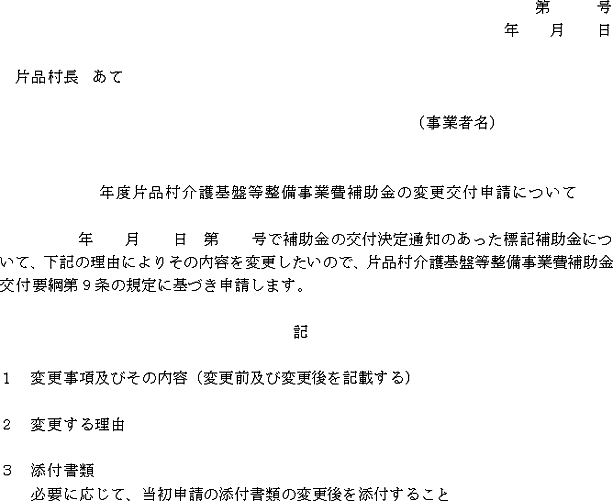
別記様式第5号(第10条関係)
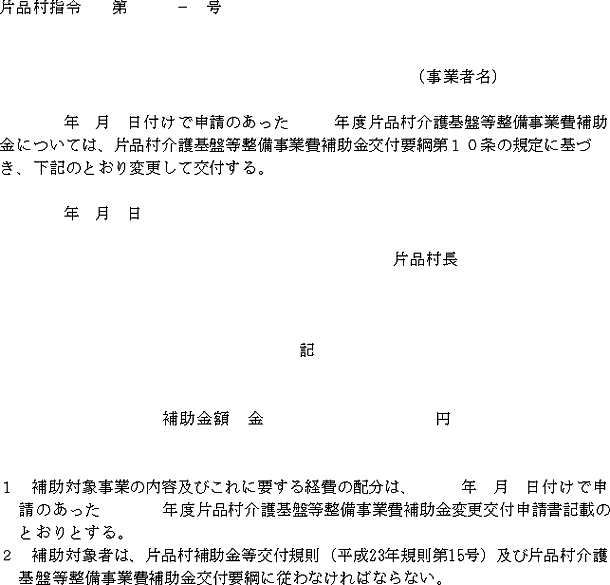
別記様式第6号(第14条関係)
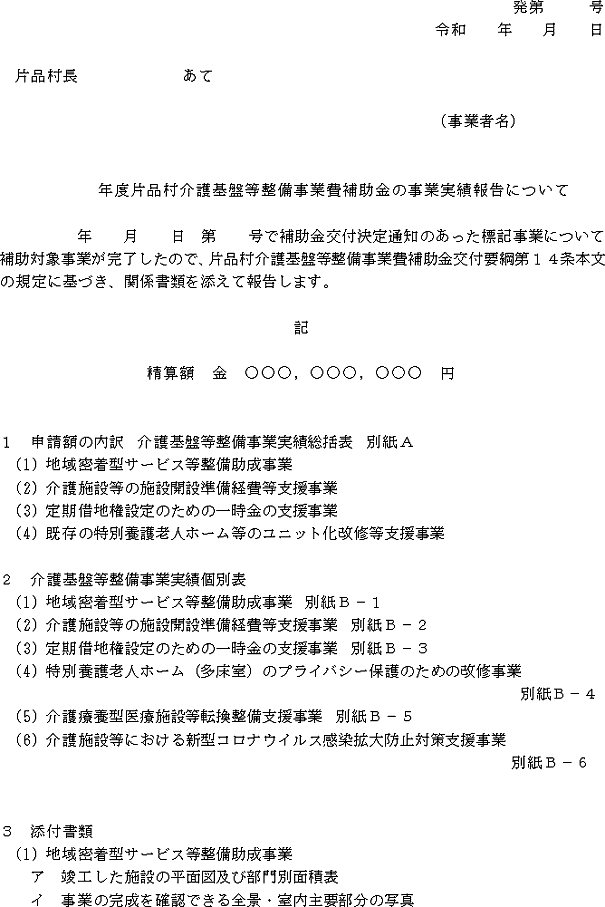
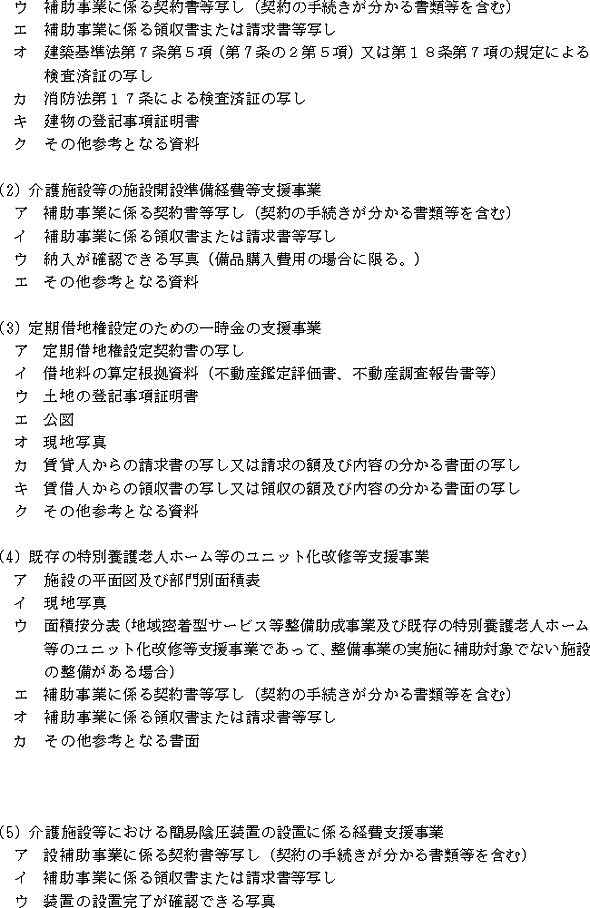
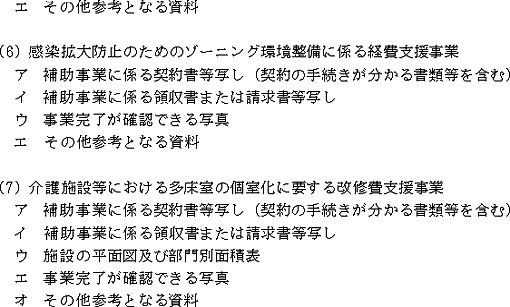
別記様式第7号(第14条関係)
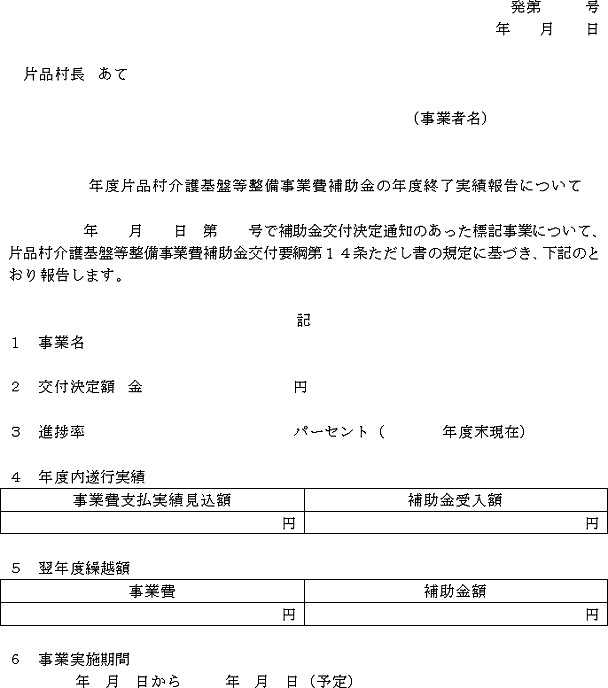
別記様式第8号(第12条関係)